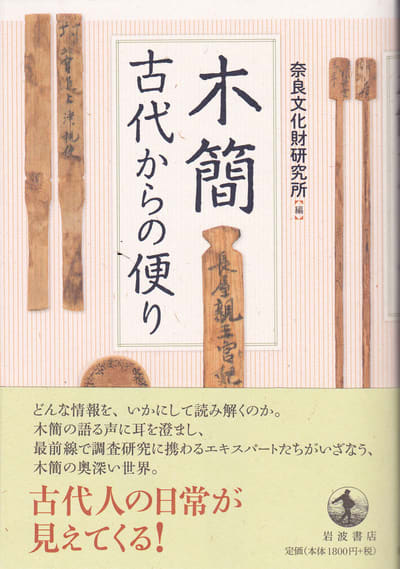今日も、いい天気だったのだが……

またまた珍品ゲット。
イエローサブマリンのカード。
66枚揃え。
Anglo Confectioneryというお菓子メーカーが1960年代後半にイギリスのHalifaxにあって、このようなカードをおまけにして、風船ガムを販売していた。
人気のサッカーなどを題材を中心にしていた。
並べると、なかなか壮観だ。
著作権の問題はないのだと思うが、映画の最後に4人が飛び入りのように出てくる場面は、映像ではなく、イラストになっている。

このカードの凄いのは、全部並べて裏返すと、一つの大きな絵になるところ。
主要キャラクターは、全部出ているし、4人もイラストだが、顔を出している。
ナイスなデザイン。

まだアップルはなかったか。
両方とも1968年のことだと思うのだが。
著作権は、King Features & SUBAになっている。
日本には、この1セットしかない?

またまた珍品ゲット。
イエローサブマリンのカード。
66枚揃え。
Anglo Confectioneryというお菓子メーカーが1960年代後半にイギリスのHalifaxにあって、このようなカードをおまけにして、風船ガムを販売していた。
人気のサッカーなどを題材を中心にしていた。
並べると、なかなか壮観だ。
著作権の問題はないのだと思うが、映画の最後に4人が飛び入りのように出てくる場面は、映像ではなく、イラストになっている。

このカードの凄いのは、全部並べて裏返すと、一つの大きな絵になるところ。
主要キャラクターは、全部出ているし、4人もイラストだが、顔を出している。
ナイスなデザイン。

まだアップルはなかったか。
両方とも1968年のことだと思うのだが。
著作権は、King Features & SUBAになっている。
日本には、この1セットしかない?