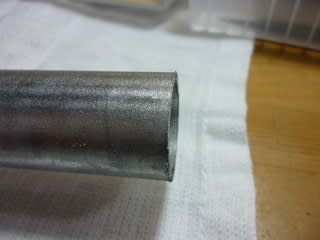最近のアヘッド構造のフォークコラムには ステムを取付ける為には
プレッシャーアンカー等が必要です 今回は KUWAHARAのヒラメの
商品を使ってみます

前回フレームにフォークを装着したので今回はハンドル周りを取付けます


ハンドルの高さを調整しますがその時に使うのが
このコラムスペーサー 色々な巾(高さ)の物が
用意されていますが メーカーに依り外径がやや
違うのは少し参ります
そしてもう一つ必要なのが フォークコラムの内部に
装着する部品 右上のギザギザの物はスターファングル
ナット コラム内に打ち込みますがこれはカーボンコラム
には使えません
左のシルバーの物はプレッシャーアンカーと呼ばれるもので
カーボンにはこちらが必要です

今回用意したのは ヒラメ 30JA-30U マルチプレッシャー
アンカーと言う商品名で価格は 1890円
KUWAHARA と言う会社から出ていますかが ここは
ポンプヘッドの HIRAME で有名ですね


構造を見てみましょう 写真左が底側です
左より テーパーナット・分割テーパーリング・テーパー押子
固定ボルト・セッティングナット・キャップボルト の名称です
ネジを含め全体にグリスとオイルを塗布しておきます
テーパー部の潤滑と防錆が目的です

ハンドルをコラムに差し込みました


ステムの上下にスペーサーを入れています、先日塗った
ブルーが結構綺麗ですね
このステアリングコラムの内部にプレッシャーアンカーを
取付けます

コラム内部に滑り止め剤を塗っておきますが
ここでの目的は防錆です


プレッシャーアンカーの固定ボルトを締め込み
コラムの内径近くまで 分割テーパーリングを
拡げます ここで使う工具は 6mmのアーレンキーで
ネジは正ネジです
又このボルトにはキャップボルトを締め込む為の
内ネジが切って有ります


リングを拡げた状態です この商品はコラムの内径
18.9mm~25.6mmまで対応しています

そのリングをコラムの中へ入れますが 後で
指で押し込める位にしておきます ここが少し
加減の難しい処かな?

ヘッドキャップを用意します これは金属製を
使います


キャップ用のボルトにセッティングナットを
キャップに軽く当たるまで締め込みます
ナットは細い方を上に使います


キャップを固定ボルトの内ネジに入れ軽く最後まで
締め込みます 使う工具は 5mmのアーレンキーで
ネジは正ネジです

そしてキャップを奥まで押し込みます

そして一旦キャップを取り外し 6mmのアーレンキーで
固定ボルトを締め込みます ここはヒラメの資料では
130~150kgf と書かれています


それだけの高トルクが必要なら この位の長さの
アーレンキーで目一杯締めたくらいでしょう
ただ最近の資料では カーボンコラムに使う場合は
締め付けトルクは、適度に調整して下さいと書かれて
います この表現では 自分の感覚が頼りですね

プレッシャーアンカーはこの様に収まっています
先程、セッティングナットを用いキャップを
押し込んだのは この適度な深さを決める為ですね


そして セッティングナットを取り外したキャップを
装着します ここは 5mmのアーレンキーを使います

ヘッドのガタつきをヘッドキャップで調整しながら
ステムのクランプボルトを締め込みます

プレッシャーアンカーと ハンドル周りの取付けが完了です
今回のヒラメのアンカー これはしっかりしていて良いですね
前回の記事 【 フォークコラムに 化粧する 】
次の記事 【 ロードレーサー 変速機の取り付け 】
プレッシャーアンカー等が必要です 今回は KUWAHARAのヒラメの
商品を使ってみます

前回フレームにフォークを装着したので今回はハンドル周りを取付けます


ハンドルの高さを調整しますがその時に使うのが
このコラムスペーサー 色々な巾(高さ)の物が
用意されていますが メーカーに依り外径がやや
違うのは少し参ります
そしてもう一つ必要なのが フォークコラムの内部に
装着する部品 右上のギザギザの物はスターファングル
ナット コラム内に打ち込みますがこれはカーボンコラム
には使えません
左のシルバーの物はプレッシャーアンカーと呼ばれるもので
カーボンにはこちらが必要です

今回用意したのは ヒラメ 30JA-30U マルチプレッシャー
アンカーと言う商品名で価格は 1890円
KUWAHARA と言う会社から出ていますかが ここは
ポンプヘッドの HIRAME で有名ですね


構造を見てみましょう 写真左が底側です
左より テーパーナット・分割テーパーリング・テーパー押子
固定ボルト・セッティングナット・キャップボルト の名称です
ネジを含め全体にグリスとオイルを塗布しておきます
テーパー部の潤滑と防錆が目的です

ハンドルをコラムに差し込みました


ステムの上下にスペーサーを入れています、先日塗った
ブルーが結構綺麗ですね
このステアリングコラムの内部にプレッシャーアンカーを
取付けます

コラム内部に滑り止め剤を塗っておきますが
ここでの目的は防錆です


プレッシャーアンカーの固定ボルトを締め込み
コラムの内径近くまで 分割テーパーリングを
拡げます ここで使う工具は 6mmのアーレンキーで
ネジは正ネジです
又このボルトにはキャップボルトを締め込む為の
内ネジが切って有ります


リングを拡げた状態です この商品はコラムの内径
18.9mm~25.6mmまで対応しています

そのリングをコラムの中へ入れますが 後で
指で押し込める位にしておきます ここが少し
加減の難しい処かな?

ヘッドキャップを用意します これは金属製を
使います


キャップ用のボルトにセッティングナットを
キャップに軽く当たるまで締め込みます
ナットは細い方を上に使います


キャップを固定ボルトの内ネジに入れ軽く最後まで
締め込みます 使う工具は 5mmのアーレンキーで
ネジは正ネジです

そしてキャップを奥まで押し込みます

そして一旦キャップを取り外し 6mmのアーレンキーで
固定ボルトを締め込みます ここはヒラメの資料では
130~150kgf と書かれています


それだけの高トルクが必要なら この位の長さの
アーレンキーで目一杯締めたくらいでしょう
ただ最近の資料では カーボンコラムに使う場合は
締め付けトルクは、適度に調整して下さいと書かれて
います この表現では 自分の感覚が頼りですね

プレッシャーアンカーはこの様に収まっています
先程、セッティングナットを用いキャップを
押し込んだのは この適度な深さを決める為ですね


そして セッティングナットを取り外したキャップを
装着します ここは 5mmのアーレンキーを使います

ヘッドのガタつきをヘッドキャップで調整しながら
ステムのクランプボルトを締め込みます

プレッシャーアンカーと ハンドル周りの取付けが完了です
今回のヒラメのアンカー これはしっかりしていて良いですね
前回の記事 【 フォークコラムに 化粧する 】
次の記事 【 ロードレーサー 変速機の取り付け 】