わたしから電話をしたのか、それとも架かってきたのか思いだせないが、急遽出かけることになった行先は天理市の山間部。
これまで取材した民俗行事に「御誓(ごせ)」という呼び名のオコナイ行事や新しく建築された地蔵堂の落慶法要に市指定無形文化財の「さる祭り」がある福住町別所の永照寺下之坊だ。
別所では住民が正月初めに行うイタダキの膳とかカンマツリも取材させてもらったことがある。
下之坊は真言宗豊山派の古刹。
推定800年とされるバラモン大杉を求める旅人が来訪する坊でもあるが、普段は扉も開いていない。
かつては上之坊、中之坊に現存する下之坊など六坊があった長谷寺末寺。
延享元年(1744)の大火災によって消失。
翌年に下之坊が唯一再建され、
本堂の修復に庫裏を建てた。
本堂はやがて文化五年(1808)および明治22年ころに修理された。
庫裏の解体作業が行われている場は通行止め。
下之坊の看板が立つ地より迂回する里道を歩く。
坂道であるが急坂でもない。
ところが、この頃の私の身体では急ぐこともできない。
足があがらず一歩、一歩を踏みしめるように登っていく。

小雨に濡れた美しいサザンカの花が目に入った。
人家があるわけでもない処に一般的なサザンカが植わっていた。

ここは最近になって整備された墓石が建つ。
雨に打たれて散り落ちた花が愛おしい。
小雨であるが、雨は止まない。

登ってきた道は円を描く。
稲田も合わせて円を描く。
刈り取った田に伐採した竹。
何に使うのだろうか。
そんなことを思いながら坂を登ってきた。
緩やかな坂のように見えるが、私にとっては堪える坂だった。
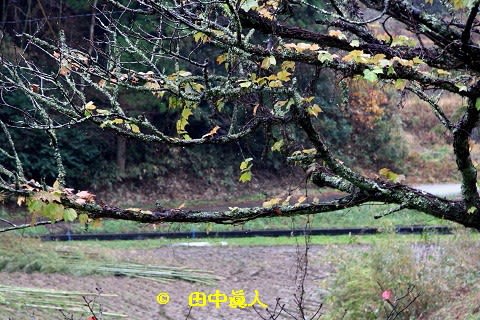
濡れた樹木に侘びを感じる。
ツタが絡まった桜の木でもなさそうな樹木の老齢に何を物語るのか・・。
業者の手によって解体作業される庫裏の姿に思いをだぶらせる。
解体作業の邪魔にならないように一歩、二歩下がって佇んでいた電話の主。
カメラを肩から下げたままだった。
この場で大きな声をあげては作業する人たちに迷惑をかける。
作業をそっと見守るように立ち尽くす。
しばらくすれば、休憩ではないが、やや小休止。

その間を見計らって下之坊前の境内に移動する。
翌月の12月23日は別所のさる祭り。
村の人たちはこの場の境内で綱を結う。
架かってきた電話の主のお誘いに急行した理由がある。
キリンちゃん重機で屋根を解体する。
解体が済めば、その作業は二度と見ることがない。
少しでもカメラに収めて記録しておきたい。
そう思って急行する。
作業は午後3時半になっても終わっていなかった。
着いたときは、終わりかけの屋根の解体作業中。
なんとか間に合った。

油圧式ショベルカーのキリンちゃん重機の先は首振り。
解体した部位を首振り爪(グラップル)で掴んで下ろす。

廃材は木材、金属などに分別して大型ダンプトラックに積み込んでいた。
庫裏の解体と聞いて確かめたかった屋根の部材がある。
茅葺であればススダケがあるはずだ。

下之坊の庫裏の内部は若干であるが、拝見したことがある。
「御誓(ごせ)」という呼び名のオコナイ行事を取材したおりに拝見した扉の向こう側。
庫裏座敷に住職を迎えた村の人たちがおられた。
土間だったことは覚えている。
竃はなかったように思える。
座敷は上がっていないから囲炉裏があったかどうか判らない。
大屋根の解体に金属物があった。
たぶんにトタン板であろう。
むき出しになった屋根の支柱に古いものもあれば新しい材のように見えるものもある。
藁綱で編んだ割り竹もあるが、ススダケは見当たらない。

延享元年(1744)の大火災によって消失した翌年に下之坊本堂の修復の際に庫裏を建てた記録があるようだ。
本堂は文化五年(1808)および明治22年ころに修理されたという記録もあるが、庫裏については判らない。
材の様相から延享二年(1745)築と思われる庫裏は、その後のいつか判らないが、何度か修理されたようようだ。
むき出しになった真新しい材が見える。
その状態から推定するに昭和の時代のように思えた。
(H27.11.25 EOS40D撮影)
これまで取材した民俗行事に「御誓(ごせ)」という呼び名のオコナイ行事や新しく建築された地蔵堂の落慶法要に市指定無形文化財の「さる祭り」がある福住町別所の永照寺下之坊だ。
別所では住民が正月初めに行うイタダキの膳とかカンマツリも取材させてもらったことがある。
下之坊は真言宗豊山派の古刹。
推定800年とされるバラモン大杉を求める旅人が来訪する坊でもあるが、普段は扉も開いていない。
かつては上之坊、中之坊に現存する下之坊など六坊があった長谷寺末寺。
延享元年(1744)の大火災によって消失。
翌年に下之坊が唯一再建され、
本堂の修復に庫裏を建てた。
本堂はやがて文化五年(1808)および明治22年ころに修理された。
庫裏の解体作業が行われている場は通行止め。
下之坊の看板が立つ地より迂回する里道を歩く。
坂道であるが急坂でもない。
ところが、この頃の私の身体では急ぐこともできない。
足があがらず一歩、一歩を踏みしめるように登っていく。

小雨に濡れた美しいサザンカの花が目に入った。
人家があるわけでもない処に一般的なサザンカが植わっていた。

ここは最近になって整備された墓石が建つ。
雨に打たれて散り落ちた花が愛おしい。
小雨であるが、雨は止まない。

登ってきた道は円を描く。
稲田も合わせて円を描く。
刈り取った田に伐採した竹。
何に使うのだろうか。
そんなことを思いながら坂を登ってきた。
緩やかな坂のように見えるが、私にとっては堪える坂だった。
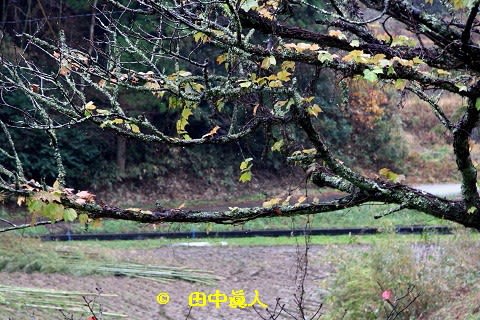
濡れた樹木に侘びを感じる。
ツタが絡まった桜の木でもなさそうな樹木の老齢に何を物語るのか・・。
業者の手によって解体作業される庫裏の姿に思いをだぶらせる。
解体作業の邪魔にならないように一歩、二歩下がって佇んでいた電話の主。
カメラを肩から下げたままだった。
この場で大きな声をあげては作業する人たちに迷惑をかける。
作業をそっと見守るように立ち尽くす。
しばらくすれば、休憩ではないが、やや小休止。

その間を見計らって下之坊前の境内に移動する。
翌月の12月23日は別所のさる祭り。
村の人たちはこの場の境内で綱を結う。
架かってきた電話の主のお誘いに急行した理由がある。
キリンちゃん重機で屋根を解体する。
解体が済めば、その作業は二度と見ることがない。
少しでもカメラに収めて記録しておきたい。
そう思って急行する。
作業は午後3時半になっても終わっていなかった。
着いたときは、終わりかけの屋根の解体作業中。
なんとか間に合った。

油圧式ショベルカーのキリンちゃん重機の先は首振り。
解体した部位を首振り爪(グラップル)で掴んで下ろす。

廃材は木材、金属などに分別して大型ダンプトラックに積み込んでいた。
庫裏の解体と聞いて確かめたかった屋根の部材がある。
茅葺であればススダケがあるはずだ。

下之坊の庫裏の内部は若干であるが、拝見したことがある。
「御誓(ごせ)」という呼び名のオコナイ行事を取材したおりに拝見した扉の向こう側。
庫裏座敷に住職を迎えた村の人たちがおられた。
土間だったことは覚えている。
竃はなかったように思える。
座敷は上がっていないから囲炉裏があったかどうか判らない。
大屋根の解体に金属物があった。
たぶんにトタン板であろう。
むき出しになった屋根の支柱に古いものもあれば新しい材のように見えるものもある。
藁綱で編んだ割り竹もあるが、ススダケは見当たらない。

延享元年(1744)の大火災によって消失した翌年に下之坊本堂の修復の際に庫裏を建てた記録があるようだ。
本堂は文化五年(1808)および明治22年ころに修理されたという記録もあるが、庫裏については判らない。
材の様相から延享二年(1745)築と思われる庫裏は、その後のいつか判らないが、何度か修理されたようようだ。
むき出しになった真新しい材が見える。
その状態から推定するに昭和の時代のように思えた。
(H27.11.25 EOS40D撮影)










