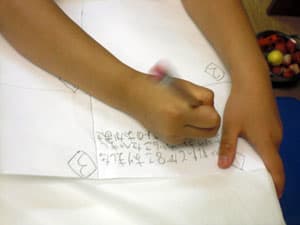子どもというのは、歩けるようになる前に、歩く練習をはじめるし、
会話ができるようになる前に、声を発し、交互に非言語のやりとりをし、大人の口真似をはじめるなど、
会話の練習をはじめます。
『アフォーダンスの心理学』には、次のような記述があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
子どもがおぼつかないながらもある行為を開始する……危なっかしい足どりで歩いたり、
本を顔の前に持ってバブバブ言ったり、
ボールからとんでもなく離れたところで
バットを振ったりする……と、
それは養育者によってその意味を゛充たし゛はじめよという
合図として受け取られる。
(『アフォーダンスの心理学』エドワード・S・リード 新曜社より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
子どもが、今はまだできない何かをやりはじめるとき、
身近な大人がそのサインを正確に受け取って、
子どもと環境の間にある落差を調節してあげると、
新しい技能の習得を促進する特別な場が生まれます。
子どもが公園内などの縁石(路肩にしかれるコンクリート)の上を歩きたがるとき、
「子どもの身体はまだ、バランスを取りながらそれを渡っていけるほど
身体能力も視力も発達していない」
「縁石はときどき途切れていて危険」など、
子どものやりたがることと、できることの間には落差があるはずです。
でも、もし大人が手をつないでバランスを取ってあげたり、転んだ時、助け起こしてあげたり、
縁石が途切れるとき、注意をうながしてあげれば、
子どもは何度もそれに取くみ、
しまいには、自分ひとりでバランスを取ってそれを渡っていくようになるでしょう。
(道路の縁石は危険ですから、安全な場所で子どもにフォローしてあげてください)
『アフォーダンスの心理学』では、
「この認識の集団的ブートストラッピングの力は過小評価されるべきでない」
と告げています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2歳児がおもちゃの聴診器のイヤホンを自分のこめかみに当て、
ぬいぐるみのクマを診察しているところなどを
見ると大人はわけしり顔で微笑む。
だが<充たされざる意味>を抱えながら
活動にたずさわる子どもの傾向性は
文化史の一翼を担うほどの力をもつのだ。
(『アフォーダンスの心理学』より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今日は、1歳7カ月の★ちゃん、2歳6カ月の●ちゃん、2歳8カ月の○ちゃんの
レッスンでした。
幼稚園がお休みだったので、★ちゃんのお姉ちゃんの☆ちゃんも
レッスンにいっしょに参加してもらいました。
★ちゃんも、●ちゃんも、○ちゃんも、
それぞれが個性的な自分の気質にあった
方法で、まだ正確にはできないおぼつかない態度で何かをはじめ、
「その訓練を見守りつつフォローする場を作ってちょうだい!」というサインを
親御さんに送っていました。
★ちゃんは、人と人の間で交わされるコミュニケーションに敏感で、
お友だちや大人のすることはすぐにまねてみて、
まだ意味がよくわからないうちから人の輪に割り込んで積極的に
「わかった風のこと」をします。
お姉ちゃんたちがじゃんけんをしていたら、「じゃんけんぽん」とタイミングだけ合わせて
手を出してみたり、
お母さんがお姉ちゃんのお世話をするのをまねてみたり。
今日も、お姉ちゃんの☆ちゃんが、「工作がしたい」というので、
準備をしようとすると、
★ちゃんが椅子を抱えて、「★ちゃんの」と言い、
もうひとつ椅子を取りにいって、「☆ちゃんの」と言って、自分と☆ちゃんの椅子をちゃっかり並べて、
準備万端という顔をしていました。
それから、私が☆ちゃんにマジックと紙を準備すると、
★ちゃんが、マジックを一本ずつ取り出しては「あい、どーぞ」と☆ちゃんに手渡していました。
★ちゃんはまだ1歳7カ月ですから、
意味がわかっていてお姉ちゃんの手助けをしているというより、
意味もわからず形だけ「わかっている風」のことをしながら、
その行為をしながら、周囲のフィードバックを受けて、自分のしていることの
意味を理解していっているのです。
「ああ、こうすれば、お姉ちゃんが座るときに助かるのか」
「ああ、こうすれば、自分の渡したマジックでお姉ちゃんが絵を描いて、
次の色を渡すと、今度はそれで絵を描くのか……!」と、後から
最初に自分のしていたことの意味を充たしているのです。
●ちゃんは自分で最初から最後までやりとげて、それを完璧にできるようになるまで
繰り返したいと思うがんばりやさん。
お母さんに出す「おぼつかない状態で始める」サインというのは、
見えやすい技能である場合がほとんどです。
お手伝いが大好きで、皿洗いも手順通りにやりたがるそうです。
虹色教室でも、できるようになるのに練習の必要な課題を見つけては、
お母さんにそれを見守ってもらいたがります。
練習中は、●ちゃん自身の集中力もすごいのですが、
「お母さん、見てて!」というお母さんに求める集中力も強いです。
●ちゃんは、完璧に自分で仕上げないと嫌なようで、
何かに集中しはじめると、お母さんと自分だけの閉ざされた世界を
作りたがります。
まだ2歳代ですから、そんなときまで、「お友だちと……」と気にかけずに、
お母さんとふたりの絆をしっかり育むのがいいんじゃないかと
思っています。
いろいろできるようになって自信がついたところで、
今度は自分からお友だちを求めて積極的に働きかけていくはずです。
○ちゃんは、周囲をよく観察して、自分の内面の世界を広げていくことを
好む子です。
意味から切り離された「部分」だけのもので遊ぶことを
極端に嫌がります。
今日も、○ちゃんのお母さんがドールハウスの階段だけ見せると、
ずっとおだやかに機嫌よく遊んでいたのに、
かんしゃくを起こして、「これはお家になきゃダメ」と半べそをかいていました。
そこで、ドールハウスを用意して、ぬいぐるみを選ばせると、
自分でストーリーを作って遊びはじめました。
○ちゃんは、とてもおませでしっかりしている一方で、
マイペースで自分の世界から出たがらないところがあります。
大人が「これしたら?」「あれしたら?」と勧めると拒否して、
前にしたことがある遊びを繰り返したがるので、
表面的には、「おぼつかないながらもある行為をはじめている」ように見えないかもしれません。
でも、○ちゃんの視線の先や、
時折、自分の空想遊びに取り入れる新しい要素に着目していると、
年上の☆ちゃんの行動や大人の行動をていねいに観察していて、
それを自分のスペースで再現している姿がありました。
○ちゃんの「お母さん!私はこんなことを始めたい!手伝って!」というサインは、
○ちゃんが、身の周りの世界で働いている人や祖父母、動物などを
観察して、その世界観を自分のごっこ遊びのなかで再現しながら
意味を探っていこうとするのに、
よりそってほしいというものなのでしょう。
○ちゃんは、お気にいりの黒猫のぬいぐるみを、
ドールハウスの窓から何度も顔だけ外に出させては、
お外を観察させて、
またお家に引きこんでレモンをたべさせる……という遊び繰り返していました。
きっと○ちゃん自身も、自分が黒猫ちゃんにさせていたように、
強い好奇心と洞察力のある観察眼で
お外の観察を繰り返しては
お母さんのもとにもどって、いつもの安心できるペースで遊べるように
してほしいと望んでいるのでしょう。

「本物の卵が割りたい」という子どもたちと。↑