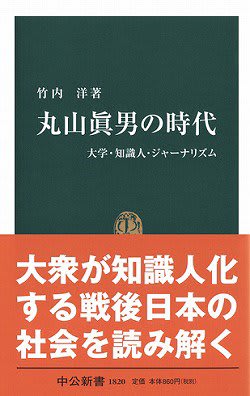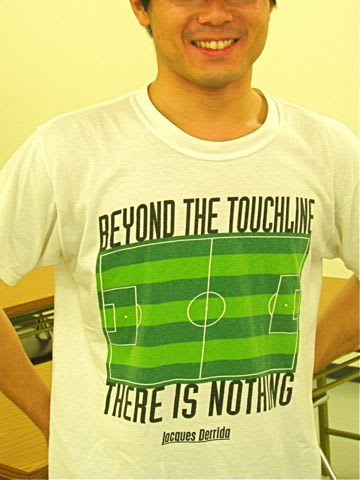以下は、NYタイムズへの東浩紀氏の寄稿です。
いってることは至極まっとうですが、やはり、国家や民族の問題でのナイーヴさ、底の浅さが露呈しているのではないでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/magnolia1977/archives/52018307.html
私もこの状況の中で人々が助け合い、忍耐をしている状況を大いに評価しますが、それを日本民族や日本国家の固有性に還元するのはいかかがなものかと思います。とりわけ次のようにいわれてしまうとやはり引いてしまうところがあるのです。
「有害なシニシズムの中で麻痺していた、自分の中の公共精神や愛国的な自分を発見した経験は色褪せることは無いだろう。」
公共精神はいざ知らず、愛国的な自分の発見とはいささか危ういのではないだろうかと思ってしまうのです。
私はゆえあって氏の書いたものをざっと観たことがありますが、いささかの危惧を感じたのがいまわかるような気がします。1980年代以降のポストモダン世代は、国家や共同体との相克を経験してはいないのです。
だからそれへの違和感をもった経歴を単なる「シニシズム」で片付けて、何かの契機で日本人万歳、日本国万歳に容易に「転向」しうるのです。
繰り返しますが、私はこの事態への人々の冷静な対応を敬意をもってみています。もちろんそこには、買い占めといった不協和音などもあるのですが、全体としては感服せざるをえない状況にあると思います。
ただしこれを、日本国家、日本民族の固有性のようなものに還元する氏の論調には危ういものを感じざるを得ないのです。ましてやそれが、「愛国的な自分を発見した経験は色褪せることは無いだろう。」などといわれてしまうとなおさらです。
こうした「転回」を遂げた氏の論調が今後どのようなものになるかを見守りたいと思います。
(デリダ読みがどしてああなるかなぁ?単なるコンストラクションではないの?)