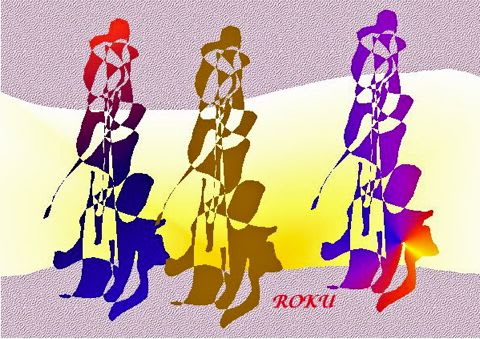
久々に芝居を観た。A・チェーホフの『三人姉妹』である。
学生時代の先輩がプロヂューサーをつとめたもので、私たち同世代が10人ほど集まっての観劇となった。
チェーホフの芝居といえば、戦前戦後を通じての「新劇」のデフォルトの演題であった。崩壊しつつある帝政ロシアでの貴族階級を中心とした不安は格好の素材であったし、その後に来たるべき新しい社会を予感させるという意味でもそれらの不安はやがてポジティヴなものの到来を予感させるものとも受け止められていた。
しかし、今や私たちは帝政ロシアの崩壊後にきたもの、戦中戦後すぐにはよく解らなかったそれらの全貌、そしてそれらの崩壊をも既にして知ってしまっている。したがって、チェーホフの描いた不安の延長上に来たるべきものを安易に語ることはもはやできない。
むしろ、私たちはチェーホフが描き出した不安そのものへ、そこでの登場人物が抱くアイデンティティの危機そのものへと今一度連れ戻されることとなる。
幕開き早々に語られる三姉妹のこぞっての希望は、地方の町からモスクワへと帰ること、そしてそこで肯定されてあったものへと回帰することであった。
しかし、その果たされぬ夢を抱きながらも愛し愛され、あるいはその錯綜とした関係に翻弄されながら時は進むだろう。そしてそこではもはやモスクワへの帰還は共通の夢としての役割を果たさないものへと変貌してゆくだろう。
「ヴ・ナロッド(民衆の中へ)」や労働への志向、どうしようもなくのしかかる現状や不意に訪れる別れなど、三姉妹はそれぞれ新たな選択肢を生きなければならない。
ラストシーン、軍楽隊の演奏をバックに「あれを聞いていると分かる気がする。なんのために私たちが生きているのか、なんのために苦しんでいるのか」というセリフが心身を共鳴させるように搾り出される。そして「でも、私たちは生きてゆくのだわ」という肯定の言葉が語られる。
そこにはもはや、モスクワという「中心」から切り離されてあるというルサンチマンはない。むしろその運命を「ウイ」といって引き受けてゆく決意すら見出すことができる。
最後に、すべての人物が去ったあと、舞台には赤子が眠ると思われる白い乳母車が残される。そこにはあたかも、新しく生まれいづるものへと託されるもの、期待や希望のようなものが集約されているように思った。
プロヂューサーに確認したところ、そうした演出意図はないということだったが、私は勝手にそう決め込んで舞台中央の白い乳母車をくっきりと視覚にもそして頭脳にも刻みこんでこの芝居を見終えたのであった。
帝政ロシアの末期という時代や場所を超えて、チェーホフの持つ普遍性を改めて知った舞台であった。顧みれば、この不透明な時代への不安、そしてそこでのアイディンティティ・クライシスは現に私たちが直面している問題でもあるのだ。
私たちは、それでも彼女ら三姉妹のように、顔を上げて「ウイ」といいうるだろうか。
*2月5、7、8、9、10、11日(6日は休演)
5、11日は13時30分開演 7、8、9日は18時30分開演
10日は13時30分 18時30分の二回公演
それぞれ開演15分前に入場するとおまけの催しがあります。
*愛知県芸術劇場小ホール
*上演台本・演出 鐘下辰男

















