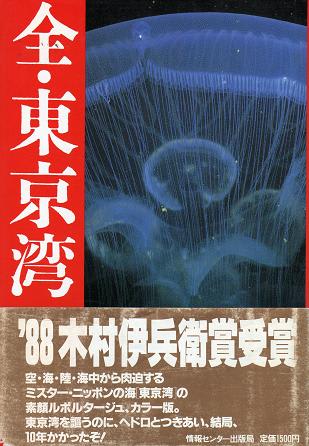NHKで放送された『大都会の海 知られざる東京湾』を観た。
スズキやアイナメ、さらには食物連鎖の最初のほうに位置するプランクトンや小さい甲殻類などの姿が記録されている。われわれの食べている魚介類にも、東京湾で獲れたものは多い。また、これが東京湾なのかと眼を見開いてしまうような色とりどりのサンゴもいる。
面白いのは、内湾と外湾との境界として、はっきりと識別できる色の違いがあり、温度や塩分濃度の違いによる「熱塩フロント」を形成していることだ。内湾は、工場の温排水のためプランクトンが豊富に生育し、外湾からの温かい海流とぶつかるフロントでは生態系にとって恵まれた条件になっている。
さらには、外敵が少ないため、マイワシやスズキがよく育っている。これは養殖ではないし、多くの人間が関与した生態系を作り上げているとみるべきなのだろう。もはや、死の海と言われたかつての面影はない。われわれの生活と海とが遠くなっているから気が付かないのだ。
ただ、変に穴ぼこを掘ってしまったために青潮はまだ発生している。栄養塩のバランスが崩れる結果の赤潮もなくなっていない。干潟やヨシが極めて少なくなってしまった結果、ハマグリは姿を消した。番組では、横浜でアマモの再生に取り組んでいる方々を紹介しているし、三番瀬でもこれは取り組まれていることだ。
その意味では、人間が関与することを前提とした自然の回復にはまだ時間も多くの努力も必要だということなのだろう。
ただ、東京湾には豊かでわれわれも連鎖の中に入った生態系があることには、あらためて凄いことだと感じる。水中写真の中村征夫が木村伊兵衛賞を受けた『全・東京湾』(情報センター出版局)には、知らないで判断することが如何に自然やそこで働く漁師などの方々への敬意を欠く結果になるかを示すエピソードがある。南葛西の主婦は、東京湾で魚が獲れることを聞かされて、「まあ、東京湾で漁してるなんて、そんなの食べたくないわ」と言ってしまう。多分、私を含め、多くの人の感覚はそれに近いものだろう。
しかし、有害物質も、有機物も、かなり少ないものとなっている。ただ、汚染ゼロはありえないが、それはわれわれの経済活動に起因する。外洋もイメージしにくいだけで汚染はゼロではない。自分も生態系の一部であること、そこから逃れる安全なエリアはないこと、さらには自分の排出に責任を持つことは胸に刻んでおいてよいことだと思う。
『全・東京湾』には、豊穣で多様でいじらしい生物の数々と、そこで生活する方々が記録されている。生物と人々との間には境界があえて設定されていないように感じさせる。もう20年近く前の本ではあるが、まだまだ驚きを孕んでいる。
それにしても、三番瀬で養殖し、天日干しで作られた海苔を食べてみたいものだ。まだあるのだろうか。この本には、干していると海苔がピシッと鳴くこと、大企業の海苔は見栄えをよくするために変に厚くしていること、などが紹介されている。
番組は、6/6深夜に再放送されるようだ。見逃した方には一見をおすすめしたい。
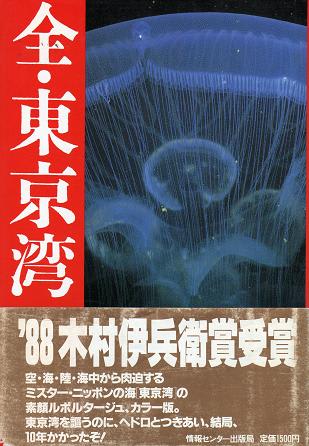
スズキやアイナメ、さらには食物連鎖の最初のほうに位置するプランクトンや小さい甲殻類などの姿が記録されている。われわれの食べている魚介類にも、東京湾で獲れたものは多い。また、これが東京湾なのかと眼を見開いてしまうような色とりどりのサンゴもいる。
面白いのは、内湾と外湾との境界として、はっきりと識別できる色の違いがあり、温度や塩分濃度の違いによる「熱塩フロント」を形成していることだ。内湾は、工場の温排水のためプランクトンが豊富に生育し、外湾からの温かい海流とぶつかるフロントでは生態系にとって恵まれた条件になっている。
さらには、外敵が少ないため、マイワシやスズキがよく育っている。これは養殖ではないし、多くの人間が関与した生態系を作り上げているとみるべきなのだろう。もはや、死の海と言われたかつての面影はない。われわれの生活と海とが遠くなっているから気が付かないのだ。
ただ、変に穴ぼこを掘ってしまったために青潮はまだ発生している。栄養塩のバランスが崩れる結果の赤潮もなくなっていない。干潟やヨシが極めて少なくなってしまった結果、ハマグリは姿を消した。番組では、横浜でアマモの再生に取り組んでいる方々を紹介しているし、三番瀬でもこれは取り組まれていることだ。
その意味では、人間が関与することを前提とした自然の回復にはまだ時間も多くの努力も必要だということなのだろう。
ただ、東京湾には豊かでわれわれも連鎖の中に入った生態系があることには、あらためて凄いことだと感じる。水中写真の中村征夫が木村伊兵衛賞を受けた『全・東京湾』(情報センター出版局)には、知らないで判断することが如何に自然やそこで働く漁師などの方々への敬意を欠く結果になるかを示すエピソードがある。南葛西の主婦は、東京湾で魚が獲れることを聞かされて、「まあ、東京湾で漁してるなんて、そんなの食べたくないわ」と言ってしまう。多分、私を含め、多くの人の感覚はそれに近いものだろう。
しかし、有害物質も、有機物も、かなり少ないものとなっている。ただ、汚染ゼロはありえないが、それはわれわれの経済活動に起因する。外洋もイメージしにくいだけで汚染はゼロではない。自分も生態系の一部であること、そこから逃れる安全なエリアはないこと、さらには自分の排出に責任を持つことは胸に刻んでおいてよいことだと思う。
『全・東京湾』には、豊穣で多様でいじらしい生物の数々と、そこで生活する方々が記録されている。生物と人々との間には境界があえて設定されていないように感じさせる。もう20年近く前の本ではあるが、まだまだ驚きを孕んでいる。
それにしても、三番瀬で養殖し、天日干しで作られた海苔を食べてみたいものだ。まだあるのだろうか。この本には、干していると海苔がピシッと鳴くこと、大企業の海苔は見栄えをよくするために変に厚くしていること、などが紹介されている。
番組は、6/6深夜に再放送されるようだ。見逃した方には一見をおすすめしたい。