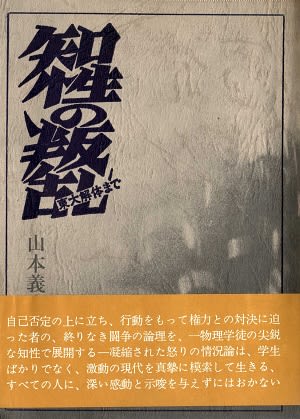やっと観た、ジョニー・トーの最新作『冷たい雨に撃て、約束の銃弾を』(2009年)。原題は『Vengeance 復仇』であり、例によって邦題化が改悪となっている。

開始間際に駆け込んで、喉を湿らせる間もなく上映が始まった。いきなりの衝撃。そこから終了まで、口の中の粘膜はからからに乾いてヒビさえ入り、最後にはちょっと泣いてしまった。『エグザイル/絆』(2006年)もそうだったが、2時間に満たない時間に信じられないくらい多くの旨みを詰め込み、ひたすらに濃密な映画となっている。
アンソニー・ウォン、ラム・シュー、ラム・カートン、サイモン・ヤムといったジョニー・トー映画の常連がまた登場するが、日活アクションのようなマンネリにはならない。プロットではなく、腕をびしりと伸ばした動きや、星座を思わせる彼らの配置に、濃いトーらしさを漂わせている。
相変わらずの工夫に目を見張る。夜のバーベキュー場、スープを鉄板に注いでの湯気の中の銃撃。殺しの検証シーンにおける、犯行時とのオーバーラップ。唐突にナプキンで目隠しをしての銃の組み立て競争。古紙の束を転がしながらの銃撃戦。身体から弾を取り出すときの細かな描写。記憶をなくしていく男の前に現れる死者たち。
アンソニー・ウォンの演じるクワイ(『ザ・ミッション 非情の罠』、『エグザイル/絆』に続いて演じる同じ役)は、一瞬の逡巡を見せつつも「乗りかかった船だ」と義理を貫き、死を迎えるときには、頬を地面に付けてにやりと笑う。ウォンだけではない。トー映画の人物たちは、自らの運命を悟り、淡々ともがきながら、それに従ってゆくように思える。そして、これもトーの定番、料理と食事によって家族や友情のつながりがナマの形で示される。
余談だが、トー映画には頻繁にカメラが登場する。『エグザイル/絆』でのコンタレックス・ブルズアイ、『文雀』でのバルナックライカとローライ二眼レフ、『イエスタデイ、ワンスモア』での何かの二眼レフ、『フルタイム・キラー』でのペンタックスZ-1Pといった具合だ。本作では、ポラロイド・SX-70が重要な役目を果たす。『PTU』の撮影時映像では、トーはツァイスイコン・ホロゴンウルトラワイドを握り締めていたし、作品を観れば観るほどトーが熱狂的なカメラファンだという確信が強くなっていく。
とにかく、大傑作『エグザイル/絆』に勝るとも劣らない超弩級の作品だ。まだ動悸が激しいような気がする。
●ジョニー・トー作品
○『エグザイル/絆』
○『文雀』(邦題『スリ』)、『エレクション』
○『ブレイキング・ニュース』
○『フルタイム・キラー』
○『僕は君のために蝶になる』、『スー・チー in ミスター・パーフェクト』
○『ターンレフト・ターンライト』
○『ザ・ミッション 非情の掟』
○『PTU』