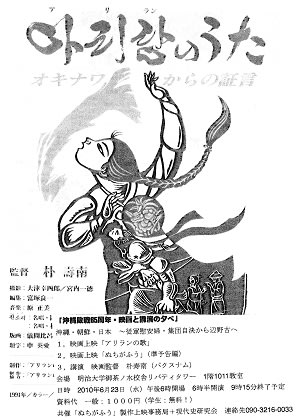丸川哲史『台湾ナショナリズム 東アジア近代のアポリア』(講談社選書メチエ、2010年)を読む。迷いを見せながらの叙述スタイルはあまり好みではないが、このことは、台湾という国家/地域の位置付けがサブタイトルにあるように難題であることの裏返しかもしれない。
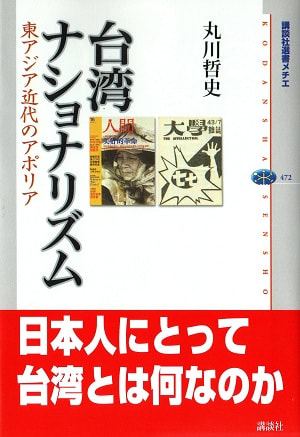
近現代の歴史を追うならば、1871年:台湾住民による宮古島漂着島民殺害事件(清朝は「化外の民」が行ったこととして責任回避)、1874年:日本による台湾出兵、1895年:前年の日清戦争での清国敗戦により日本への割譲(下関条約)、1945年:日本敗戦と中国本土からの蒋介石・国民党上陸、といった具合である。支配者が変わっただけでなく、その背後にある米国や中国の思惑も変わり続けた。
以下に、いくつか重要な指摘をピックアップしてみる。
●日本による台湾の植民地化にはコスト上の問題があり、売却論さえあった。メリットは、植民地経営の成功が、西洋列強と同等の地位にあることを証明するところにあった。
●1943年のカイロ会談(中国も参加)は、戦後の体制を方向付けるものであった。その際、蒋介石は、次のように考えていた。台湾は日本が中国から奪った土地であり返還。琉球はかつて日本と清国との両属であったものの、琉球処分を経て、日清戦争前には日本の主権下にあったから、米国と中国との共同管理でもよい。朝鮮は独立してもよい(中国は、かつて一度も朝鮮の独立を明確に承認したことがなかった)。
●特に琉球については、カイロ会談は、沖縄の地上戦と軍事占領への道筋を確定したとも言うことができる。また、日本の台湾出兵(1874年)における、琉球住民を日本人として扱った日本政府の言動を容認しているとも言うことができる。
●朝鮮と台湾の扱いの違いは、丸ごと支配か、割譲かの差による。
●現在は比較的「親日」的とみなされる台湾だが、終戦直後は全く異なり、中華民国の統治が日本帝国主義から解放してくれるとの期待があった。しかし、その後の二・二八事件などにより、中国本土に対する失望が蔓延していく。
●台湾での皇民化と中国戦線への加担は、日本の中国戦略に対抗した国民党が戦後台湾を支配したため、タブー視されることとなった。
●戦後日本でも、数年後の台湾でも、土地改革がドラスティックに行われた。これが結果として、「赤化」防止につながった。逆に、中国共産党の勝利は、政治運動としての土地改革の展開による効果が大きかった。
●朝鮮戦争(1950年)により、米国は台湾を反共の側に設定しなおした。同時に、台湾における中華民国の事実上の主権状態が成立した。もし朝鮮戦争がなかったなら、台湾は中国本土から派遣された解放軍によって「解放」されていた可能性が高い。その意味で、朝鮮戦争という出来事は、台湾においてタブー視されている。
●中華民国政府は、米国の意向を汲んで、日本に賠償請求を行わなかった。冷戦状況にあって、アジアの反共ブロック内の対決を回避させるための圧力であった。その後、日台関係は、米国を間においての日本の保守政治家と台湾高官との交流が主となり、次いで経済的な結びつきが増加していった。その際には植民地時代の人脈が復活した。日本においては植民地時代の記憶が忘却された。
●国民党政府にとって、米国に頼らなければならないとする見方と、米国流の民主主義や米国の後ろ盾を持つ台湾独立派への敵視とがジレンマとなっていた。
●イラクのクウェート侵攻(1990年)に続く湾岸戦争(1991年)は、大陸中国の「台湾解放」のシミュレーションでもあった。人民解放軍にとって、米国の介入による粉砕は、「台湾解放」が不可能であることを思い知らされる結果であった。
●革命を経ていない台湾は、濃厚に中華的なものを残している。台湾ナショナリズムとは、近代以降・冷戦以降の特定の時代意識の反映と見ることが妥当である。
●日本における「主権」意識は低い。これは、戦後日本が、主権の一部を米国に譲渡し続ける状態を「自然化」させているからであり、他のアジア国/地域と比べると奇怪である。韓国では、米軍基地を抱えることが不自然な状態との自覚が強い。台湾から70年代に米軍基地が撤去されたのは、大陸政府によるネゴシエーションの結果であり、これはまた「主権」という意味ではグレーゾーンに入る。
強く印象に残るのは、日本における歴史意識の希薄さと、その裏返しとしての突出した米国依存である。