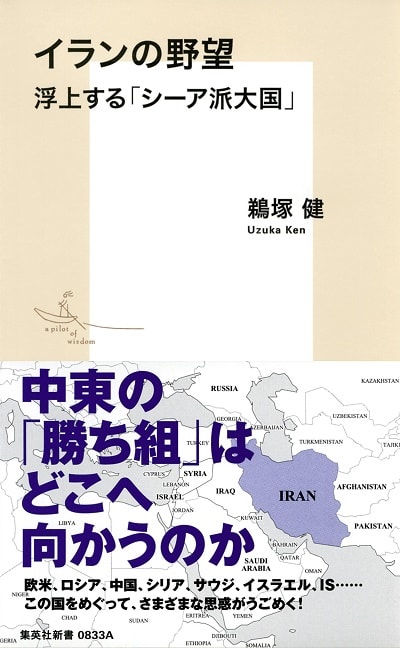日比谷図書館にて、西嶋真治『抗いの記 記録作家 林えいだい』の試写会(2016/6/9)。

林えいだいという、筑豊の記録作家がいる。現在は癌を患っているが、副作用で作家活動に支障をきたすため、抗癌剤の服用を止めている。もう手が自由に動かないため、手に万年筆をセロテープで固定して書き続ける凄さがある。それというのも、林さんには、書いておかねばならぬという強い原動力があるからだ。
筑豊の炭鉱には地獄谷と呼ばれるところがいくつもあり、そこには必ず貧しい朝鮮人と、地図には載っていない「アリラン峠」があった。故郷に帰りたくても帰れない、脱走するには道なき山道をゆかねばならない。そして脱走を図った朝鮮人労働者を殴り殺した、炭鉱の労務係もいた。
豊州炭鉱では水没事故(1960年)で67人が生き埋めになり、遺体の発掘は翌年の国の勧告で断念された。炭鉱労働者はそのように扱われ、エネルギー政策の転換とともに流民となった。なかでも朝鮮人労働者に対する扱いは凄惨を極め、空腹を訴えると、出征している兵士よりも恵まれているとして殴られた。これは日本の植民地支配とエネルギー政策が作り上げた、人為的な地獄であった。
朝鮮人労働者たちは、死んでもなお尊厳を与えられなかった。古河大峰炭鉱跡付近にある日向墓地には、身寄りも引き取り手もない死者が、ボタ石を墓として葬られているという。
こういった理不尽を追い続ける林さんの父親は、神社の神主であった。逃げてきた朝鮮人労働者をかくまった咎で憲兵隊に拷問され、やがて亡くなっている。この無念さを原動力のひとつとする林さんは、自らを「国賊・非国民の子」だと称する。これが想像力の源泉となっていることが、如何に残酷なことか。大学のときに荒畑寒村『谷中村滅亡記』に影響された林さんは、北九州市に勤めながら公害の実相を撮影し、37歳にして記録作家に転身する。否定しようもなく見出した構図は、「国家は企業のためなら国民を犠牲にしてもよいと考える」というものだった。このことが現在と地続きであることが林さんの原動力であり続けるのだとすれば、悲しく怒るべきことである。
林さんはいま、自己の集大成として、特攻隊の記録をまとめている。大刀洗町は大陸侵略の拠点たる飛行場が建設されたところであり、そこには、機密の特攻機・さくら弾機があった。それは3トン弾を搭載し、もはや操縦などできない片道切符の棺桶だった。しかし、出撃直前の1945年5月に、さくら弾機はおそらく放火されてしまう。憲兵隊は、証拠を集めることなく、朝鮮人であった「山本伍長」を犯人だと決めつけ、拷問によって自白させ、敗戦直前に銃殺刑に処した。仲間たちが「かれではない、なぜ自分に訊かなかったのか」と口を揃えるほどの冤罪であった。植民地主義が生んだ差別構造のひとつの結末である。
麻生吉隈炭鉱の跡には現在公園があり、大きな桜の樹があり、その下には500体もの遺体が眠っているという。主に身寄りも引き取り手もない朝鮮人労働者である。林さんはかれらの想いを想像し、「こんな無念なことはないですよ。悔しいですよ」と語った。
◆
上映後、監督の西嶋真治さんと、もとTBSの金平茂紀さんとのトークがあった。
金平さんは言った。
本来はこのようなテーマこそマスメディアが扱わなければならないのだが、いまでは一番扱わないテーマとなってしまった。九州は日本の近代化のための植民地であったが、そのような地域に足をおろした記録作家には凄みがあった(石牟礼道子、渡辺京二、松下竜一、森崎和江)。東京にも迫力のある人がいた(竹中労、平岡正明、高杉晋吾)。ところが現在では、そのような個人よりも資金力も人員もあるはずのメディアが、ベッキーや清原を追っかけている有様。
オバマ大統領が広島に来たことは画期的なことではあるが、単なる歓迎に終わらせることは、声を上げることなく死んでいった人たちへの冒涜である。いま広島に生きる者たちが声を上げる権利をさえ、予め抑えようとするとはどういうことなのか。歴史への想像力が、もの凄い勢いで無くなっているのではないか。そして自由にものが言えない、他と違うことを言うと滅多打ちにされてしまう社会になっている―――と。
ここに登場する林さんの個としての姿は、決して突出した個なのではなく(結果的にそのようになっているが)、このみっともない社会において各々が取り戻すべき姿であるだろう。
●参照
奈賀悟『閉山 三井三池炭坑1889-1997』
熊谷博子『むかし原発いま炭鉱』
熊谷博子『三池 終わらない炭鉱の物語』
上野英信『追われゆく坑夫たち』
山本作兵衛の映像 工藤敏樹『ある人生/ぼた山よ・・・』、『新日曜美術館/よみがえる地底の記憶』
本橋成一『炭鉱』
勅使河原宏『おとし穴』(北九州の炭鉱)
友田義行『戦後前衛映画と文学 安部公房×勅使河原宏』
本多猪四郎『空の大怪獣ラドン』(九州の仮想的な炭鉱)
佐藤仁『「持たざる国」の資源論』
石井寛治『日本の産業革命』