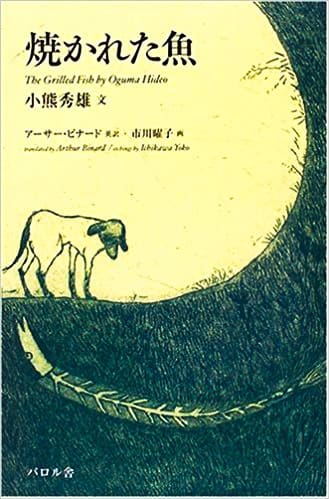ブルーノート東京でセシル・マクロリン・サルヴァントを観る(2018/3/25、1st)。

Cécile McLorin Salvant (vo)
Aaron Diehl (p)
Paul Sikivie (b)
Kyle Poole (ds)
最初に「I Didn't Know What Time It Was」、次に「I've Got Just About Everything」。言葉の発音がとてもクリアなことにあらためて驚く。続く「What's The Matter Now」はベッシー・スミスも歌った曲だそうであり、セシルの歌声にも少なからずベッシーの透明で高い声が重なるように聴こえる。「All Or Nothing At All」では「at all」の歌唱に圧倒されてしまう。
「My Man's Gone Now」はアーロン・ディールの弾くイントロから可憐に歌い始め、彼女にスポットライトが当たる。もうやられっぱなし。「... together to the promised land」に至り大変な説得力をもって迫る。ちょっとアビー・リンカーンを思わせる瞬間もある。
「Lover, Come Back To Me」はポール・シキヴィーのウォーキングベースとのふくよかなデュオから入り、やがてピアノとドラムスとが介入する。最初からずっと、ディールのピアノがカラフルで工夫を凝らしていることが印象的だったのだが、ここで、セシルはピアニストに対し、あなたほど歌うようなピアニストは知らない、なんて呟きながら、「I Hate A Man Like You」でピアノとのデュオ、にくい。
客席に向かって、ビートルズは知ってる?と呼びかけ、「And I Love Her」。最後の曲だと言いながら、『West Side Story』から「Something's Coming」。ピアノトリオがリズムを頻繁に変え、セシルはロングトーンで執拗に歌う。裏声も使い、「Maybe tonight!」と言うありさまには狂気も漂っていた。アンコールは、ジュディ・ガーランドが歌った「The Trolley Song」で、アップテンポでがんがん攻め、最後は両手を開いて「... to the end of the line」と絶唱した。
わたしはエラもサラも観たことがないが、歌唱力も迫力も説得力もレジェンドに匹敵するものではないかと思えるほどだった。ときにこちらに視線が来ると、雷に打たれたように、蛇に丸呑みされたようになってしまった。もう完璧。新譜も聴こう。
そういえばカイル・プールって、NYのSmallsで深夜セッションをよくやっている人ではなかったか。