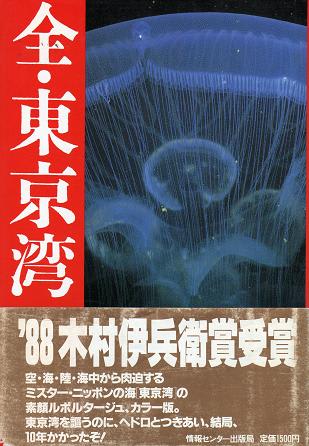この著者が鯨についての記述に本の半分を割いているのには理由がある。小松氏は水産庁で捕鯨を担当し、国際捕鯨委員会(IWC)で日本代表も務めた人物であり、捕鯨推進に向けた著書が多い。そのため、書きっぷりとしても、鯨の食文化が豊かであること(外房・内房で最近でも続いている、ビーフジャーキーのような「タレ」など)、ヒゲや脂や骨を含めあらゆる部位を利用できることなど、江戸時代以降の日本文化としての紹介となっている。
私は、一般的に食べる魚のようにはすぐ旨く食べられないからといって、乱暴に「食べなくてもよいもの」と決め付けてよいとは思わない。そんな個人的な理由だけで何百年もの文化を軽んじる人は、他の大事なものにも思いをはせることなく捨て去ってしまえる人であろう。ましてや非捕鯨国との国際折衝で決められるような捕鯨制限など論外だと思っている。
しかし、この本で挙げられている、「鯨を保護しすぎたせいで近海の魚が激減した」という説明はちょっと中立的でない。グラフでは、主要魚種を積み上げて、1988年あたりの750万トン程度をピークとして、確かに2001年には200万トン程度にまで漁獲量が減少しており、一方ミンククジラ・ニタリクジラ・イワシクジラの数は着実に増えていることが示されているので、両者の関係はありそうに見える。しかし、よく見ると、漁獲量が減っているのはマイワシであり、他のサンマやカタクチイワシなどはそんなに減っていないか、増えてさえいる。
この関係は、今週の『週刊朝日』(2007/6/22号)でも紹介している。やはり情報の出所は水産庁と(財)日本鯨類研究所だ。調べてみると、マイワシの激減には、乱獲や、よくある長期的・地球規模の変動も理由として挙げられているようだ(例えば、東大海洋研究所『激減したマイワシ資源』参照)。
ちょっとこのあたりは、強引に過ぎるのではないか。鯨の食文化を守ろうとする意義はよくわかるだけに残念に思える。
小松氏は、東京湾の魚介類は食べても問題ないことを示そうとして、グラムあたりのダイオキシン類の等量を、東京湾の魚介類と地中海のクロマグロとを比較している。それによると、東京湾の魚貝は概ね1~2 pgTEQ/g未満、脂肪の多いアナゴ(ダイオキシンは脂肪に蓄積しやすい)で3.5 pgTEQ/g程度。それに対して地中海のクロマグロは10 pgTEQ/gを超えている。
ただ、これもちょっと調べればわかることだが、実際の測定値は東京湾の魚介類でも10 pgTEQ/gを超えていることはあるし、マグロでも10 pgTEQ/g未満の場合もある。つまり、概ねの傾向としては間違っていないが、示し方と示すデータが明らかに恣意的なのである。
おそらく東京湾の底泥に蓄積されたダイオキシン類は無視し得えず、また、日本の他の地域に比べれば概ね数値的には高いのだろう。しかし、この物質は長期的に人間に影響を与えるものであり、その許容量を元に魚介類に含まれても問題が小さいダイオキシン量が定められている。つまり、毎日江戸前のアナゴを食べ続けたり、毎日マグロの刺身を食べ続けたりすると、ひょっとすると閾値を超えて発癌などのリスクが無視できない程度になってくるかもしれない。そもそも、食事はバランスよく食べないと、ダイオキシン云々ではなくおかしなことになるのだ。
私も、近くで獲れたものを食べるということには賛成であり、現在の水準であれば問題ないと考えている。それどころか豊かな自然が、実はそこにある。それだけに、無理に説得力を持たせようとした図表の示し方が、ここでも残念に感じられる。
折角、羽田沖の埋め立てなどが底泥を巻き上げ、そこに蓄積されていたダイオキシンが新たな汚染源となる可能性についても指摘されているのに・・・。
問題点を挙げたが、この本で紹介されている「東京湾の豊かさ」は、本当にわくわくするようなものが多い。実はおすすめの本である(笑)。
現在東京湾で養殖されている海苔はスサビノリ(海の条件変動に強く、パリッとしてコンビニのおにぎりなどに向く)だが、昔ながらのアサクサノリを再生しようとする取り組みがあることを知った。私も早速問い合わせてみたが、なかなか売るというところは難しく、できるとしても来年のお楽しみのようだ。三番瀬の海苔の天日干しも、本格的にやっておられた船橋の方(中村征夫『全・東京湾』でも紹介している)が引退された今、本当の稀少品となっている。ああ、手に入れて炙って食べてみたい。
うちの近く、浦安の当代島稲荷神社には、江戸時代に、東京湾に迷い込んできた鯨を捕えてあぶく銭を得た漁師が、最後に寄進したのを記念した碑もあるそうだ。今度散歩のついでに見つけてみよう。











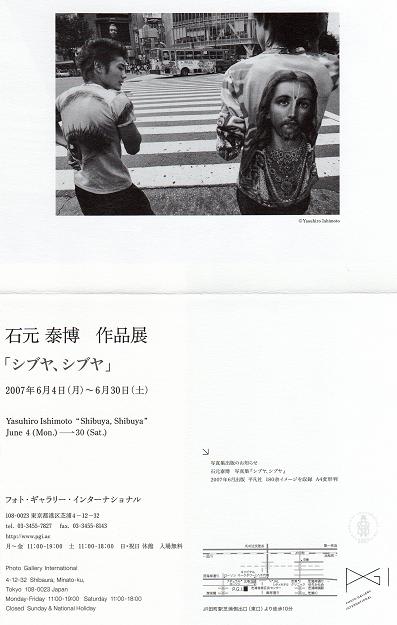




 =====
=====