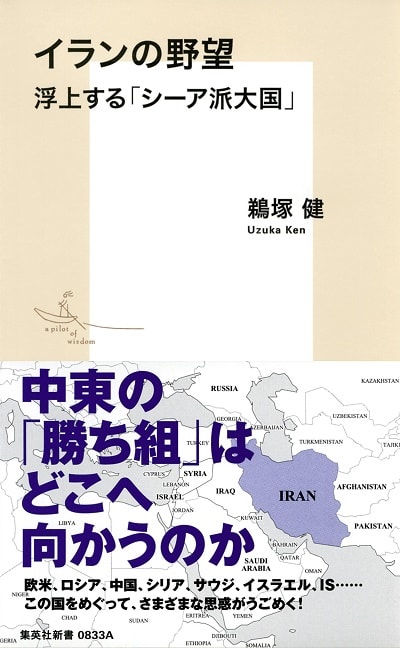何気なく「上野経済新聞」を読んでいたら、日暮里に「あさと」という沖縄料理店があるとの記事(>> リンク)。さっそく沖縄オルタナティブメディアのNさんと行くことにした。
ここは、谷中銀座から階段「夕焼けだんだん」を昇って、ちょっと右側に入った横丁「初音小路」にある。わたしも割と近くに4年以上住んでいたことがあるのに、横丁の存在にまったく気がつかなかった。何でも、かつては谷中銀座が栄えたためにマーケットとなっていた場所のようで、まさにそのような作り。裏寂れた感じなのだろうという予断は裏切られ、「あさと」のような古い料理屋も、新しいバーもあって、かなりの活気があった。


「あさと」は開店24年だということで、毎日人が座っていた場所ならではの居心地のよさがある。角煮(東京の沖縄料理なので敢えて「ラフテー」などとは呼ばないのだ)は泡盛と黒砂糖をきかせてあってとても旨い。もずくと玉ねぎが入ったひらやーちーも、生姜が効いた豚の中身汁も旨い。
石垣島出身の店主の安里さんによれば、ちょっと外れてはいてもやはり「谷根千」、ガイドブックを持ったヨーロッパの観光客がしばしば来るそうだ。この日は、三線を習っていてもうすぐ「度胸試し」で沖縄の大会に出るのだという人が、店の三線を借りて、「安波節」や「安里屋ユンタ」を歌った。

Nさんは、ジェームス・ブラウンのドキュメンタリー映画『ミスター・ダイナマイト』のお面をかぶって、JBがいかに画期的であったかという話。映画もずいぶん面白そうなので(てっきり劇映画だと思い込んでいた)、わたしも早く行くことにする。話は津島佑子、カーソン・マッカラーズ、ウィリアム・サローヤン、『白鯨』、ポール・オースター、コリン・ウィルソン、マーク・トウェインなどの小説から、豊里友行、石川真生、石川竜一と沖縄写真の方へ。
とくに、石川真生『大琉球写真絵巻』である。この、コスプレによって沖縄の抑圧された歴史を語りなおす作品の「ためにする」側面をどう視るか。多くの者がまおさんの写真にあってほしいと思うに違いない姿は、米兵や労働者を撮ったリアリズム写真家としてのそれである。しかしそれはそれとして、大傑作『日の丸を視る目』も、かつて沖縄芝居の仲田幸子を撮った作品群も、コスプレであり、歴史の語り直しではなかったのか。それ以上に、まおさんは、観る者が引いてしまうような表現を続けてきた写真家ではなかったのか。そして「ためにする」写真という側面で、豊里友行さんの写真をどう視るか。そんな話。
ところで、夕焼けだんだんの上には、パクチー山盛りの「深圳」の斜向かいに角打ちの「大島酒店」があって、窓には、紀藤ヒロシという歌手の歌う「夕焼けだんだん」のポスターが貼られている。どんな歌なのか興味津々。

誰かに死ぬまでだましてほしい
iphone 6s
●参照
たくさんのミントとたくさんのパクチー
飽きもせずに蒲田の東屋慶名
「東京の沖縄料理店」と蒲田の「和鉄」
『けーし風』読者の集い(26) 辺野古クロニクル/沖縄の労働問題(秋葉原の「今帰仁」)
坂手洋二『8分間』@座・高円寺(高円寺の「抱瓶」)
灰谷健次郎と浦山桐郎の『太陽の子』(神戸の沖縄料理店)
須田一政『凪の片』、『写真のエステ』、牛腸茂雄『こども』、『SAVE THE FILM』(新宿の「海森」)
山之口貘のドキュメンタリー(池袋の「おもろ」)