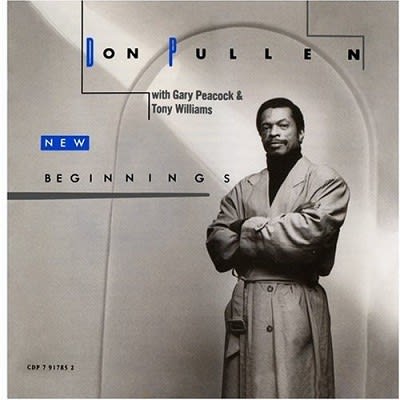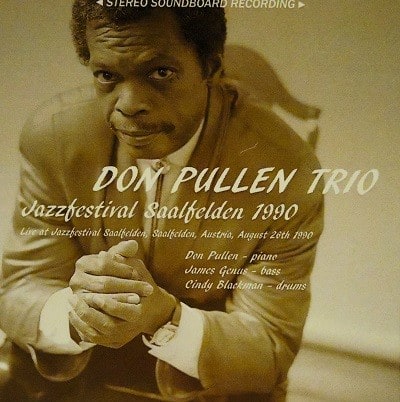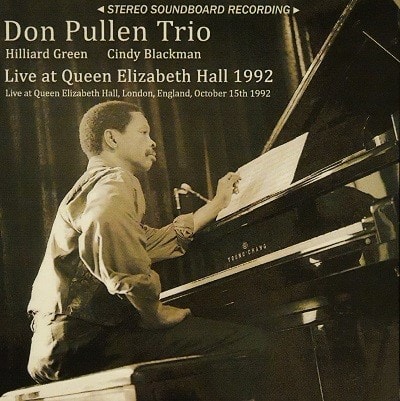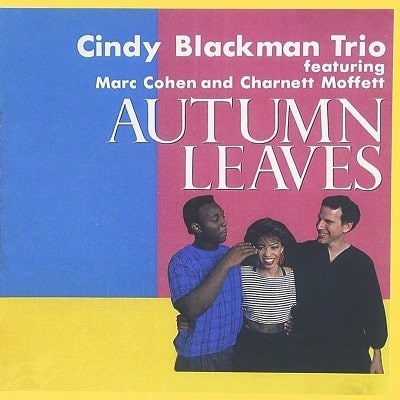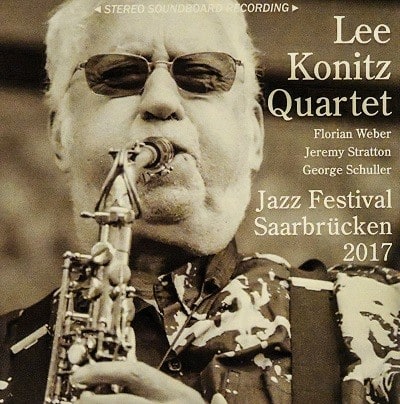時間が取れず国会前に行けなかった日。帰宅して、A-Musik『e ku iroju』(Zeitgenössische Musik Disk、1983年)のLPを聴く。

1. 不屈の民
竹田賢一(大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵(ds)、時岡秀雄(as)、工藤冬里(p)
2a. 前進
竹田賢一(fl)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、篠田昌已(as)、高橋鮎生(vo)
2b. 統一戦線の歌
竹田賢一(fl)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、篠田昌已、時岡秀雄、オニオン釜ケ崎(as, ts)
2c. プリパ
竹田賢一(大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、千野秀一(Moog liberation syn)、篠田昌已、時岡秀雄、オニオン釜ケ崎(as, ts)
3. 自殺について
竹田賢一(大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(ds)、久下恵生(ds)、時岡秀雄(as)、工藤冬里(p, syn)、高橋文子(vo)
4. There Will Never Be Another You
竹田賢一(fl)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、時岡秀雄(as)、工藤冬里(p, syn)、三浦燎子(vo)
5. I Dance
竹田賢一(大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、時岡秀雄(as)、工藤冬里(org)、坂本龍一(p)
6. 反日ラップ
竹田賢一(vo)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、千野秀一(Moog liberation syn)、篠田昌已、時岡秀雄、オニオン釜ケ崎(as, ts)、河野優彦(tb)、Rorie、勝田由美、大熊亘、中村峰子、田正彦(back-up voices)
7. El Vito
竹田賢一(大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、工藤冬里(p)、時岡秀雄(as)、Rorie(vo)
8. ぬかるみの兵士たち
竹田賢一(vo, 大正琴)、小山哲人(b)、石渡明廣(g)、久下恵生(ds)、工藤冬里(p, org)、John Duncan (whispering)
9. 二ルリリヤ
竹田賢一(harmonium)、篠田昌已(ss, ts)、佐藤春樹(tb)、山本譲(cello)、箕輪攻機(tabla)、カムラ(vo)
ライナーノートにおける竹田賢一さんの発言によれば、A-MusikのAは、ドイツのE-Musik(純音楽)でもU-Musik(大衆音楽)でもないものとして、インスピレーションで付けられたようなものだった。アナーキーのA、アンチのA、アーティフィシャルのA、間のA。
グループでは曲を演奏する。チリのビクトル・ハラ、ジャズスタンダード、韓国の民謡、スペインの民謡など幅広いが、Aの色であるとともに、普遍的な色も持っているように聴こえる。それはチャーリー・ヘイデンのリベレ―ション・ミュージック・オーケストラと同じであって(「統一戦線の歌」は両方で演奏)、聴き込んでいくと、多様さと普遍さがあるために自分の音楽になる。
それにしてもこのメンバーの凄いことである。かれらがAを演奏し、それは、コンポステラやストラーダや中央線ジャズやソウル・フラワー・ユニオンだけでなくあちこちでの種となって有象無象となっているに違いない。
いちどはナマで観たいものだなあ。去年ラストワルツでのライヴに誘われたのだが、つい別のところに行ってしまって少し後悔した。