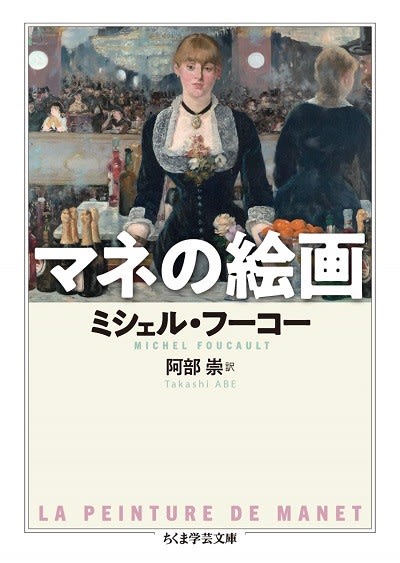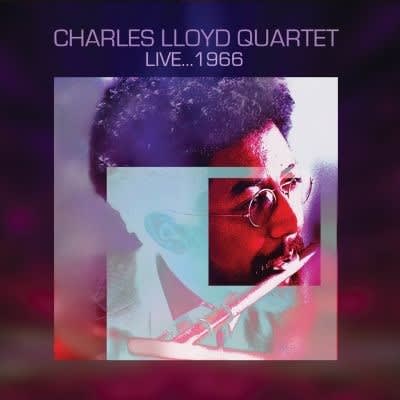ネナ・チェリーがザ・シングと共演した『The Cherry Thing』(Smalltown Supersound、-2012年)は名盤である。しかし、これを多くのミュージシャンがリミックスした『The Cherry Thing Remixes』(Smalltown Supersound、-2012年)なんて盤があることは最近まで知らなかった。

Neneh Cherry (vo)
Mats Gustafsson (ts, bs, live electronics, organ)
Ingebrigt Håker Flaten (ds, vibes, electronics)
Paal Nilssen-Love (ds, perc)
Christer Bothén (guimbri, donso n’goni)
Mats Äleklint (tb)
Per-Åke Holmlander (tuba, cimbasso)

1. What Reason Could I Give (Remix By Kim Hiorthøy)
2. Dream Baby Dream (Remix By Four Tet)
3. Accordion (Remix By Hortlax Cobra)
4. What Reason Could I Give (Remix By Carmen Villain)
5. Accordion (Remix By Jim O'Rourke)
6. Cashback (Remix By Lindstrøm & Prins Thomas)
7. Sudden Moment (Remix By Merzbow)
8. Golden Heart (Remix By Nymph)
9. Dirt (Remix By Christof Kurzmann)
10. Golden Heart (Poole Blount Legacy Dub) (Remix By Lasse Marhaug)
オリジナルアルバムの1曲を除きすべてカバーされており、オーネット・コールマンの「What Reason Could I Give」のみ2ヴァージョン。その片方はカルメン・ヴィランによるミックス。スマートで人工的でも自然でもある芳香の風が吹き抜けるようで悪くない。またカルメンさんを観たい。
メルツバウはさほど暴れず静かな狂気。ジム・オルークはもうちょっと野性的なグルーヴを付加している。あとはよく知らない面々だが楽しめる。こんなイヴェントやればいいのに、あるいはリリース時になにかあったのかな。
とは言え、やはり、オリジナルのぐわっと迫りくる野蛮さこそが好きである。「What Reason Could I Give」でのインゲブリグト・ホーケル・フラーテンのベースはかれらしく異常に強く粘るし、マッツ・グスタフソンやポール・ニルセン・ラヴの音は、ずっと棍棒を振り回すがごとき危険さである。もちろんネナ・チェリーのハスキーで通る声、ちょっとエフェクトがかけてあったりして痺れる。
●マッツ・グスタフソン
大友良英+マッツ・グスタフソン@GOK Sound(2018年)
マッツ・グスタフソン+クレイグ・テイボーン『Ljubljana』(2016年)
ザ・シング@稲毛Candy(2013年)
マッツ・グスタフソン+サーストン・ムーア『Vi Är Alla Guds Slavar』(2013年)
ピーター・エヴァンス+アグスティ・フェルナンデス+マッツ・グスタフソン『A Quietness of Water』(2012年)
ペーター・ブロッツマンの映像『Concert for Fukushima / Wels 2011』(2011年)
ペーター・ブロッツマンの映像『Soldier of the Road』(2011年)
大友良英+尾関幹人+マッツ・グスタフソン 『ENSEMBLES 09 休符だらけの音楽装置展 「with records」』(2009年)
マッツ・グスタフソンのエリントン集(2008年)
●インゲブリグト・ホーケル・フラーテン
デイヴィッド・マレイ+ポール・ニルセン・ラヴ+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン@オーステンデKAAP(2019年)
ロッテ・アンカー+パット・トーマス+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン+ストーレ・リアヴィーク・ソルベルグ『His Flight's at Ten』(2016年)
ジョー・マクフィー+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン『Bricktop』(2015年)
アイスピック『Amaranth』(2014年)
ザ・シング@稲毛Candy(2013年)
インゲブリグト・ホーケル・フラーテン『Birds』(2007-08年)
スティーヴン・ガウチ(Basso Continuo)『Nidihiyasana』(2007年)
スクール・デイズ『In Our Times』(2001年)
●ポール・ニルセン・ラヴ
フローデ・イェシュタ@渋谷公園通りクラシックス(2019年)
デイヴィッド・マレイ+ポール・ニルセン・ラヴ+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン@オーステンデKAAP(2019年)
Arashi@稲毛Candy(2019年)
ボーンシェイカー『Fake Music』(2017年)
ペーター・ブロッツマン+スティーヴ・スウェル+ポール・ニルセン・ラヴ『Live in Copenhagen』(2016年)
ザ・シング@稲毛Candy(2013年)
ジョー・マクフィー+ポール・ニルセン・ラヴ@稲毛Candy(2013年)
ポール・ニルセン・ラヴ+ケン・ヴァンダーマーク@新宿ピットイン(2011年)
ペーター・ブロッツマン@新宿ピットイン(2011年)
ペーター・ブロッツマンの映像『Concert for Fukushima / Wels 2011』(2011年)
ジョー・マクフィーとポール・ニルセン-ラヴとのデュオ、『明日が今日来た』(2008年)
4 Corners『Alive in Lisbon』(2007年)
ピーター・ヤンソン+ヨナス・カルハマー+ポール・ニルセン・ラヴ『Live at Glenn Miller Cafe vol.1』(2001年)
スクール・デイズ『In Our Times』(2001年)
●カルメン・ヴィラン
メルツバウ、テンテンコ、カルメン・ヴィラン@小岩bushbash(2017年)
●メルツバウ
メルツバウ、テンテンコ、カルメン・ヴィラン@小岩bushbash(2017年)
●ジム・オルーク
ペーター・ブロッツマン@新宿ピットイン(2011年)
森山大道展 レトロスペクティヴ1965-2005、ハワイ(2008年)
デレク・ベイリーvs.サンプリング音源(1996、98年)