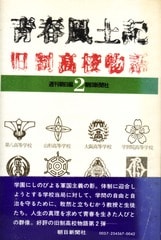敗戦直後の食料難について様々な人から話を聞いたことがある。中でも犬の肉を食べたという回想が一番印象に残っている。大正の初めに生まれた男性(故人)は「赤犬の肉は美味かったのぅ。腹が空いとったんを差し引いても兎よりははるかに上等じゃった。子どもに言うても分からんじゃろーが(笑)」と言った。
現代の感覚で犬の肉を口にする行為を悪食と決め付けるのは愚かだと思う。少なくとも江戸時代までは武士が精をつけるために犬肉を食べていた。我が国の犬食文化が衰退した理由としては犬公方の登場が大きいと思われる。綱吉は犬食を止めさせるためにあの悪法を出したという説もある。文明開化で日本人は徐々に牛肉などに慣れていくが、まさか再び犬肉を食べることになろうとは思いもしなかったろう。
「青春風土記 旧制高校物語2(週間朝日編 朝日新聞社 一九七八年)」に興味深い記述があるので引用しておこう。
そのうち戦争が終わり、食う物がいよいよ少なくなった。四高生を行列の先へいれようとすれば、自分が食いはぐれるかも知れない。四高生のほうでも、町の人の温情をあまりあてにできなくなった。
そのころ、水泳塾の学生は赤犬をたべるという風評が立った。それを聞いた山岳塾の学生たちが、ある日、赤犬を一匹つれて来た。この犬は、英語の神保教授の飼い犬なのだが、山岳塾の学生によく馴れて、ちょいちょい遊びに来ていたものである。
水泳塾の学生が手際よく処分し、ちょうど来合わせた金沢医大の先輩に解剖してもらって、すき焼きにして食った。部長の牧野信之助教授まで招待するという師弟の情誼の深さであった。
なんにも知らない神保教授は、愛犬がいつまでも帰って来ないので、北国新聞に尋ね犬の広告を出した。それを見て、水泳塾の連中は首をすくめた。
犬は一匹だけではなかった。水泳塾の周辺で、四、五匹の犬が姿を消しているはずである。
塾のおばさんも、犬すきのお相伴にあずかった一人である。しかし彼女はいかにも金沢人らしく、信心深い人だったので、仏壇に犬の絵をさげて、朝夕念仏をとなえていた。
極度の飢えは人間の眠っていた本性を呼び覚ました。食欲が理性を抑える特殊な事例を私は笑うことができないのである。