材木商を営んでいた田中七左衛門本陣の立派な庭に建つ明治天皇草津行在所(あんざいしょ)碑。本陣が高貴な身分の人の宿泊所として利用された証である。
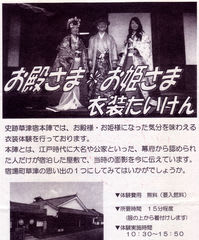
時代は変わり入館料を払えば私のような者でも立ち入ることができる。更に本陣内で武家の衣装をまとい殿様、姫様気分を味わうこともできるようだ。
展示の中で最も印象に残ったのが上段雪隠(じょうだんせっちん)である。畳敷きの部屋に大と小が備え付けられているのだが、放出物は木箱に取っていたという説明を読んで驚いた。私はてっきり下には甕(かめ)があるものとばかり思っていた。

さて現代の雪隠は非常にお洒落できれいに掃除されていた。本陣の見学を終えた頃には雨はほぼ上がっていた。最寄り駅はJR草津駅だが、偏屈な私はあえて楽なコースを選択するのを避けたのである。


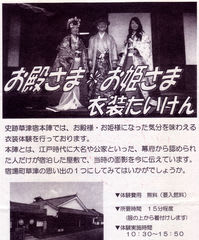
時代は変わり入館料を払えば私のような者でも立ち入ることができる。更に本陣内で武家の衣装をまとい殿様、姫様気分を味わうこともできるようだ。
展示の中で最も印象に残ったのが上段雪隠(じょうだんせっちん)である。畳敷きの部屋に大と小が備え付けられているのだが、放出物は木箱に取っていたという説明を読んで驚いた。私はてっきり下には甕(かめ)があるものとばかり思っていた。

さて現代の雪隠は非常にお洒落できれいに掃除されていた。本陣の見学を終えた頃には雨はほぼ上がっていた。最寄り駅はJR草津駅だが、偏屈な私はあえて楽なコースを選択するのを避けたのである。




















