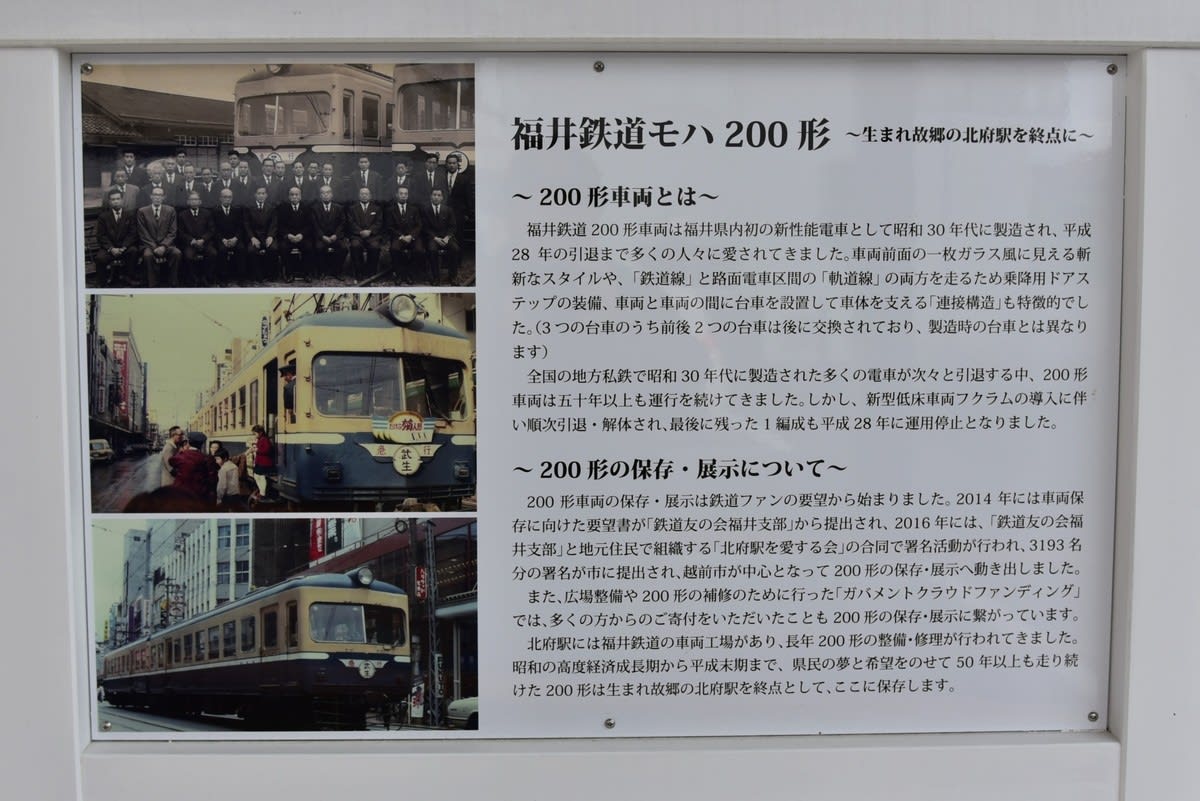(FUKURAMを超えろ、ジャパニーズトラム@福井駅前~福井城址大名町間)
福井城址大名町で青色のFUKURAMと交換するのは、「FUKURAM Liner」こと福鉄2000形。2023年2月に導入された、福井鉄道の最新型車両。2013年からFUKURAMこと福鉄F1000形を導入し、低床型新型トラム車両の導入に舵を切った福井鉄道。生え抜きの福鉄200形や、名古屋市交の改造車である600形などのステップ付きの経年の高床車を置き換え、「ああ、200形の引退は大変残念だけど、このまま福鉄はFUKURAMを軸にした車両の導入を続けて行くんだろうなあ」なんてぼんやり思っていたのですが、FUKURAMの導入は第4編成である1004Fまでで一旦お休みとなり、この「FUKURAM Liner」が1編成追加で投入されました。流線型のFUKURAMとは異なる非常にソリッドなデザインと、シャープに流れるサイドの福鉄カラーがカッコいいですよねえ。最近の鉄道車両、前面下部にラインを落とし込むようなデザイン(京成3100形とか)が非常に多いのですが、これもその「流行り」に乗ったものなんでしょうか。


ヒゲ線を通って恐竜のオブジェが待つ福井駅前へ。新しい街に新しいトラムが映える。先に導入された「FUKURAM」は、ボンバルディアトランスポーテーション(ドイツ)のライセンスを受けて日本の新潟トランシスが製造したブレーメン型と言われる超低床型トラムですが、この2000形「FUKURAM Liner」は、日本式超低床型トラム「リトルダンサー」シリーズのロングタイプ車両で、大阪のアルナ工機を中心とし、東芝や東洋電機製造ほか日本の交通機器産業に関わるオールジャパンの企業体の技術を結集して作られています。噂によると、FUKURAMの場合はいっぺん不具合が見つかると、重要部分がドイツのライセンス製品のために日本では調達が出来ず、故障や事故の際の保守管理に時間がかかるなどの問題点があるようです。よくイタリア車とかアメ車とか買っちゃうと、故障したときに部品が本国取り寄せになっちゃってカネも時間もかかるみたいな話を聞きますが、それの電車版みたいな感じ。では、日本はどうなのかというと、そこまでLRT車両の市場が大きくないので、保守や管理などのランニングの部分のサポートは見込めても、イニシャルの部分の量産性や納期の問題があるのだそうですが・・・(だから福井は当面の需要を満たす1編成だけの発注になったなんて話も)。宇都宮のLRTも、開業に備えて車両を用意するのに国内メーカーではその納期に間に合わせることがなかなか難しくて、結局新潟トランシス&ボンバルディア連合に発注したんだとか。鉄道産業における世界の産業構造の話になってしまったが、色々と勉強になることもあり。


ともあれFUKURAM Liner、見た目の意匠が目を引く存在で、道行く先でカメラを持っている同業者の姿が。観光客も連られてスマホのカメラでパチリ。ちなみに、私はこの車両を最初見た時にパッとひらめいたのが「OLFAカッター」ですね。あの、切れなくなると刃先をポキポキ折って新しい刃を出して使うやつ。これ、黄色く塗ったらまんまOLFAカッターやな、って。運転席のところからポキポキ折れそう。折れたらアカンやろけど(笑)。