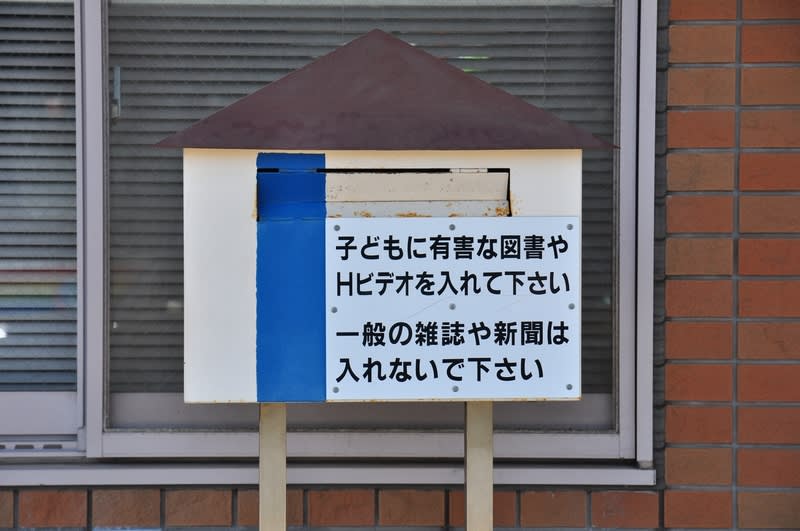(祇園神社の夏祭り@愛知郡愛荘町)
夕方になって、車内にめっきり増えて来た浴衣姿。その行き先はここ、愛荘町にある祇園神社。国道8号線、東海道新幹線、そして近江鉄道が渡る愛知川の鉄橋のたもとにあり、「橋神様」として日々の交通安全と橋の安全をお守りしている神様であります。今日は祇園神社の夏祭り、そして夏祭りに合わせて行われる愛知川の花火大会は今年で何と132回目!滋賀県最古の伝統の花火大会として、多くの観客を集める夏の名物イベントなんだそーな。
と言う事で、貴生川から乗って来た米原行きは、八日市からさらなる花火の観客を乗せて祇園神社の最寄り駅である五箇荘駅に到着。人込みに巻かれながらアタクシも降ります。花火大会だったのは知らなかったけど、元々降りる予定でしたからねえ。続々と降りて来る浴衣姿の花火客と近江ガチャコンの交換シーンは、夏のひとコマとしては実にいい感じ。そして夏のアイテムとして変な意味じゃなくて浴衣姿の娘さんってーのは凄く華やかでフォトジェニックなものだねえ。駅の掲示板には花火大会に合わせて臨電をブチ込む旨のお知らせがあり、これなら撮影回数も稼げそう。願ったりの展開です。
駅から花火客に混じって歩く事15分、愛知川の鉄橋にやって参りました。
元々ここに来ようと思ったのは、この近江鉄道の愛知川橋梁が国の有形文化財指定を受けている事によるものでして、1898年(明治31年)の架橋以来100年以上に亘って当時の姿をとどめたまま現存する貴重な土木構造物であるからなのです。橋長は239m、9連のプレートガーダーに彦根側の1スパンだけ単式のポニーワーレントラスが乗っかった構造で、トラス部分はイギリスのハンディサイド社と言う会社が作った舶来モノ。トラスを組む鉄骨の補助支持部分が横にウニっと曲がって出っ張っているのが特徴なんでしょうか…ちなみに「ポニー」とはトラス部分が小さく上部で通路を覆う横梁部分がないものを言い、「ワーレン」とは鋼材の組み方が△型になっているものを言い、「トラス」とは鋼材を三角形に組み上げる構造の事を言います。実生活では覚えててもしょうがない無駄知識を披露したところで、八日市の中線で昼寝していたパト電が夕方のパトロールにやって来ましたw
土手に並ぶ露店をバックに、八日市行きの単車222型が祭りの日の愛知川橋梁を渡る。ガーターを震わせるジョイント音と吊り掛け音のコラボレーション、車内は立ち客も目立って盛況の様子。しかしこの橋梁、普通は橋の真ん中とか水路上にトラスがあるものだと思うのだが、何の関係もない橋の末端部分だけトラス構造になっているのは何でなんだろうね。シロート目には、土手に近い場所にトラスを組んでもしょうがないと思うのだけど。
明治から続く花火大会と、明治から愛知川に架かる鉄橋。湖国の夏の夕晴れを、前パン振りかざして803編成が行く。並行する国道8号線の橋から撮影しているのだが、こうして構えている間にもアタクシの後ろをぞろぞろと花火客が祇園神社の会場に向かって歩いていくので、ちょっとお邪魔だったかしら。
花火大会の会場から離れ、五箇荘駅に戻って来ました。
なお駅からは続々と花火会場に向かう観客の波が続いていますが、少し趣向を変えて五箇荘駅の南側に広がる田園地帯でカメラを構えてみる事にします。南側に見える山は、太郎坊宮のある箕作山に繋がる八日市丘陵。この辺りで近江鉄道に並行する東海道新幹線が駅の南側で離れて行くので、同じ位置から近江鉄道も新幹線も見る事が出来ます。傾いた夕日に陰影を深める田園を手前に置いて、思わず新幹線を流し撮りw
田園地帯の農道の土手に座って電車を待っていると、花火大会臨電の高宮行キャラ電@809編成が夕日を浴びながらやって来た。八日市線の運用の後は本当ならお休みだったのだろうか、残業お疲れさんですなあ。夕方になって空気が澄んで来たようで、青空と夏の雲に表情があってなかなかいいコンディション。
暮れて行く夏の一日とフジテック編成。本来は夜からの運用になる新鋭900系も宵の口の臨電運用に参戦して花火客を会場に送り込みます。近江では新顔になる西武の新101系ですが、流山、秩父、伊豆箱根、上信、三岐、そして近江とこれで6社目の譲渡先。地方私鉄と言うと東急車の牙城のように思えますけど、何気に単一車種で6社もの会社にトレードされているクルマと言うのも珍しいのでは。
花火大会の開催を告げるバン、バンと言うかんしゃく玉の音と、本番を前に試し打ちされる花火がちらちらと見える五箇荘駅のホーム。花火大会は何時くらいに始まるのだろうか?出来れば、五箇荘の駅に停まる電車と花火を絡めて一枚撮ってみたいなあと。帰りの新幹線の時間とにらめっこしながら待っていると、再び折り返しのフジテック編成。宵闇に流れる花火客の姿、遠くから町長の挨拶なんかが聞こえて来て、もうすぐ始まりそうなんだけどな~。
五箇荘駅のタイムリミットは19時40分の上り電車。どうも始まりそうでいて始まらない花火大会、時間切れですかねえ。19時くらいから始まるのかと思ってたが、西の国は日没が遅いのをすっかり忘れていた。出来る事ならもうちょっと粘りたかったんだけど、フリーきっぷは土曜日限り。しゃあねえ、諦めます。
次回へ続く。