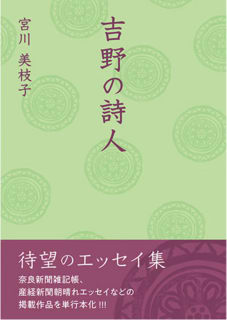奈良新聞「明風清音」欄に月1~2回、寄稿している。今月(2024.11.21)掲載されたのは〈吉野のエッセイスト〉だった。吉野町在住の宮川美枝子さんが、初のエッセイ集を刊行された。
私は「推薦のことば」のリクエストをいただいたので、ひとあし早く、ゲラ刷りを読ませていただいた(私の「推薦のことば」は末尾に記載)。初のエッセイ集というのに、その完成度の高さには目を見張った。では、記事全文を抜粋する。
吉野のエッセイスト
11月15日、吉野町にお住まいの宮川美枝子さん(77)が、初のエッセイ集を刊行された。それが『吉野の詩人』(京阪奈情報教育出版刊 税別1200円)である。珠玉の77編が収録されていて、ほとんどが本紙「雑記帳」欄に投稿されたものだ。
本書の表題である「吉野の詩人」とは、吉野町出身の故池田克己氏のことである。氏は詩人、編集者、写真家として活躍され「日本現代詩の先駆け」とも言われた人であるが、41歳で早世された。
宮川さんは学校(旧吉野工業学校、旧吉野工業高校)の先輩でもある池田氏に、私淑されていた。宮川さんは俳句も短歌も嗜(たしな)まれるし、評伝などノンフィクション作品も多いが、文学に興味を持たれたきっかけは、詩作だそうだ。私は本書推薦文のご依頼を受けたので「吉野の風土・風物が匂い立つ好エッセイ」のタイトルをつけた。
本書に登場する「吉野の風物」とは、背山から吹き下ろす山風、吉野川の川霧、吉野山の紅葉、阿太高原の梨、東吉野村の干し柿、こばし餅店のやき餅、吉野杉の印鑑ケース、文様割箸、吉野の金柑(きんかん)など。普段の吉野の暮らしの中から、自然と浮かび上がってくるものばかりだ。吉野には俳句や短歌の結社が多いが、このような恵まれた環境にお住まいなら自ずと詩心が湧き出てくるのかも知れない。
本書各章のタイトルは、吉野の四季、吉野人、食物語、60歳のラブレター 絆、出会い、家族、竹ざしと、吉野での心豊かな生活ぶりがうかがえる。吉野町に生まれ、吉野町にお住まいの宮川さんは、今までずっと吉野に住み続けていたわけではない。51年前に東京に嫁ぎ、定年退職された11年前、ご主人とともに吉野に戻って来られた。長年の東京生活があったからこそ、地元の良さを改めてかみしめておられるのだろう。
「宇宙の声」という一篇がある。〈秋の夜、草むらに生息する虫の声が融合して、軽快な音色を醸し出している。まるで宇宙が鳴らす鈴のよう。(中略)この地に住むようになって、この音色を聞くたびに、私はそう思う。宇宙に声があるとすれば、もしかしたらこのような響きかも知れないと〉(本紙「雑記帳」2018.11.14)。吉野の草むらの虫の声から、壮大な宇宙に思いを馳(は)せている。
「鉄橋のある町」には、〈夕日を浴びながら、近鉄吉野線二両電車は、大和上市駅から吉野神宮駅への鉄橋を渡っていた。吉野川を真ん中に雄大な風景に、息をのんだ。上市橋を自転車で走っていた私は、その神々しさに見とれた。(中略)山が聳(そび)え、川が流れ、鉄橋のある町。わが町は弥生式土器、縄文式土器が出土した、まほろばである〉(同24.3.11)。
「早春の川」には、〈真夏、大阪方面から来た都会の子らが、水遊びをして賑(にぎ)わっていた吉野川は、今、鴨(かも)が渡来し生息していた。夜行性の鴨たちは昼間、縦一列になって水の中に浮かんだり、時には小さな岩に上がり、群れでゆったりとした時間を過ごしていた。
(中略)水量のなみなみとした夏の吉野川を人間に与え、水の少ない冬は渡り鳥用にと、天は人間との共有を考え、粋なはからいをしていたのかも知れない〉(同23.3.29)。小動物に注ぐ目は、とてもやさしい。
「杉の香り」には、〈春、杉は轟音(ごうおん)のような勢いで水を吸い上げ、暑い夏を越し秋を迎え、やがて冬を。春に水を吸い上げすぎた杉は、冬には凍って自爆し、塔婆のような姿になってしまう。また雪が多い年は、その重みで木が折れてしまうこともある〉
(同17.10.11)。
吉野のエッセイストは、厳しい自然界の掟を書き留めることも、忘れないのだ。ぜひ、ご一読をお薦めしたい。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)
※本書に関するお問い合わせ先:京阪奈情報教育出版(0742・94・4567)
(ご参考)推薦のことば 吉野の風土・風物が匂い立つ好エッセイ
NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」専務理事 鉄田憲男
宮川美枝子さんとは、2022(令和4)年に刊行された俳人・故岩田まさこさんの俳句と生涯を紹介された『惜春の大地 中村汀女を師と仰いだ吉野人の軌跡』(京阪奈情報教育出版刊)を拝読して以来のお付き合いです。
その後も宮川さんは、奈良新聞「雑記帳」欄にエッセイの投稿をを続けられ、短歌もお始めになりました。私より6歳先輩の後期高齢者のはずなのに、「このパワーは、どこから生まれてくるのだろう」と不思議に思っていました。
その疑問は本書を読んで、氷解しました。きれいな空気、おいしい水、それらで育てられた地元のとれたて野菜や果物。心やすらぐ吉野の風景、優しいご家族ご親族やお友だち。このような環境にいらっしゃるから心が満たされ、また感受性が研ぎ澄まされ、良いエッセイが次々と生まれるのだな、と納得しました。
例を挙げますと、「蜩(ひぐらし)」(17ページ)の一篇。〈夏の夕暮れ一匹の蜩が歌い出すと、さらにもう一匹が。独唱が輪唱となり、何百匹もの蜩の合唱となっていく。夕方、こんもりとした背山(せやま)がその音色に染まった。
(中略) 蜩の合唱はやがて隣の山へと移行していく。何と壮大な光景だろう。その昔、この地は南北朝時代の舞台となったところ。何千、いや何万もの、数えきれない死者が大地に埋まったことだろう。クリスタルのような音律は、地中深く眠っていた古人の言霊(ことだま)が、蜩の化身となって歌っていたのではないだろうか〉。
「カナカナカナ」という蜩の合唱から、南朝の死者の霊に思いを致す。吉野の風土が生み出した名篇と言えるでしょう。
また「天日干し」(80ページ)。〈同級生が私の傍にきた。「近所から渋柿をいただいて、干し柿にしたの。酢の物に入れると美味しいよ」と、言う。半分を、私の土産に持たせてくれた。干し柿の横には、剥いた皮も乾かしてある。また薄く切って、柿チップも作っている。彼女は食べ物を無駄にしない昭和人。
(中略)その日の夕食後、私は干し柿をご馳走になった。素朴で飾らない彼女の人柄のような旨味(うまみ)が、口いっぱいに広がった〉。純朴なお友だちのお人柄と良いご関係が、伝わってきます。私も「柿の皮は乾かせばそのままポリポリと食べられるし、砂糖の代わりに煮物や漬物に入れてもいい」とは聞いていましたが、本当に皮まで干しておられたとは……。
他にも、虫の声に宇宙が鳴らす鈴の音を感じる「宇宙の声」(18ページ)、ザクロをもいで食べる10匹ほどの猿の集団を活写した「宴」(20ページ)、好きな女性ができてアトピーが治った元上司を描いた「恋のパンチ」(112ページ)など、ユーモアやウイットの利いた名篇の数々は、ぜひ急がず味わいながら、じっくりとお読みください。2024(令和6)年10月吉日

私は「推薦のことば」のリクエストをいただいたので、ひとあし早く、ゲラ刷りを読ませていただいた(私の「推薦のことば」は末尾に記載)。初のエッセイ集というのに、その完成度の高さには目を見張った。では、記事全文を抜粋する。
吉野のエッセイスト
11月15日、吉野町にお住まいの宮川美枝子さん(77)が、初のエッセイ集を刊行された。それが『吉野の詩人』(京阪奈情報教育出版刊 税別1200円)である。珠玉の77編が収録されていて、ほとんどが本紙「雑記帳」欄に投稿されたものだ。
本書の表題である「吉野の詩人」とは、吉野町出身の故池田克己氏のことである。氏は詩人、編集者、写真家として活躍され「日本現代詩の先駆け」とも言われた人であるが、41歳で早世された。
宮川さんは学校(旧吉野工業学校、旧吉野工業高校)の先輩でもある池田氏に、私淑されていた。宮川さんは俳句も短歌も嗜(たしな)まれるし、評伝などノンフィクション作品も多いが、文学に興味を持たれたきっかけは、詩作だそうだ。私は本書推薦文のご依頼を受けたので「吉野の風土・風物が匂い立つ好エッセイ」のタイトルをつけた。
本書に登場する「吉野の風物」とは、背山から吹き下ろす山風、吉野川の川霧、吉野山の紅葉、阿太高原の梨、東吉野村の干し柿、こばし餅店のやき餅、吉野杉の印鑑ケース、文様割箸、吉野の金柑(きんかん)など。普段の吉野の暮らしの中から、自然と浮かび上がってくるものばかりだ。吉野には俳句や短歌の結社が多いが、このような恵まれた環境にお住まいなら自ずと詩心が湧き出てくるのかも知れない。
本書各章のタイトルは、吉野の四季、吉野人、食物語、60歳のラブレター 絆、出会い、家族、竹ざしと、吉野での心豊かな生活ぶりがうかがえる。吉野町に生まれ、吉野町にお住まいの宮川さんは、今までずっと吉野に住み続けていたわけではない。51年前に東京に嫁ぎ、定年退職された11年前、ご主人とともに吉野に戻って来られた。長年の東京生活があったからこそ、地元の良さを改めてかみしめておられるのだろう。
「宇宙の声」という一篇がある。〈秋の夜、草むらに生息する虫の声が融合して、軽快な音色を醸し出している。まるで宇宙が鳴らす鈴のよう。(中略)この地に住むようになって、この音色を聞くたびに、私はそう思う。宇宙に声があるとすれば、もしかしたらこのような響きかも知れないと〉(本紙「雑記帳」2018.11.14)。吉野の草むらの虫の声から、壮大な宇宙に思いを馳(は)せている。
「鉄橋のある町」には、〈夕日を浴びながら、近鉄吉野線二両電車は、大和上市駅から吉野神宮駅への鉄橋を渡っていた。吉野川を真ん中に雄大な風景に、息をのんだ。上市橋を自転車で走っていた私は、その神々しさに見とれた。(中略)山が聳(そび)え、川が流れ、鉄橋のある町。わが町は弥生式土器、縄文式土器が出土した、まほろばである〉(同24.3.11)。
「早春の川」には、〈真夏、大阪方面から来た都会の子らが、水遊びをして賑(にぎ)わっていた吉野川は、今、鴨(かも)が渡来し生息していた。夜行性の鴨たちは昼間、縦一列になって水の中に浮かんだり、時には小さな岩に上がり、群れでゆったりとした時間を過ごしていた。
(中略)水量のなみなみとした夏の吉野川を人間に与え、水の少ない冬は渡り鳥用にと、天は人間との共有を考え、粋なはからいをしていたのかも知れない〉(同23.3.29)。小動物に注ぐ目は、とてもやさしい。
「杉の香り」には、〈春、杉は轟音(ごうおん)のような勢いで水を吸い上げ、暑い夏を越し秋を迎え、やがて冬を。春に水を吸い上げすぎた杉は、冬には凍って自爆し、塔婆のような姿になってしまう。また雪が多い年は、その重みで木が折れてしまうこともある〉
(同17.10.11)。
吉野のエッセイストは、厳しい自然界の掟を書き留めることも、忘れないのだ。ぜひ、ご一読をお薦めしたい。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)
※本書に関するお問い合わせ先:京阪奈情報教育出版(0742・94・4567)
(ご参考)推薦のことば 吉野の風土・風物が匂い立つ好エッセイ
NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」専務理事 鉄田憲男
宮川美枝子さんとは、2022(令和4)年に刊行された俳人・故岩田まさこさんの俳句と生涯を紹介された『惜春の大地 中村汀女を師と仰いだ吉野人の軌跡』(京阪奈情報教育出版刊)を拝読して以来のお付き合いです。
その後も宮川さんは、奈良新聞「雑記帳」欄にエッセイの投稿をを続けられ、短歌もお始めになりました。私より6歳先輩の後期高齢者のはずなのに、「このパワーは、どこから生まれてくるのだろう」と不思議に思っていました。
その疑問は本書を読んで、氷解しました。きれいな空気、おいしい水、それらで育てられた地元のとれたて野菜や果物。心やすらぐ吉野の風景、優しいご家族ご親族やお友だち。このような環境にいらっしゃるから心が満たされ、また感受性が研ぎ澄まされ、良いエッセイが次々と生まれるのだな、と納得しました。
例を挙げますと、「蜩(ひぐらし)」(17ページ)の一篇。〈夏の夕暮れ一匹の蜩が歌い出すと、さらにもう一匹が。独唱が輪唱となり、何百匹もの蜩の合唱となっていく。夕方、こんもりとした背山(せやま)がその音色に染まった。
(中略) 蜩の合唱はやがて隣の山へと移行していく。何と壮大な光景だろう。その昔、この地は南北朝時代の舞台となったところ。何千、いや何万もの、数えきれない死者が大地に埋まったことだろう。クリスタルのような音律は、地中深く眠っていた古人の言霊(ことだま)が、蜩の化身となって歌っていたのではないだろうか〉。
「カナカナカナ」という蜩の合唱から、南朝の死者の霊に思いを致す。吉野の風土が生み出した名篇と言えるでしょう。
また「天日干し」(80ページ)。〈同級生が私の傍にきた。「近所から渋柿をいただいて、干し柿にしたの。酢の物に入れると美味しいよ」と、言う。半分を、私の土産に持たせてくれた。干し柿の横には、剥いた皮も乾かしてある。また薄く切って、柿チップも作っている。彼女は食べ物を無駄にしない昭和人。
(中略)その日の夕食後、私は干し柿をご馳走になった。素朴で飾らない彼女の人柄のような旨味(うまみ)が、口いっぱいに広がった〉。純朴なお友だちのお人柄と良いご関係が、伝わってきます。私も「柿の皮は乾かせばそのままポリポリと食べられるし、砂糖の代わりに煮物や漬物に入れてもいい」とは聞いていましたが、本当に皮まで干しておられたとは……。
他にも、虫の声に宇宙が鳴らす鈴の音を感じる「宇宙の声」(18ページ)、ザクロをもいで食べる10匹ほどの猿の集団を活写した「宴」(20ページ)、好きな女性ができてアトピーが治った元上司を描いた「恋のパンチ」(112ページ)など、ユーモアやウイットの利いた名篇の数々は、ぜひ急がず味わいながら、じっくりとお読みください。2024(令和6)年10月吉日