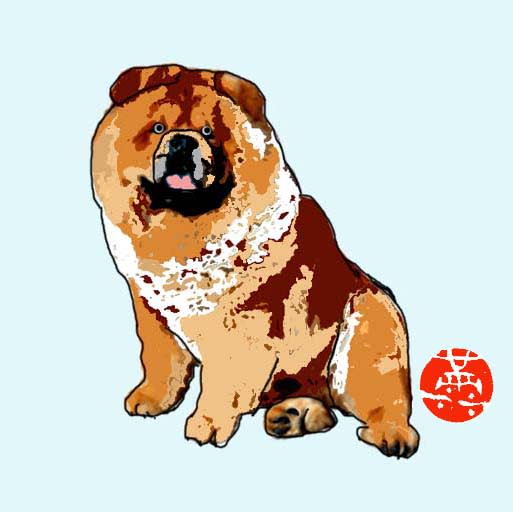都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
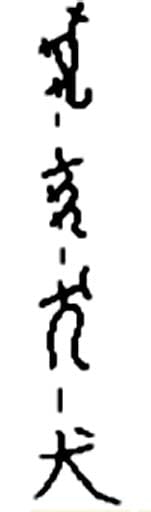 「イヌ」の語源は、人間にまとわりついてきて、「何処かへ行け!」の古語「往ね(イネ)」が訛ったものだと言われています。
「イヌ」の語源は、人間にまとわりついてきて、「何処かへ行け!」の古語「往ね(イネ)」が訛ったものだと言われています。
それではあまり可哀想ですよね。
そのほかには、いつも人間のそばに「居ぬる」から「イヌ」になったという説もあります。
イヌを犬(ケン)と称するのは、いうまでもなくそれがケンケン(k'uen)と鳴くからだそうです。犬(ケン)ということばは、いわゆる擬声語なのです。
余談ですが、「戻る」という字は「戸」に「大」と書きますが、本来は「戸」に「犬」と書き、「?」です。
字義には2説あります。
① 暴犬が戸内に閉じ込められ暴れるさまから、逆らう、もどる。
② 玄関の下に悪霊よけのために埋められた犬。
悪霊を追い返す->もどす。家の前に生贄の犬を埋めた形をあらわしたものです。
犬を埋めることで地中の悪霊をはらったそうです。
「戻」も「戸に犬」でないと意味をなさないのですが、「臭」「戻」「器」も、「大」という字が含まれていますが、元は「犬」であり、当用漢字(1946年)常用漢字(1981年)が定められた時に「大」になってしまったそうです。「嗅」は犬が残ったのに、臭は大になりました。こうして、漢字は意味のないものに鳴ってしまうのでしょうか。
もとと「犬」にある点は、犬の耳の意味で、この点をつけることで、「犬」と、人の正面形をあらわす「大」を区別したものです。「犬」から点を取ってしまい、犬も人も同じにしてしまったのが、戦後の漢字改革なのです。
「臭」:鼻を表す「自」と鼻が利く動物「犬」の組み合わせだったのに、自と大になり、何が何だかわからない字になってしまった。
「器」:器は、本来は口4つと犬の組み合わせで、生贄の犬を入れ、神様にささげお祓いをする字が、「器」との事。だから旧字は、点がある。
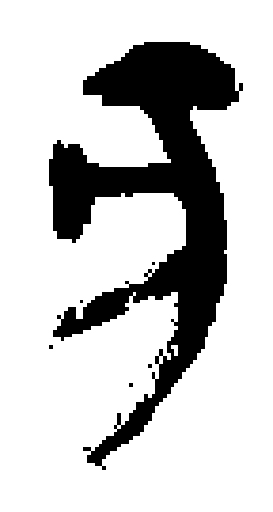 「然」の中には、犬がいるのです。というより犬がメイン。古代の中国では祈りや願いの犠牲として犬がささげられたので、犬を含む漢字は沢山あるのです。「然」は、犬、月(にくづきで肉を意味する)、火(下の点4つ)から出来ている。神様は犬を焼いた匂いが大好きなので、犬の肉を火で燃やして天上の神様にと届ける字が、「然」と言う字なのです。
「然」の中には、犬がいるのです。というより犬がメイン。古代の中国では祈りや願いの犠牲として犬がささげられたので、犬を含む漢字は沢山あるのです。「然」は、犬、月(にくづきで肉を意味する)、火(下の点4つ)から出来ている。神様は犬を焼いた匂いが大好きなので、犬の肉を火で燃やして天上の神様にと届ける字が、「然」と言う字なのです。
残酷な話ですが、中国で犬食の文化があったことは「羊頭狗肉」の言葉にも残っています。チャウチャウは食用犬として改良された犬なのです。
身近にいるがために人間の犠牲になってきた犬たちですが、今はペットとして人々に安らぎを与えています。
今は犬を家の中で飼う時代ですから、漢字も変わったと言うことでしょうか。
したっけ。