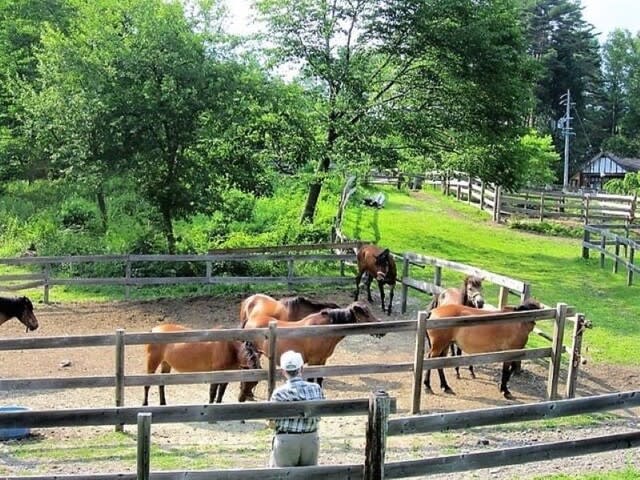以前に大型客船「ふじ丸」で熱海の沖にある離島の初島へ東京から行きました。
今日は初島へ航海の思い出をお送り致します。
客船が初島に到着しまた。ところが「ふじ丸」が大き過ぎて初島の小さな港へ入れません。いったいどのようにして初島観光をするのか不思議でした。
そうしたら客船に搭載して行った大きい救助艇を高い舷側から海へ降ろすのです。

1番目の写真は搭載して行った救助艇です。100人乗れるそうです。
右舷と左舷に積んで行った「さざなみ号」と「そよかぜ号」を海面に降ろしたら、どこからともなく大きな台船を引っ張った船がやって来ました。
その台船を大型客船の一階の出入り口の下に繋いで、その外側に救難艇を係留します。お客が救助艇に無事乗り移れれば、初島の港へ着けます。

2番目の写真は初島に着岸したところです。
お客が周囲4kmの島を散策します。4時間後にまた救難艇に乗って本船に帰ります。そして東京まで7時間の航海で帰って来ました。
下の写真は初島の東海岸から見た日本で初めて1989年に進水した豪華客船、「ふじ丸」の姿です。
これが最後のクルーズになります。古くなったので商船三井が就航を停止して、売り出している船です。
3番目の写真は初島の東海岸から見た豪華客船、「ふじ丸」の姿です。湖の船は日本で初めて1989年に進水した豪華客船です。
熱海の沖の離れ小島の初島には東明寺というお寺がぽつんと一軒だけあります。
境内に佇み、そして時々静かに歩きまわりながら撮った写真をお送りいたします。
お寺に入ると左手に同じような墓が一列に並んでいます。
4番目の写真はお寺に一列に並んで墓です。
みんな、みんな大東亜戦争で戦死した兵隊さんたちのお墓です。
この小島から歓呼の声に送られて出征し、二度と帰って来なかった島の若者たちの墓標です。私はひとうひとつ名前を読んでいきました。帝国陸軍一等兵、伍長、曹長、などなどです・・・・少尉や中尉の字はありません。
しばらくしてから、本堂の裏手に歩いていくとそこには下の写真のように昔の無縁仏の墓石がまとめてありました。
5番目の写真は昔の無縁仏の墓石です。
島には江戸時代から41軒の家しかありません。長い年月の間にどの墓が、どの家の先祖なのか分からなくなったのでしょう。あるいは江戸城の石垣の石を切り出しに来た人々のお墓かも知れません。
気がつくと兵隊さんたちの墓のすぐ後ろには洒落た木造の小学校・中学校の校舎が見えるのです。戦前はもっと粗末な校舎だったに違いありません。そこを卒業し、漁業や農業にいそしんでいた若者たちが戦争へ行ってしまったのです。
私は最後に本堂の前の香炉に線香をあげて帰って行きました。線香のかおりが静かにながれていました。
それはそれとして、
今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)