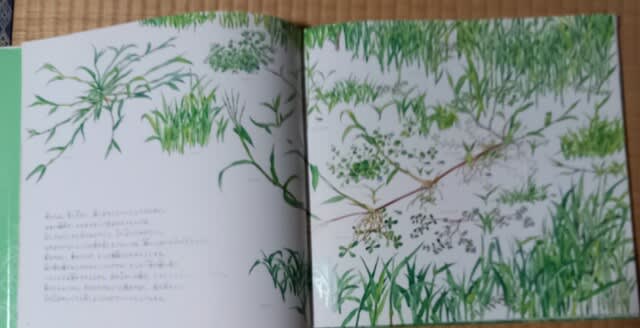WTT女子ファイナルズの卓球の試合が日本・名古屋で行われている。
世界ランク上位者16人でトーナメントを戦い、グランドチャンピオンを決める。
日本勢は、世界ランクから早田ひな、張本美和、伊藤美誠の3人が出場している。
早田と張本は、抽選運が悪い。
初戦で、世界ランク3位や1位の中国選手と当たってしまったのだ。
でも、下剋上を期待し、BSテレ東の中継を見た。
日本勢で最初に登場したのは、日本の№1、早田ひな選手だった。
世界5位だというのに、初戦の相手は世界3位で東京五輪金メダルの陳夢。
試合が始まると、さすが王者陳夢。
ボールが強く、コース取りも巧みだ。
早田は、粘ろうとしたものの、5-11で失った。
第2ゲームになると、接戦になった。
早田が陳夢のボールに慣れてきた、とでもいえばよいのだろうか。
9-7でリードしたが、そこは陳夢、強気で早田を攻め、逆転してゲームポイントを握った。
9-10と窮地に陥った早田だが、ネットインを利して攻め、ジュースに持ち込んだ。ここからの粘りがすばらしかった。
11―11で、早田がタイムアウト。
12-12から13-12となりゲームポイントを握るも、連取され、13-14。
しのぎながら14-15となったところで、陳夢がタイムアウト。
ところが次の1本を取って、15-15早田追いつく。
ここで3球目攻撃が決まり、16-15。
そして、ついに1本取って17-15。ゲームカウント1-1に追いついた。
次の第3ゲームは、6-6からレシーブでチキータ攻撃でリード。
ここから一気に攻めて11-7でこのゲームを奪った。。
だが、ここから陳夢が立て直す。
第4ゲームは、出足からリードし、1-3、2-4、3-6、4-8、5-9と差を広げていく。
早田も粘って、6-10からサーブで2本取り8-10とするも、8-11。
ゲームオールとなる。
第5ゲームも出だしから長いサーブで陳夢が2-0とリード。
早田もサーブを工夫し1-2。ラリーで攻めたが、1-3。
しのいで2-3から3-3。レシーブのコントロールがいい。
だが、ここから早田5失点。
3-8。しのいでエッジボールで6-8と追い上げながらも2本取られ、6-10。
1本取ったものの、7-11でゲームセット。
惜しかった。
だが、早田の対応力はすごいと思った。
第1ゲームを見ただけではかなわないと思ったのに、第2ゲームは粘ってジュースに持ち込み勝ち取った。
そして、先に2ゲームを取って勝利に近づいた。
勝利まであとひと息だったのだ。
これでいて、早田は今プレースタイルを改造中だという。
それが完成したら、もっと強くなるということだろう。
年々強くなる早田ひな。
来年の活躍が楽しみだ。
ともすれば、それよりも惜しかったと言えるのが、世界ランク1位孫穎莎と対戦した張本美和。
試合開始から、バックハンドで孫を振り回し、11-6で先取。
第2ゲームは、競りながら9-11で落とす。
第3ゲーム、6-1から8-4と大きくリードした。
ところが、ここで勝ちを意識したのか7本連取され、8-11で落としてしまった。
だが、第4ゲームは、その悔しさからか、6-1、7-3とリード。
途中から孫の攻めが雑になり、11-3で張本が奪い、ゲームオールに追いついた。
勝負の第5ゲーム。出足が勝負だ。
サーブを利して、2-0、強気の攻めで3-0となったところでタイムアウトをとる孫。
ここで流れが変わった。
4本連取し、孫が逆転。
4-4となるも、再び4本連取で4-8。
結局、6-11で撮られ、張本は敗れた。
第3ゲームの逆転負けが、返す返すも残念だ。
だが、まだ15歳。これだけどれだけ強くなるか、非常に楽しみだ。
早田も張本も、中国勢にフルゲームの熱戦を展開した。
あと一歩まで来ている。
そう感じる、日本卓球女子の力の向上を見た思いだった。
この大会、あとは勝ち残った伊藤美誠にぜひがんばってもらいたいものだ。