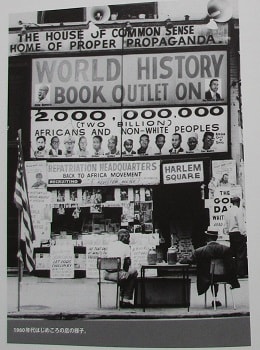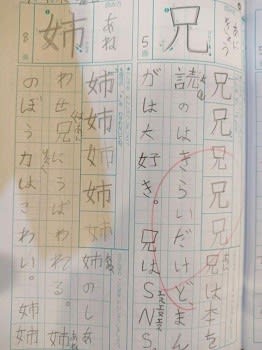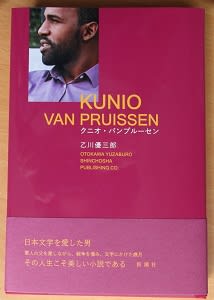昨年の大河ドラマは(ああ、ドラマだなあ)と思いつつ、途中パスする回もでてきたが、今年の「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 」は、はるかに興味を持って観ている。江戸の出版文化が作られていく過程が、蔦屋重三郎を通してどう描かれるかに関心がある。

山東京伝のもとに書塾を営む沢田東里が訪れ、越後の鈴木儀三治(俳号・牧之ぼくし)が書き集めた北國の奇談の草稿に目を通してもらえないかと相談をもちかけた。
その絵の巧みさに目を奪われた京伝。
聞けば儀三治は19歳のとき行商で江戸に出た折、沢田東里の父のもとで書の手ほどきを受け、越後にあっては狩野派の門人に絵を学び、俳諧も村人たちと楽しむ男だった。
耕書堂を営む蔦屋重三郎と京伝とは17年にも及ぶ付き合いがあったが、この5月に死んでしまった。どの板元に…。
「承知の助だ。まずは預かってみる」と京伝だったが、さてここからが長い。
京伝、馬琴、玉山、芙蓉、様々な戯作者の手に渡りながらも頓挫が続く。『北越雪譜』刊行まで40年のときを要した。
実に多くの板元や戯作者(その作品名もだが)が登場し、交錯する人間関係、思惑が展開するが、何を機に、どうあって実を結ぶに至るのかと興味を引っぱられる形で読み終えた。
松岡正剛氏によると、鈴木牧之が交流した人士は、交わした往復書簡を貼りつけて綴じた『筆かがみ』というものに丁寧に残しているため、大体がわかるのだという。
また氏は「原画は牧之が描いたが、仕上げは京伝の息子の京山の手が入った」と書いているが、作品中では京山は弟であった。京伝に実子はいなかった。史実の脚色はさほど簡単ではないというが、どうなのだろうか。
それにしても越後と江戸の遠さよ。
夫・吉村昭の死から3年あまり
〈生き残った者のかなしみを描く小説集〉、5作が収められた『遍路みち』(津村節子)。
「私の身辺のことを綴ったものばかりを選び、ほとんど事実に近い」とあとがきにあった。

「楽しいことも 嬉しいことも あったはずなのに…、
悔いのみ抱いて 生きてゆく遍路みち」
夫の死にまつわる騒動のいきさつなど語られ、自らの軽率を省みている。
十分な介護ができなかった悔い。
作家夫婦の暮らしぶりも垣間見え、情愛など染み入るが、どうあっても苦はなくならないという生きることの事実を深く強く思い知らされ、胸を突いてくる作品だった。一気に読んだ。

山東京伝のもとに書塾を営む沢田東里が訪れ、越後の鈴木儀三治(俳号・牧之ぼくし)が書き集めた北國の奇談の草稿に目を通してもらえないかと相談をもちかけた。
その絵の巧みさに目を奪われた京伝。
聞けば儀三治は19歳のとき行商で江戸に出た折、沢田東里の父のもとで書の手ほどきを受け、越後にあっては狩野派の門人に絵を学び、俳諧も村人たちと楽しむ男だった。
耕書堂を営む蔦屋重三郎と京伝とは17年にも及ぶ付き合いがあったが、この5月に死んでしまった。どの板元に…。
「承知の助だ。まずは預かってみる」と京伝だったが、さてここからが長い。
京伝、馬琴、玉山、芙蓉、様々な戯作者の手に渡りながらも頓挫が続く。『北越雪譜』刊行まで40年のときを要した。
実に多くの板元や戯作者(その作品名もだが)が登場し、交錯する人間関係、思惑が展開するが、何を機に、どうあって実を結ぶに至るのかと興味を引っぱられる形で読み終えた。
松岡正剛氏によると、鈴木牧之が交流した人士は、交わした往復書簡を貼りつけて綴じた『筆かがみ』というものに丁寧に残しているため、大体がわかるのだという。
また氏は「原画は牧之が描いたが、仕上げは京伝の息子の京山の手が入った」と書いているが、作品中では京山は弟であった。京伝に実子はいなかった。史実の脚色はさほど簡単ではないというが、どうなのだろうか。
それにしても越後と江戸の遠さよ。
夫・吉村昭の死から3年あまり
〈生き残った者のかなしみを描く小説集〉、5作が収められた『遍路みち』(津村節子)。
「私の身辺のことを綴ったものばかりを選び、ほとんど事実に近い」とあとがきにあった。

「楽しいことも 嬉しいことも あったはずなのに…、
悔いのみ抱いて 生きてゆく遍路みち」
夫の死にまつわる騒動のいきさつなど語られ、自らの軽率を省みている。
十分な介護ができなかった悔い。
作家夫婦の暮らしぶりも垣間見え、情愛など染み入るが、どうあっても苦はなくならないという生きることの事実を深く強く思い知らされ、胸を突いてくる作品だった。一気に読んだ。