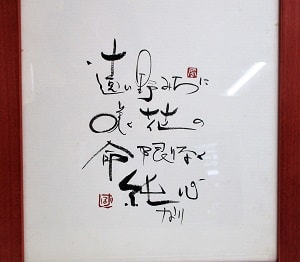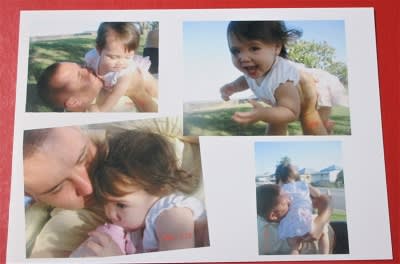昨日27日、古典文学の舞台を紹介し、散策路を策定する「文遊回廊」が、京都新聞で始まった。第1回目は『方丈記』で、国際日本文化研究センター教授・荒木浩氏が解説されている。地下鉄東西線石田駅から、長明の庵跡とされる方丈石を山中に訪ね、帰り道には長明を捉えた日野の里の法界寺や親鸞ゆかりの日野誕生院へと足を延ばすコースがとられていた。
この記事で私が心に留めたのは方丈石ではなく、岩間寺だった。滋賀県大津市と京都府宇治市の境にある標高443mの岩間山中腹に位置する真言宗の寺。西国三十三所、びわ湖百八霊場の一として、また、芭蕉が「古池や蛙とびこむ水の音」と詠んだとされる池のある寺、としてその名を記憶していた。大津市には芭蕉ゆかりの地が多く、4ヵ月住んだという幻住庵、石山寺、墓のある義仲寺、などと点在している。岩間の名が出てくる『幻住庵記』、そのことからも、この池である信憑性は高いようだ。
引用されていた原文を読み、芭蕉よりはるかに以前、長明が岩間寺に詣でていたことに気づかされた。
岩間寺は勅願寺院で、熊野、吉野と並ぶ日本三大霊場の一つとして隆盛していたという。長明は気が向けば、近江の国へと山を越え、あるときは岩間寺に詣で、またある時は石山寺に参拝。またある時は蝉丸の翁の旧跡を訪れているし、猿丸太夫の墓を訪れたりもしていた。
【京都を守護する大神社の御曹司だった男は、いろいろあって俗世を厭い、平安京の郊外を南北するうち、ついに「一間」の山暮らしを「故郷」と感じる。その代わり、東国の鎌倉将軍の知己まで得た彼の視点は、縦横に闊達。長明の身心はすこぶる健やかで自在】、と解説に。
昨日は友人との約束があったのだが、体調不良とのことで前の晩に予定はキャンセルとした。で、時間が空いていた。決断は早く、早速午後から車でひとっ走り岩間寺に向かうことにした。
九十九折りの山道、歩いて登る人の脇を車で通り過ぎてしまう私。ちょっとうしろめたさを覚えた。ここのご本尊は毎夜、136の地獄をかけ巡って人々を救済し、翌朝には汗をかきながら戻ってくるので「汗かき観音」とも呼ばれるのだとか。できるなら、汗をかかないといけないのだ、な…。
本堂と不動堂との間、観音堂の前に小さな池はあった。
参道入口には石山観音への道は38丁と記した石碑があった。空を覆う枝の広がりを見せる桂の大樹。本堂前の大銀杏の黄葉はみごとなことだろう。騒音などとは無縁の静かな山中で3、40分を過ごして戻った駐車場で、車ですれ違った男性と出会い、どちらからともなく「こんにちは」と言葉を交わした。楽しちゃったな…。