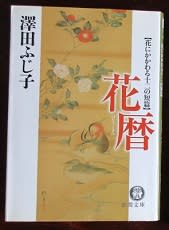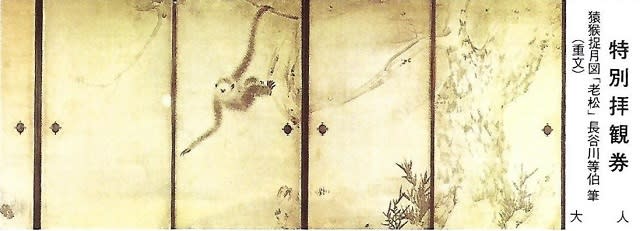【「鬼の目にも涙や流す節分の 窓の柊に行きあたりつつ」
浅井了意の「出来斎京土産(できさいきょうみやげ)」が狂歌に詠んだ五条天神社の節分祭。
平安遷都に際し大和から勧請した古社。五条大路にあり、五条天神宮とも称した。
祭神少彦名命(すくなひこなのみこと)は医薬の祖神。近世、節分に朮(おけら)を受け家でくすべ悪鬼を払う習いがあった。日本最古という宝船図の授与は今も有名で、神朮(しんじゅつ)の風習を訪ね求める参詣者もある。】
と記された坂井輝久氏の『京近江 名所句巡り』に導かれ、初めて五条天神社を訪ねてみた。
烏丸四条から西へ、西洞院通を南に松原通まで下がると右手に鳥居が目に入る。


近隣の氏子さん?か、顔見知りらしい人が多かった。

宝船と聞いてうかぶ七福神のイメージとは大きく異なって、船には一束の稲穂が乗っているだけ。
日本最古という宝船図には関心もあったが、こうして見本が貼り出されていて、それをこともあろうか?写真に収めてすます。
そんな人間でも、この一年の息災の祈りは医薬の祖神にとどくものかしら…。
※「出来斎京土産」というのはネットで検索してみたところ、出来斎という主人公が洛中洛外の名所を遍歴して狂歌を詠む趣向の名所案内記と説明されたものがあった。作者の浅井了意は、江戸前期の仮名草紙作者で、浄土真宗の僧となったという。
ぎょうさんの齢いただく年の豆 桂信子
ああ、豆ばらに…。
浅井了意の「出来斎京土産(できさいきょうみやげ)」が狂歌に詠んだ五条天神社の節分祭。
平安遷都に際し大和から勧請した古社。五条大路にあり、五条天神宮とも称した。
祭神少彦名命(すくなひこなのみこと)は医薬の祖神。近世、節分に朮(おけら)を受け家でくすべ悪鬼を払う習いがあった。日本最古という宝船図の授与は今も有名で、神朮(しんじゅつ)の風習を訪ね求める参詣者もある。】
と記された坂井輝久氏の『京近江 名所句巡り』に導かれ、初めて五条天神社を訪ねてみた。
烏丸四条から西へ、西洞院通を南に松原通まで下がると右手に鳥居が目に入る。


近隣の氏子さん?か、顔見知りらしい人が多かった。

宝船と聞いてうかぶ七福神のイメージとは大きく異なって、船には一束の稲穂が乗っているだけ。
日本最古という宝船図には関心もあったが、こうして見本が貼り出されていて、それをこともあろうか?写真に収めてすます。
そんな人間でも、この一年の息災の祈りは医薬の祖神にとどくものかしら…。
※「出来斎京土産」というのはネットで検索してみたところ、出来斎という主人公が洛中洛外の名所を遍歴して狂歌を詠む趣向の名所案内記と説明されたものがあった。作者の浅井了意は、江戸前期の仮名草紙作者で、浄土真宗の僧となったという。
ぎょうさんの齢いただく年の豆 桂信子
ああ、豆ばらに…。