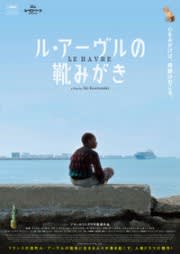8月1・2・3日と高野山夏季大学に参加してきました。雨の高野山でした。
高野山教学部長を勤められる小藪実英さん(福知山の観音寺のご住職)は、ぜひにと高野山へ招かれたことで高校教諭退職後の人生設計が狂ってしまったと、ユーモアを交えながら本音に近い?胸の内も覗かせてくださるお話がありました。(「弘法大師に学ぶ前向きな心」)
4歳で父親と死別、後に寺が全焼するなど苦しいことが多かったけれど「嫌だと思えばストレスに。負けないぞ、負けないぞと思えば根性になる」。不幸があるから生きていく力がつくのであって、「人の値打ちは心の状態で決まる」「心の偏差値を高めよう」とお話でした
最も楽しみにしたのは、最終日の姜尚中氏の「心の力」と題したお話です。
9時からの開始に合わせ8時半開場と案内でした。眠くなる脳みそにつける薬はなく、負けっぱなしの二日間でしたが、この日ばかりは気力充実!? 「6時の鐘」で8時の鐘が撞かれ始めたのを聞きながら会場に向かいましたところ、すでに長蛇の列。ゲストお二人への期待度の証しか、予定より少し早い目の開場でした。
テレビで拝見しているだけだった姜さんが目の前に。あの声です! ソフトな語り口はそのままですが、マイクにのって声もよく通り、メリハリがあってテンポも良く、心の中に収まっていきます。
「相続とは、亡くなった人の人生、つまり物語、命・魂をいただくことなのです」ということばは印象に残りました。
漱石の『こころ』も然り。先生の遺書を私が受けて、第三者に渡していく物語であること。母親の愛情を知らずに、自分は余計者意識のまま「不安」の虜で生きた漱石。「人間一生に一度 真面目になれ」(『虞美人草』)のことばをひいて、「悲劇は人を真剣にさせる」、どうしたら良いのかと、考え抜くことが心の力をつける。最後に、「自分は次の世代に何を伝えたいか」ということになるわけだが、と投げかけられて…。遺書を残すことは一つの形だと言えそうです。
由紀さおりさんは、あの美しい歌声を時々ご披露くださりながら「日本語の美しさ」を説かれました。「日本語は旋律」と。童謡に見られる日本語のやさしさ、美しい響き。濁音と鼻濁音を区別をすることなど、改めて意識させられた点でした。
2日午後から、今回大きな願いでもあった女人堂へ足を運ぶことができました。宿坊からは歩いて20分ほど。すれ違う人もいない道を傘をさしながら一人ぶらりと訪ねましたら、同じような思いの先客が一人。
高野山は女人禁制の時代がありました。高野山の入り口ですが、この先へは入ることのできない女性のための参詣所として設けられた女人堂。建立以来300年、唯一現存する不動坂口(京街道口)のお堂です。女性たちの信仰の篤さ、そんな思いをちょっと想像しながら、ゆっくり時間を過ごして戻りました。