珍しく自分で買った小説を読む。
厳密にいうと「自分で買った」とは言い難い。なぜなら、ひょんなことで、親しい人から頂いた図書券で買った本だからだ。
図書券を頂いたとき、さて何を買おうかなと迷った。その時、この『献灯使』の広告が目についた。そうだ、小説を書く人からもらったのだから小説を買おうと思った。
多和田さんのものにしたのはそれなりの理由がある。かつて、「日本語とはどんな言葉だろう」という小論を同人誌に書いた折、この人の評論やエッセイ、そして小説からずいぶん学ばせてもらった。もちろん小説はとても面白かった。

多和田さんは、言葉に敏感で、常に自分の使っている言葉をメタレベルから見ながらそれに対して自己干渉してゆくところがある。それは例えばある種の「言葉遊び」のようなものとして表現されるが、それは決して「遊び」ではない。
例えば、この表題作では、どうやら外来語が禁止されているらしく、ジョギングは「駆け落ち」と言い換えられる。ただしこれは、古い日本語が持っていた色恋沙汰とは無縁な、「駆ければ血圧が落ちる」から来たらしい。同様に、ターミナルは「民なる」になる。

ここですでにほのめかしたように、これはリアルタイムの小説ではなく、ある種の近未来を描いたものである。表題作のみならず、それに付された短編、「韋駄天どこまでも」(これには漢字を分解し組み立てるという実験的な試みがなされている)、「不死の鳥」、「彼岸」、「動物たちのバベル」もすべて近未来を示している。
とくに最後の短編は、人間たちが滅亡した後の、動物たちの対話劇となっている。
しかしである、作者自身がロバート・キャンベル氏との対談で語っているように、これは決してSF小説や未来小説ではなく、リアルなものでもある。なぜなら、表題作をはじめ、四つの短編すべてのバックにあるものは、あの3・11の大地震、大津波、そして原発事故という隠しおおせようのないものだからである。
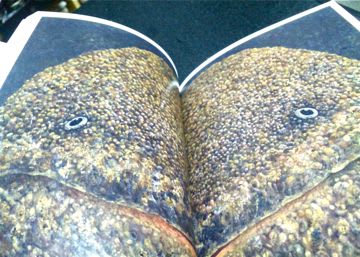
これらはある種のデストピアとして描かれているが、それは災害の悲惨さにとどまらず、先にみた外来語の禁止などの規制があったり、移動の自由が規制されたりしているある種の管理社会として示されている。
しかし、その管理の主は決して表面化されない。
多和田さんはそれを、強制によらない自己内面化による自主規制として描いている。そして、それこそ、私たちが直面している管理者会の罠なのだ。
アーレント流にいうならば、それはノウバディによる支配であり管理である。しかし、ノウバディの意向を内面化した支配は、もっとも強力な支配ともいえる。

この緩やかなデストピアは、どうやら鎖国という情況設定に依拠している面がある。したがって、このデストピアからの脱出はその外部との接触を回復することである。
主人公のひとり、未来少年「無名」は、15才の折、秘密組織から「献灯使」に選ばれる。この「献灯使」が、日本の歴史上の「遣唐使」をもじったものであることは容易にみてとれる。
老人がいつまでも「そのまま」生き延びてしまう自同性の社会は、自らの他者である外部との接触を若者に託すことによって未来を垣間見る。

これらの小説は、ドイツに在住する著者が、3・11を踏まえて観念的に紡ぎだしたものでは決してない。多和田さんは、フクシマ原発のすぐ近く、浪江町などを訪問し、その住民たちと対話するなかでこの小説の構想を得たという。
だからこそ、これはSFではなく、リアルな、私たちの物語なのだ。

最後に、多和田さんの自作の朗読を以下に載せる。多和田さんは、ドイツ語や日本語で自作の朗読をあちこちで行っている。音楽家や舞踏家とのコラボもあるようだ。
ここに載せたものは、「群像」1月号で私が読んだロバート・キャンベル氏との対談の前か後に行われたものである。ぜひ、多和田さんのナマの表情ともども聴いてみてほしい。
https://www.youtube.com/watch?v=ywXTGBfdkzo
厳密にいうと「自分で買った」とは言い難い。なぜなら、ひょんなことで、親しい人から頂いた図書券で買った本だからだ。
図書券を頂いたとき、さて何を買おうかなと迷った。その時、この『献灯使』の広告が目についた。そうだ、小説を書く人からもらったのだから小説を買おうと思った。
多和田さんのものにしたのはそれなりの理由がある。かつて、「日本語とはどんな言葉だろう」という小論を同人誌に書いた折、この人の評論やエッセイ、そして小説からずいぶん学ばせてもらった。もちろん小説はとても面白かった。

多和田さんは、言葉に敏感で、常に自分の使っている言葉をメタレベルから見ながらそれに対して自己干渉してゆくところがある。それは例えばある種の「言葉遊び」のようなものとして表現されるが、それは決して「遊び」ではない。
例えば、この表題作では、どうやら外来語が禁止されているらしく、ジョギングは「駆け落ち」と言い換えられる。ただしこれは、古い日本語が持っていた色恋沙汰とは無縁な、「駆ければ血圧が落ちる」から来たらしい。同様に、ターミナルは「民なる」になる。

ここですでにほのめかしたように、これはリアルタイムの小説ではなく、ある種の近未来を描いたものである。表題作のみならず、それに付された短編、「韋駄天どこまでも」(これには漢字を分解し組み立てるという実験的な試みがなされている)、「不死の鳥」、「彼岸」、「動物たちのバベル」もすべて近未来を示している。
とくに最後の短編は、人間たちが滅亡した後の、動物たちの対話劇となっている。
しかしである、作者自身がロバート・キャンベル氏との対談で語っているように、これは決してSF小説や未来小説ではなく、リアルなものでもある。なぜなら、表題作をはじめ、四つの短編すべてのバックにあるものは、あの3・11の大地震、大津波、そして原発事故という隠しおおせようのないものだからである。
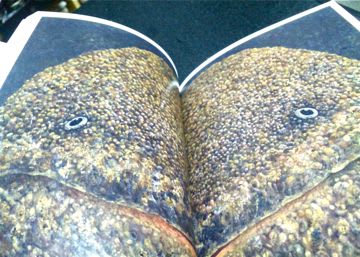
これらはある種のデストピアとして描かれているが、それは災害の悲惨さにとどまらず、先にみた外来語の禁止などの規制があったり、移動の自由が規制されたりしているある種の管理社会として示されている。
しかし、その管理の主は決して表面化されない。
多和田さんはそれを、強制によらない自己内面化による自主規制として描いている。そして、それこそ、私たちが直面している管理者会の罠なのだ。
アーレント流にいうならば、それはノウバディによる支配であり管理である。しかし、ノウバディの意向を内面化した支配は、もっとも強力な支配ともいえる。

この緩やかなデストピアは、どうやら鎖国という情況設定に依拠している面がある。したがって、このデストピアからの脱出はその外部との接触を回復することである。
主人公のひとり、未来少年「無名」は、15才の折、秘密組織から「献灯使」に選ばれる。この「献灯使」が、日本の歴史上の「遣唐使」をもじったものであることは容易にみてとれる。
老人がいつまでも「そのまま」生き延びてしまう自同性の社会は、自らの他者である外部との接触を若者に託すことによって未来を垣間見る。

これらの小説は、ドイツに在住する著者が、3・11を踏まえて観念的に紡ぎだしたものでは決してない。多和田さんは、フクシマ原発のすぐ近く、浪江町などを訪問し、その住民たちと対話するなかでこの小説の構想を得たという。
だからこそ、これはSFではなく、リアルな、私たちの物語なのだ。

最後に、多和田さんの自作の朗読を以下に載せる。多和田さんは、ドイツ語や日本語で自作の朗読をあちこちで行っている。音楽家や舞踏家とのコラボもあるようだ。
ここに載せたものは、「群像」1月号で私が読んだロバート・キャンベル氏との対談の前か後に行われたものである。ぜひ、多和田さんのナマの表情ともども聴いてみてほしい。
https://www.youtube.com/watch?v=ywXTGBfdkzo

















