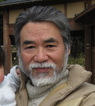第二回
私は、市立堺病院及び堺市長に対して下記のような「質問及び要望書」を出して母子同室の実現のために活動しています。これは5年にわたる長期戦でした。
やっと昨年(2006年6月)に母子同室になりました。
一人の市民が声をあげることで改善できるのです。
正しいことを無欲で言い続ける事こそ最大の武器です。
最後は子育てに理解のある市民派女性議員が考え方に賛同してくれ、情報公開の場に同席してくれたり、
委員会で市当局に質問してくれたりしてやっと実現しました。
病院の助産師など内部にも理解者は必要です。
お母さんと赤ちゃんのためには母子同室は必要です。
不幸な子育てのスタートを切らせないためにも。
次に堺市に対して公開質問状だして市当局に回答を求めその回答に基づき話し合いを繰り返しました。
質問状と回答をお読みください。
*****************
2003年7月11日
堺市長 様
市立堺病院院長
特定非営利活動法人 たまごママネット
理事長 新井 一令
住所 ○○○
質問書及び市立堺病院産婦人科における母子同室の実施要望
2002年11月に市立堺病院からの回答について、母子同室ができない理由についての回答が不十分であり、再度の質問と要望を行う。
1 母児同室について
回答(堺市)
ご質問の「母児同室」については、よい点が多数あることを認識しています。
しかしながら、本院では、次に掲げる理由により、「母児同室」の全面的な実施は行っていませんのでご了解ください。
なお、現在のところ、本院でも、妊産婦様から「母児同室」のご希望があった場合において、個室が空いているは「母児同室」を行っていますが、妊産婦様からの当該のご希望が余りないのが実情です。
質問
妊婦からの希望がないのではなく「母児同室」の必要性の教育がなされていないのではないですかされているのであれば具体的に回答してください。
また、私どもの法人にはの堺市民多くから母子同室ではないので、同室が出来るところで分娩をするという声が寄せられています。貴院の患者からも、母子同室にして欲しかった。
退院してから大変だったという声が多数よせられています。それについてはどのようにお考えですか見解を求めます。
回答(堺市)
産科の専門病院では「母児同室」を実施しやすいと考えますが、本産婦人科病棟は、妊産婦意外の患者様も多数入院しておれれる混合病棟です。
従いまして、重傷な患者様の中には、同じフロアの病室から聞こえてくる赤ちゃんの泣き声が気にかかって休養できないという方もおられますので、母児同室の全面実施が困難です。
質問
ユネスコの子ども権利条約9条に関連して「母児同室」をすべきだと思いますが貴院の見解をお答えください。
「母子同室」は、産後の母と子は一つの単位であり、不可分である事は、子ども権利条約にも、その第9条に明記してあります。(子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。
はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。)
出生直後から母と子を同室にする事により、赤ちゃんから発せられる様々なメッセージを感じることができます。
泣き声やその視線に対して、母親はすばやく反応し、授乳し、、オムツを替えてやり、話し掛け、そして抱っこを行います。
するとそれに対して赤ちゃんは、早期から養育者である母親が自分に関心を向けているかどうかを敏感に感じながら
発育するといわれてます。
母親からの働きかけに対して、赤ちゃんも反応し、お互いに密接で深いコミュニケーションが育まれます。
この母子相互作用により赤ちゃんには母親に対する愛着が育ち、母親の母性はより豊かになります。
母と子の心理的一体感が育まれると共に、親子の絆もまた強いものに育っていきます。
別室制の施設で教えられた赤ちゃんの扱いを、最良の育児法であるかのように錯覚して、帰宅後もそのやり方をまねて育児するしかないのが実情です。
その結果、育児不安を欠けてしまいます。
赤ちゃんの扱いと母乳哺育による母性が完成されないからです。
母と子の絆がつくられないと「可愛いはずなのに愛せない」と悩む母親になってしまいます。
「最初の一週間」こそ育児体験を持たない、核家族化する今日の妊婦さんにとっては、育児実習のゴールデンタイムでもあるわけですが、この人生の始まりにおける一瞬の手抜き、うっかりした瞬時の息抜きが、一生の悔いになります。
多くの赤ちゃんは天国のような胎内生活を経験し、産道ではこれまで経験したことのない痛みや苦痛の試練を経て、
新しい生活が始まります。
それまでの暖かく宇宙遊泳のような楽しい世界と比べて、この未知の世界は騒がしく、まぶしく、寒く、そして重力のある、不自由な世界です。
心ない病院では、形ばかりの母との出会いを終えると、直ちに新生児室へとつれていかれます。
突然の環境の激変です。
そこでは心を慰めてくれる懐かしい母の匂いも温もりも、そしてやさしい声も聞こえてはきません。
不安を訴えても誰も答えてはくれません。
更に空腹を訴えても決められた時間が来るまで、その欲求は満たされません。加えて新生児室では、
おっぱいからの直接の授乳時のように、五官を通じて行う互いの心の交流は望むべくもなく、多くの場合一定に時間を決めて、しかも哺乳瓶による「くわえのみ」で牛のお乳が与えられます。
おしっこや排便でオムツが汚れて不快を訴えても誰も答えてくれません。
どんなにメッセージを送ってもお母さんは現れてくれません。
誰一人として不安や不満、そして甘えを受け入れてくれません。
このように出生直後より赤ちゃんの生理や欲求を無視し、大人のルールを 守る事を強制した扱いに、やがて赤ちゃんはメッセージを送る事をあきらめ、人との交流・・・例えそれが自分の母親であっても・・・お互いのコミュニケーションを取りやめてしまい、自分の殻に閉じこもります。
サイレントベビー予備軍の誕生です。
皆さんの大切なお子さんのために、見せ掛けのきらびやかさにまどわされずに心の豊かさを、母と子の間に育まれる基本的信頼と心理的一体感と、母と子の共生生活へと向けて素晴らしい出発(たびたち)の場として施設が必要である。
すべての両親と新生児は、生まれたその瞬間から親密な接触を持つ権利がある。
母子が一緒にいることは、女性ないし赤ちゃんに影響を及ぼす帝王切開分娩やその他の医学的介入が行われた場合を含め、あらゆる状況において奨励されるべきであると思いますが貴院の見解を求めます。
産褥早期に母親と新生児をルーチンに離してしまうことによって生じたと思われる不利益に関する証拠はこの手法が広く普及した30年又はそれ以上の間に蓄積している。
いくつかの対照試験で、出産直後のの数時間に母親と新生児の相互作用を規制する施設の方針と、この期間に相互作用を促す方針との影響比較研究された。
母親としての愛情あふれた態度は、児との触れあいを制限された母親には、自由に触れ合うことを促された母親よりも有意に少なかった。
母子同室の方針と比較して母子分離がルーチン化した「市立堺病院」の方針は、社会的に成熟していない初産の母親が「幼児虐待やネグレクト」を引き起こす危険度が高くなるのではないでしょうか。
貴院の見解を求めます。
母子同室を奨励するとともに、正常新生児を集中管理する新生児室の廃止を求め、その見解を求めます。
まさに「市立堺病院」は赤ちゃんの人権や母性を育むなどという考え方がないといわざるを得ない。
猛省を促すとともに早期の母子同室を求めます。
また、入院中の母子の接触についてのスケジュール及び指導のための文書の提供を求める。
****************
次に続きます。
私は、市立堺病院及び堺市長に対して下記のような「質問及び要望書」を出して母子同室の実現のために活動しています。これは5年にわたる長期戦でした。
やっと昨年(2006年6月)に母子同室になりました。
一人の市民が声をあげることで改善できるのです。
正しいことを無欲で言い続ける事こそ最大の武器です。
最後は子育てに理解のある市民派女性議員が考え方に賛同してくれ、情報公開の場に同席してくれたり、
委員会で市当局に質問してくれたりしてやっと実現しました。
病院の助産師など内部にも理解者は必要です。
お母さんと赤ちゃんのためには母子同室は必要です。
不幸な子育てのスタートを切らせないためにも。
次に堺市に対して公開質問状だして市当局に回答を求めその回答に基づき話し合いを繰り返しました。
質問状と回答をお読みください。
*****************
2003年7月11日
堺市長 様
市立堺病院院長
特定非営利活動法人 たまごママネット
理事長 新井 一令
住所 ○○○
質問書及び市立堺病院産婦人科における母子同室の実施要望
2002年11月に市立堺病院からの回答について、母子同室ができない理由についての回答が不十分であり、再度の質問と要望を行う。
1 母児同室について
回答(堺市)
ご質問の「母児同室」については、よい点が多数あることを認識しています。
しかしながら、本院では、次に掲げる理由により、「母児同室」の全面的な実施は行っていませんのでご了解ください。
なお、現在のところ、本院でも、妊産婦様から「母児同室」のご希望があった場合において、個室が空いているは「母児同室」を行っていますが、妊産婦様からの当該のご希望が余りないのが実情です。
質問
妊婦からの希望がないのではなく「母児同室」の必要性の教育がなされていないのではないですかされているのであれば具体的に回答してください。
また、私どもの法人にはの堺市民多くから母子同室ではないので、同室が出来るところで分娩をするという声が寄せられています。貴院の患者からも、母子同室にして欲しかった。
退院してから大変だったという声が多数よせられています。それについてはどのようにお考えですか見解を求めます。
回答(堺市)
産科の専門病院では「母児同室」を実施しやすいと考えますが、本産婦人科病棟は、妊産婦意外の患者様も多数入院しておれれる混合病棟です。
従いまして、重傷な患者様の中には、同じフロアの病室から聞こえてくる赤ちゃんの泣き声が気にかかって休養できないという方もおられますので、母児同室の全面実施が困難です。
質問
ユネスコの子ども権利条約9条に関連して「母児同室」をすべきだと思いますが貴院の見解をお答えください。
「母子同室」は、産後の母と子は一つの単位であり、不可分である事は、子ども権利条約にも、その第9条に明記してあります。(子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。
はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。)
出生直後から母と子を同室にする事により、赤ちゃんから発せられる様々なメッセージを感じることができます。
泣き声やその視線に対して、母親はすばやく反応し、授乳し、、オムツを替えてやり、話し掛け、そして抱っこを行います。
するとそれに対して赤ちゃんは、早期から養育者である母親が自分に関心を向けているかどうかを敏感に感じながら
発育するといわれてます。
母親からの働きかけに対して、赤ちゃんも反応し、お互いに密接で深いコミュニケーションが育まれます。
この母子相互作用により赤ちゃんには母親に対する愛着が育ち、母親の母性はより豊かになります。
母と子の心理的一体感が育まれると共に、親子の絆もまた強いものに育っていきます。
別室制の施設で教えられた赤ちゃんの扱いを、最良の育児法であるかのように錯覚して、帰宅後もそのやり方をまねて育児するしかないのが実情です。
その結果、育児不安を欠けてしまいます。
赤ちゃんの扱いと母乳哺育による母性が完成されないからです。
母と子の絆がつくられないと「可愛いはずなのに愛せない」と悩む母親になってしまいます。
「最初の一週間」こそ育児体験を持たない、核家族化する今日の妊婦さんにとっては、育児実習のゴールデンタイムでもあるわけですが、この人生の始まりにおける一瞬の手抜き、うっかりした瞬時の息抜きが、一生の悔いになります。
多くの赤ちゃんは天国のような胎内生活を経験し、産道ではこれまで経験したことのない痛みや苦痛の試練を経て、
新しい生活が始まります。
それまでの暖かく宇宙遊泳のような楽しい世界と比べて、この未知の世界は騒がしく、まぶしく、寒く、そして重力のある、不自由な世界です。
心ない病院では、形ばかりの母との出会いを終えると、直ちに新生児室へとつれていかれます。
突然の環境の激変です。
そこでは心を慰めてくれる懐かしい母の匂いも温もりも、そしてやさしい声も聞こえてはきません。
不安を訴えても誰も答えてはくれません。
更に空腹を訴えても決められた時間が来るまで、その欲求は満たされません。加えて新生児室では、
おっぱいからの直接の授乳時のように、五官を通じて行う互いの心の交流は望むべくもなく、多くの場合一定に時間を決めて、しかも哺乳瓶による「くわえのみ」で牛のお乳が与えられます。
おしっこや排便でオムツが汚れて不快を訴えても誰も答えてくれません。
どんなにメッセージを送ってもお母さんは現れてくれません。
誰一人として不安や不満、そして甘えを受け入れてくれません。
このように出生直後より赤ちゃんの生理や欲求を無視し、大人のルールを 守る事を強制した扱いに、やがて赤ちゃんはメッセージを送る事をあきらめ、人との交流・・・例えそれが自分の母親であっても・・・お互いのコミュニケーションを取りやめてしまい、自分の殻に閉じこもります。
サイレントベビー予備軍の誕生です。
皆さんの大切なお子さんのために、見せ掛けのきらびやかさにまどわされずに心の豊かさを、母と子の間に育まれる基本的信頼と心理的一体感と、母と子の共生生活へと向けて素晴らしい出発(たびたち)の場として施設が必要である。
すべての両親と新生児は、生まれたその瞬間から親密な接触を持つ権利がある。
母子が一緒にいることは、女性ないし赤ちゃんに影響を及ぼす帝王切開分娩やその他の医学的介入が行われた場合を含め、あらゆる状況において奨励されるべきであると思いますが貴院の見解を求めます。
産褥早期に母親と新生児をルーチンに離してしまうことによって生じたと思われる不利益に関する証拠はこの手法が広く普及した30年又はそれ以上の間に蓄積している。
いくつかの対照試験で、出産直後のの数時間に母親と新生児の相互作用を規制する施設の方針と、この期間に相互作用を促す方針との影響比較研究された。
母親としての愛情あふれた態度は、児との触れあいを制限された母親には、自由に触れ合うことを促された母親よりも有意に少なかった。
母子同室の方針と比較して母子分離がルーチン化した「市立堺病院」の方針は、社会的に成熟していない初産の母親が「幼児虐待やネグレクト」を引き起こす危険度が高くなるのではないでしょうか。
貴院の見解を求めます。
母子同室を奨励するとともに、正常新生児を集中管理する新生児室の廃止を求め、その見解を求めます。
まさに「市立堺病院」は赤ちゃんの人権や母性を育むなどという考え方がないといわざるを得ない。
猛省を促すとともに早期の母子同室を求めます。
また、入院中の母子の接触についてのスケジュール及び指導のための文書の提供を求める。
****************
次に続きます。