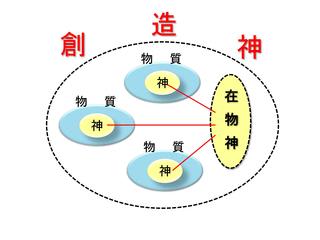バイブリシズム(聖句主義)という活動を理解するのは難しいですね。
もう少し説明を追加しましょう。

<知らないことの弊害からアプローチ>
今回は「聖句主義を知らないが故の弊害」をあげつらってみましょう。
まず、「聖句は膨大な内容を持っていて、絶対的な解読は人間にはほとんど出来ないという認識が曖昧になる」という事象から。
聖句主義はその認識を肝に据えて、そこから~ある意味、開き直って~出発しています。
ところがこの行き方を知らないと、そのあたりが曖昧なままになります。
+++
そして、漠然と解読出来ると思ったりして解読を試みますが、毎回、上手く行かない。
そこで、、これは自分の知力が足りないからではないか、と思ったりもします。
「密かに」そう思う。 だってばれたら「あいつは駄目だ」と烙印を押されることを恐れますからね。
そして、こういうことを繰り返していると、人間の心は萎縮していきます。

<「救い」の確信も>
たとえばこれはいわゆる「救い」への確信にも影響しています。
「正しい」解読があると思っているので、自分の聖書解釈では「救われないのでは・・・」と漠然と感じることになる。
その結果、「救い」への解釈も浅いものとなり、怖くなって萎縮することにもなるのです。
+++
こうなると~「確信のない」聖句解釈状態で~誰か他の人(牧師さんとか、三浦綾子さんとか)の解釈にしがみつく、ということもします。
そして、一旦しがみつくと、他者に向かってはそれを自己の見解だと断定的に表現しやすくなります。
こういう人はまた、他の解釈を見ると「異端!」とヒステリックに非難したりもします。
+++
もうどうしょうもない・・・といった感じですが、理由は次のところにあります。
実は、確信無く鵜呑みした他人の解釈は、人間の意識の中で不安定な状態にあるのです。
すると人はその不安感から逃れようとして他者を非難します。
他者を非難してると、一時的に自分の解釈が確信あるもののように錯覚できますからね・・・。
+++
余談ですがここには「キリスト者の自由」はありません。
またこうした信者の群れに、ビジネスマンなど知的な一般人が加わりたいと思うことは、ほとんど起きません。

<全般的影響を示唆する事例>
話を戻します。
バイブリシズムへの無知が、広く日本人の思考全般をを萎縮させていることも示唆する事例を、鹿嶋のこのブログへのコメントでもって示してみましょう
このブログでひところよくコメントを書いて下さった方に「石ころ」さんというペンネームの方がおられました。
彼女など、ひたすら福音の真髄を求め続けておられて、台所で料理しているとき、突然聖霊を受けた人でした。
その彼女ですら、こんなコメントを寄せてこられました。
(コメント)
・・・・・・・・・・・・
主を知る自由を知りました (石ころ)
2006-07-26 07:21:35
初めまして、何時も学ばせて頂いています。
始めて(バイブリシズムの思想を)目にしたときには、かなりショックを受けました。
20年以上の信仰生活の中で、このように聖書を読む事が許されるのだとは、思いもつきませんでした。
しかし、間違いに出会ったときの、ザワザワとした違和感はありませんでした。
新しい自由を知って、「・・すべからず、・・すべし」は、主を探求していないと思えるようになりました。
「吟味しなさい」というみことばは、誰にでも、御霊の導きがあるということだと思っています。
何も恐れることはない、主を知りたいとワクワクして読ませて頂いています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
+++
~次の方も教理統一主義的な思考に流れる傾向を言っておられます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
はじめまして (Cissac)
2006-07-31 11:51:22
はじめまして、lukeさんのページで紹介があり、そこから飛んできました。
4年ほど前にイエス様を救い主として受け入れた者です。
聖句主義、教理主義とありますが、聖句を追求すると言いながらも
知らぬ間に教理でガチガチ
ということもあるのかなと思っています。
(後略)
・・・・・・・・・・・・・・
+++
~次の方、SAITOHさんは、鹿嶋に代わって解説して下さっていますが、同時に、やはり、日本人は教理統一方式敵思考に流れやすいことを指摘されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自ら考えることがカギ (SAITOH)
2006-07-27 01:51:44
まず、自分で考えること、探求し続ける姿勢が大事なのだと思いますよ。人生の問題に正解はないように、聖書の解釈にも解答はありません。
知れば知るほど、面白みが増してくる、と同時に自分の愚かさも見えてきて、人の意見を聞こうと思うようになります。
枠が必要だと思うなら、使徒信条、あるいはニカイア信条あたりで、十分なのではないでしょうか。仮に、それにも囚われずに解釈するとしても、解釈するだけなら問題はありません。
特定の立場、教義を絶対視してしまうことが問題なのです。
しかし、往々にして、そうなってしまいがちですね。
そして、特定の教理を選び取って、それに従うこと(悪く言うと思考停止ですけど)がキリスト教信仰だと考えている人が多いようにも思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回はこれくらいにしておきましょうか。