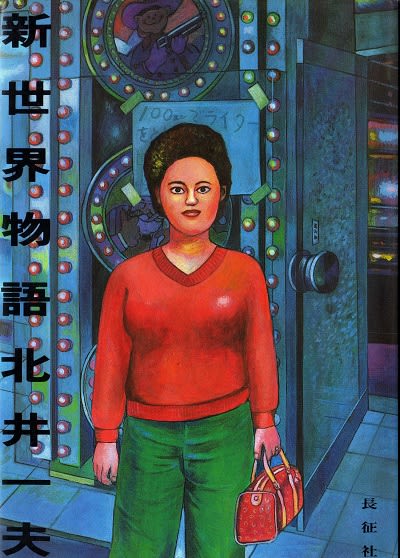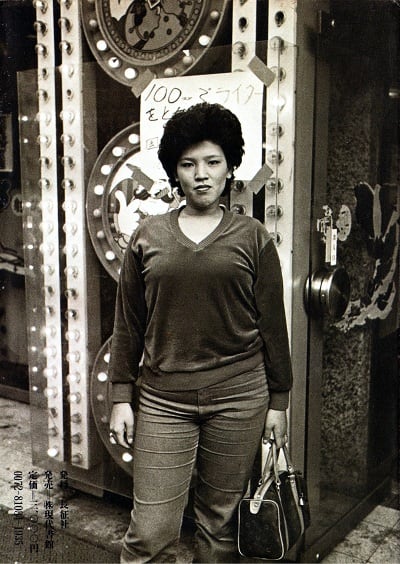大江・岩波沖縄戦裁判が、最高裁において原告(旧日本軍の守備隊長ら)の敗訴に終わった。訴訟の対象となったひとつが、大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書、1970年)であった。施政権返還の直前に出された本だが、沖縄において生起する声と、醜いヤマトゥの姿を提示する内容は、残念なことに、まったく古びていない。
これはいわゆる「集団自決」についての告発書ではない。「集団自決」の責任に関する旧守備隊長の言動について、「かれ個人は必要でない」としつつ、日本人の「想像力の問題」の奥底を抉りだそうと試みている書である。
なお原告は、歴史修正主義の尻馬に乗っていたためか、この本を読んでいなかったと言われる(訴訟の対象を読んでいないとはどういうことか?)。裁判が一応の決着を見たこともあり、あらためて読んだ。

言葉のひとつひとつを練った上で、思いを伝えんがための、大江健三郎独自の文章構造と節回し。それらは私の好きだった『「雨の木」(レイン・ツリー)を聴く女たち』や『人生の親戚』でも感じ入ったものだったが、ここでは、想像世界を繰り広げるわけにいかない対象だけに、より直接的に迫ってくる。施政権返還前にして、「沖縄に日本が属する」ものとして、また自らを醜いヤマトゥの人間として、思考を進めたひとつの形である。
そういえば、大江健三郎がノーベル文学賞を受賞したとき、故人となってもはや賞を受けることのできない大岡昇平や安部公房、そして当然賞を受けるべき存在としてマリオ・バルガス・リョサやミラン・クンデラの名前を挙げていた記憶がある。その後、リョサがノーベル賞を受けたが、さてクンデラはどうなるのか。
無駄なことは言わず、いくつか大江の言葉を拾ってみる。
「新しい沖縄残酷物語をくりだして、旅行者の好奇心にちょっとした賦活作用をあたえてやる奉仕などまで、なぜ沖縄に生きつづける人々がおこなわねばならないだろう?」
「・・・現実には行使できていない沖縄の民衆の主権をも、あたかもつつみこんでいるすべての日本人の主権であるかのように擬装して、本土から日本国の潜在主権というもうひとつ別の「御意」をもちこんでゆくところの、われわれもまた毒ガスの側に立っている。」
「日本人とはなにか、という問いかけにおいて僕がくりかえし検討したいと考えているところの指標のひとつに、それもおそらくは中心的なものとして、日本人とは、多様性を生きいきと維持する点において有能でない属性をそなえている国民なのではないか、という疑いがあることもまたいわねばならない。」
「沖縄の民衆の抵抗は、つきつめれば、この核兵器による恐怖の均衡の体制にたいする、恐怖する者、殲滅される危機のさなかに生きる者としての、異議申し立てにつらぬかれているのであるが、それを沖縄駐在の米軍と高等弁務官がどのように無視し、どのように抑圧してきたかはわれわれの知るところである。しかしわれわれが十分にそれを知ってきたかといえば、・・・」
「・・・日本が沖縄に属する、というような発想には、肉体および精神の奥底を逆なでされる不愉快を感じるのが一般であるように見えるという観察には、いまも僕は固執する。もしかしたらそれが、日本人の政治的想像力における最悪の疾患をかたちづくっているところのものにつうじる鍵ではないであろうか?」
「それは一般に日本人が、あいまいな、欺瞞くさい言葉にたいして、科学的・実証的にくいさがることをしないタイプの精神であり、しかもそれでいて不安におそわれることもないのは、日本の「中華思想」的感覚が、その論理化されない暗部にとぐろをまいており、いやそのままあいまいにしておけばうまくゆくのだし、疑心暗鬼になることは「中華思想」の外にはじきだされた弱小者のやることだと、根拠もなく鼻であしらっているような内実があるからではあるまいか? なんとか自分だけはうまい牧草の、豊かに自生したところにみちびかれるように手をうってあるのだ、という小利巧な、しかしいったん甘い予想がひっくりかえればまったくお先まっ暗であるところの、奇妙にタカをくくった他人まかせの気質が作用しているからではあるまいか?」
「それはまったく逃れようのない蟻地獄の穴に陥没してゆく日本と日本人を、まともに正視するかわりに、様々な自己欺瞞をかさねてきた、自分への認識ということで・・・」
「・・・とにかく若い娘が戦場で死ぬということは痛ましいことだ、というかたちに一般化し、そうすることによって本土の日本人には誰にとってもかれの人間としての根源を刺してくるはずの沖縄の毒から身をまもり、安穏に涙を流すことができた。そして涙が乾けば、もう「沖縄問題は終った」と、・・・」
「・・・憲法の名を持ち出す時、自民党の政治家たちはその廉恥心において手が震えるということはないのか? これはハノイに旅したアメリカ人たるスーザン・ソンタグが発見してきた用語であるが、かれらに倫理的想像力 moral imagination はいささかもないのか?」
「かれは他人に嘘をついて瞞着するのみならず、自分自身にも嘘をつく。そのような恥を知らぬ嘘、自己欺瞞が、いかに数多くの、いわゆる「沖縄戦記」のたぐいをみたしていることか。(略)
慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。かれは、しだいに希薄化する記憶、歪められる記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいてかれは自己弁護の余地をこじあけるために、過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、1945年の事実に立って反論する声は、実際誰もが沖縄でのそのような罪を忘れたがっている本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。」
「・・・沖縄を軸とするこのような逆転の機会をねらいつづけてきたのは、あの渡嘉敷島の旧守備隊長にとどまらない。日本人の、実際に膨大な数の人間がまさにそうなのであり、何といってもこの前の戦争中のいろいろな出来事や父親の行動に責任がない、新世代の大群がそれにつきしたがおうとしているのである。(略) ・・・かれらからにせの罪悪感を取除く手続きのみをおこない、逆にかれらの倫理的想像力における真の罪悪感の種子の自生をうながす努力をしないこと、されは大規模な国家犯罪へとむかうあやまちの構造を、あらためてひとつずつ積みかさねていることではないのか。」
●参照
○沖縄「集団自決」問題(記事多数)