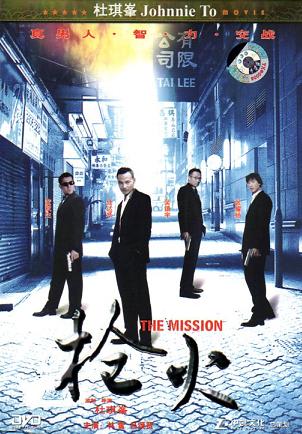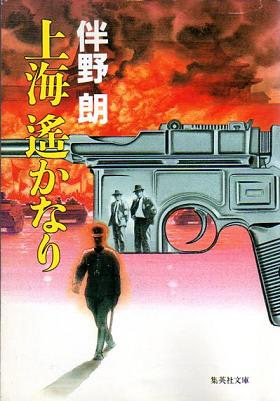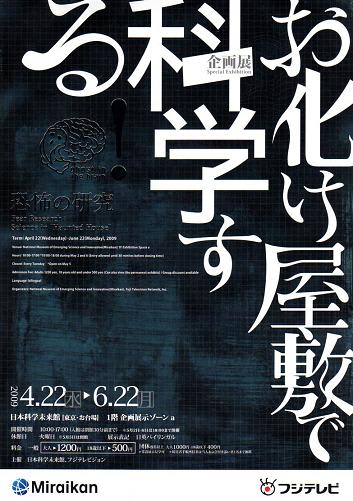いままで斜め読みしかしていなかった、天野礼子『ダムと日本』(岩波新書、2001年)をあらためて読んだ。ダムの歴史や問題を体系的に整理したものではなく、長良川などでの反対や欧米の脱ダムの動きなど、著者自身の活動に沿った書き方になっている。そして、これまで漁業組合をカネや圧力で取り込んできたこと、公共事業について妥当な判断ができなかったために社会党が凋落したことなどを読み取ることができる。

現在では、多くの場合、日本における新たなダム建設の目的とされてきた治水・利水のシナリオが現実と乖離していることや、それが政治や土建業界の利権と密着していることは、半ば常識として浸透している。しかし、実際には未だ、なかなか止まらない事業が存在している。千葉県の森田知事も、知事選の際には曖昧にしていた八ツ場ダムの推進を(やはりというべきか)表明している。「まとも」とは到底思えない根は深い。
本書の後半では、民主党の鳩山代表らを巡る動きが書かれている。そのなかで、「鳩山委員会」は、「緑のダム構想」として、森林での保水機能をダム代替として積極的に評価している。これは民主党のマニフェスト(2007年)(>> リンク)にも、「森林の公益的機能を守るための公共事業(みどりのダム事業)も積極的に進めます。」と残されている。今夏政権交代してからどのように懸案のダムが扱われていくのか注目したい。
ところで、最近は「工場萌え」のブームが「土木萌え」にまで拡がっている。萩原雅紀『ダム DAM』と『ダム2 DAMDAM』(メディアファクトリー)もそのひとつだ。それぞれ、何十ものダムの写真を並べ、審美眼的にのみ評価しているカタログ的な写真集である。


私も仕事上触れることが多いせいか、産業施設は好きであり興味もある。だからこれらの写真集も持っているし、顔がひとつひとつ異なるダムの姿に感心する。必要とされたダムがあることも知っている。しかし一方では、極めてアンバランスな無邪気さ、これにより犠牲になった動植物や海辺や川や人や社会について思いを馳せることは微塵もなさそうだ。
例えば岐阜県・木曽川にある丸山ダム。米国の資金と技術により完成した、日本最初の本格的な大規模ダムである。その米国では、「TVA思想」が破綻し、既に行き過ぎたダム開発を反省した政策を進めている。一方、『ダム2 DAMDAM』では、1983年の台風で下流が洪水を起こしたことを原因として、すぐ下流に新丸山ダムの建設が決定されたことを挙げ、「完成すれば丸山ダムは水没することになる。あまりに厳しいダム界の現実だ。」と述べている。必要性や受益・受苦のことには触れず、まったく別の世界にある鑑賞の対象としているわけだ。
また、アイヌ民族の聖地に強行建設された、北海道・沙流川の二風谷ダム。「激しい反対運動が起こるなどの経緯があったため、なるべく威圧感のないデザインを模索」とし、「その後アイヌの方々とは共存の道を歩み・・・」とまとめている。これは何だろうか。そういえば、最近の『生活と自治』(生活クラブ生協)には、もう土砂が溜まってしまった二風谷ダムの無惨な姿を紹介していた。
2つの視線は決して交錯することはない。