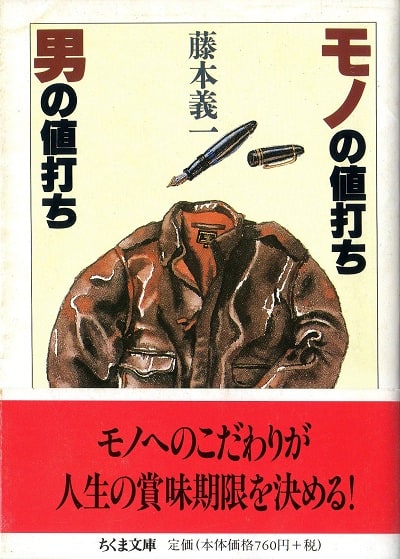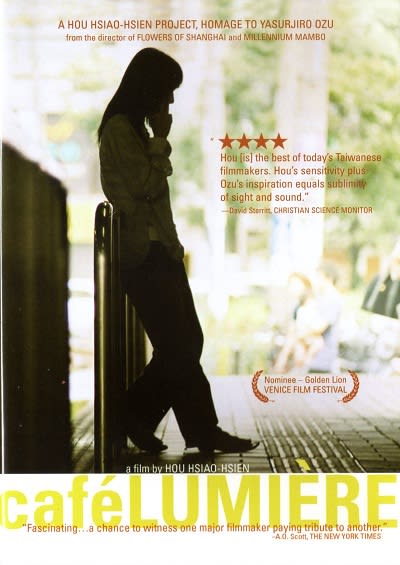ギル・エヴァンス『Plays the Music of Jimi Hendrix』(RCA、1974-75年)は、文字通り、ギル・エヴァンスのオーケストラによるジミ・ヘンドリックス曲集である。ジミが1970年に亡くなったため実現はしなかったが、共演の計画もあったのだという。スティングと共演したギルのことだから驚くにはあたらない。たとえば、デイヴィッド・マレイのグレイトフル・デッド集(>> リンク)などというものも、ギルのこのようなクロスボーダーの活動からつながる系譜にある。
勿論そのままジャズ作品として聴いても面白いのだが、折角なので、ジミの『Electric Ladyland』(1968年)とあわせて聴いてみる。「Crosstown Traffic」、「Voodoo Chile」、「Gypsy Eyes」、「1983」が、両方のアルバムで演奏されている。

どの演奏も、他のギルによる作品がそうであるように、要素がぎっちりと詰まっていてやけにカラフルでいて、同時に、やけにスマートなアレンジである。聴いていて耳が悦ぶとはこのことだ。
特に、「Voodoo Chile」におけるハワード・ジョンソンの執拗なチューバのソロ、「Angel」や「Little Wing」におけるデイヴィッド・サンボーンの鮮烈なアルトサックスのソロ、「Castle Made of Sand」におけるわれらがビリー・ハーパーのテナーサックスの粘っこいソロ、「Up from the Skies」におけるハンニバル・マーヴィン・ピーターソンのトランペットのソロなんかに耳を奪われる。
ハンニバルは「Crosstown Traffic」や「Little Wing」でヴォーカルも披露しているが、これは微妙だ(そういえば、90年代後半に「新宿DUG」で聴いたときにも歌っていた)。
一方のジミヘンはというと、怪しく燃える火のようで、これは文句なく格好いい。ごちゃごちゃ言わないで聴く。

●参照
○ビリー・ハーパーの新作『Blueprints of Jazz』、チャールズ・トリヴァーのビッグバンド、ギル・エヴァンス『Svengali』
○ビリー・ハーパーの映像
○デイヴィッド・マレイのグレイトフル・デッド集