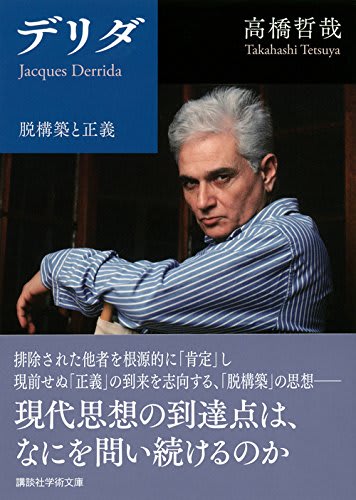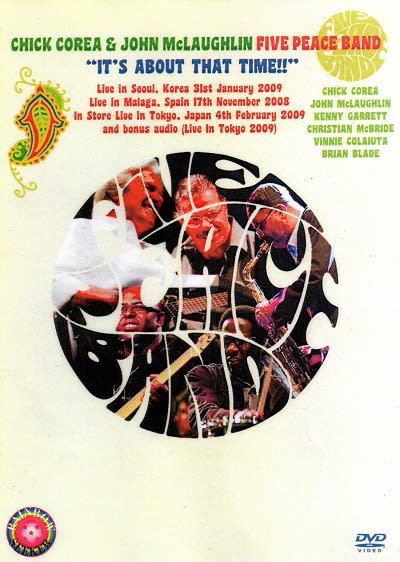新藤健一・編著『沖縄「辺野古の海」は、いま 新しい巨大米軍基地ができる』(七つ森書館、2015年)を読む。

前半は、辺野古を中心とした写真群。高江、白保、泡瀬干潟の写真も収められている。見たことのある写真も初めての写真もある。
辺野古の海には、少し潜ると、アオサンゴの群生など非常に多くの貴重な自然が多い。ジュゴンだけではないのである。もちろんこの論理には、美しく貴重な自然環境・生物でなければ破壊してもよいのかという陥穽が含まれているのだが、素晴らしいものは素晴らしい。吃驚し、魅入らされるばかりだ。
ところが、沖縄防衛局は埋め立てを強行しつつあり、こともあろうに、対象地域外で巨大なコンクリートブロックを沈め、サンゴを破壊している。また、海上保安庁は反対する市民をむきだしの暴力で排除している。写真を視ることで、その暴力性が迫ってくる。
そして素晴らしいやんばるの森。この多くは、米軍のジャングル戦闘訓練センターが占めており、ベトナム戦争時代から密林でのサバイバル訓練がなされている。すなわち、沖縄が米軍に基地を提供させられ、海外で数多くの市民が殺され、それを不可視化することで、日本が存続してきた。非常に歪んだ構造であり、可視化すれば、その構造はその都度揺らいでくる。
そして後半の解説にあるように、仮に一万歩譲って米軍の軍事行動を前提条件としても(譲るのは誰か?)、米軍基地を沖縄に置く意味は、軍事戦略としても、経済的にも、実に稀薄なものとなっている。しかし、辺野古の新基地(移設という言葉を使うこと自体が欺瞞である)は、米軍により50年前からずっと狙われてきたものであり、ジャングル戦闘訓練センターも含め、東西冷戦時代の日米合作がいまや亡霊のようになって沖縄を徘徊し続けているものだと言うことができる。
●参照
二度目の辺野古(2010年)
2010年8月、高江
泡瀬干潟(2010年)
高江・辺野古訪問記(2) 辺野古、ジュゴンの見える丘(2007年)
高江・辺野古訪問記(1) 高江(2007年)