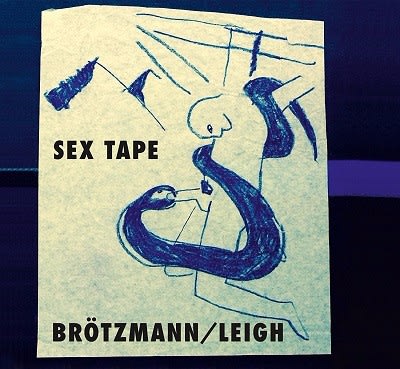さて今日はじめてマリア・シュナイダー・オーケストラを観に行く前に、気持ちを盛り上げようと2枚ほど聴く。
■ 『Allegresse』(Artist Share、2000年)

Maria Schneider (conductor)
Tim Ries (ss, cl, fl, alto fl)
Charles Pillow (as, ss, cl, fl, piccolo, oboe, English horn)
Rich Perry (ts, fl)
Rick Margitza (ts, ss, fl)
Scott Robinson (bs, bass sax, cl, bcl, fl, alto fl)
Tony Kadleck (tp, piccoro tp, flh)
Greg Gisbert (tp, flh)
Laurie Frink (tp, flh)
Ingrid Jensen (tp, flh)
Dave Ballou (tp, flh)
Keith O'Quinn (tb)
Rock Ciccarone (tb)
Larry Farrell (tb)
George Flynn (bass-tb)
Ben Monder (g)
Frank Kimbrough (p)
Tony Scherr (b)
Tim Horner (ds)
Jeff Ballard (perc)
細やかなアレンジで次々に楽器の音が重ね合わされてゆく。それなのにまったくヘヴィではない不思議さだ。油絵のように塗りこめていく感覚ではなく、透過性のある絵の具で色がどんどん複雑になりセンサーが悦ぶ感覚。ギターのベン・モンダーの音が効果的に使われているからこその柔らかさでもあるのかな。
ソロイストはグレッグ・ギルバート、リック・マーギッツァ、フランク・キンブロウ、イングリッド・ジェンセン、リッチ・ペリー、ティム・リース、チャールス・ピロウ、ベン・モンダー、スコット・ロビンソン。確かにジェンセンのトランペットなんてパワーで攻めず実に柔らかいし、ここにいることがしっくりくる。またソロイストとして書かれていないが、ジェフ・バラードのパーカッションも気持ちが良い。
■ 『Concert in the Garden』(Artist Share、2001-04年)

Maria Schneider (conductor)
Charles Pillow (as, ss, cl, fl, alto fl, oboe, English horn)
Tim Ries (as, ss, cl, fl, alto fl, bass fl)
Rich Perry (ts, fl)
Donny McCaslin (ts, ss, cl, fl)
Scott Robinson (bs, fl, cl, bcl, contrabass cl)
Tony Kadleck (tp, flh)
Greg Gisbert (tp, flh)
Laurie Frink (tp, flh)
Ingrid Jensen (tp, flh)
Keith O'Quinn (tb)
Rock Ciccarone (tb)
Larry Farrell (tb)
George Flynn (bass tb, contrabass tb)
Ben Monder (g)
Frank Kimbrough (p)
Jay Anderson (b)
Clarence Penn (ds)
Jeff Ballard (cajón, quinto cajón)
Gonzalo Grau (cajón)
Gary Versace (accordion)
Luciana Souza (voice, pandeiro)
Pete McGuinness (tb)
Andy Middleton (ts)
これはまた随分と雰囲気が異なる。タイトル通り、まるで緑に囲まれた中庭で音楽を聴くようなオープンで爽やかな感覚がある。
ここには、ゲイリー・ヴェルサーチのアコーディオンやルシアーナ・ソウザの囁くようなヴォイスが貢献している。また、全般にベン・モンダーのギターがサウンドを柔らかくし、フランク・キンブロウのピアノが多数埋め込まれたスワロフスキーのように光を取り込み屈折反射させている。
ソロイストは、ベン・モンダー、フランク・キンブロウ、ゲイリー・ヴェルサーチ、リッチ・ペリー、イングリッド・ジェンセン、チャールス・ピロウ、ラリー・ファレル、ダニー・マッキャスリン、グレッグ・ギルバート。マッキャスリンはハードに攻めるかと思いきや、丹念に音を選んでいてこれもまた良い感じ。
●マリア・シュナイダー
マリア・シュナイダー『The Thompson Fields』(2014年)