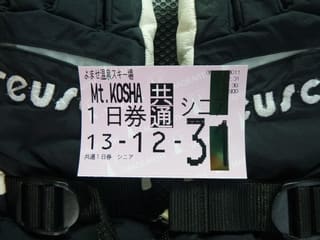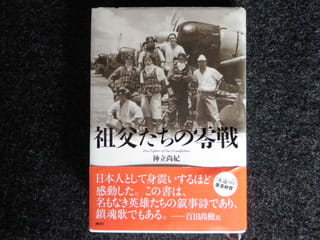■初釣りは舞鶴から■
いよいよ初釣り。今年も「メダイ食いたさ。」から、舞鶴沖でスタートした。
お世話になる釣り船は、舞鶴地区では「ボクの信頼のおける船頭さん」の1人である船長が操る、滝ヶ浦遊船所属の日本海41だ。そして期待を込めて、舞鶴へと向かったのだが…。

■空き家続き■
出船が不能、または、危ぶまれる天候続きだったのが、奇跡的に落ち着いた日曜の朝、予定通りの出船となった。湾口を出ても波高は1.5mほどであり、釣りに支障が出る程ではないことにホッとしつつ、日本海41は更に沖へと進んでいった。
今回は、不調の白石グリは始めから避け、冠島方面へと向かうことになった。そして、その道中の天然&人工漁礁で魚探の反応を見ながら「ここぞ!」というポイントを見つけ出し、そこで竿出しして攻めるという作戦だった。
しか~し!である。ほとんどのポイントで魚影が全く無いのである。
移動すること5~6回目の深場で、何やら薄い影を発見するのだが、投入した天秤ズボ仕掛は、そこでは不発。続いて冠島を挟んで東から西へ移動をしたのだが、その方面でもほとんどが空き家という始末だった。
■低活性■
移動することさらに数回目、ようやく魚影を発見したのだが、ここも、モヤモヤとした感じで頼りないモノだった。それでもないよりはマシと、投入を開始する。ここも深場の水深100ラインなので、ここでも天秤ズボ仕掛を使用した。
仕掛けを打ち返すこと数回目、「竿先に変化があったような気がした」程度のアタリを拾って、30cmほどのアジをゲットする。しかし、食ってウマイ魚であっても、全くファイトをしてくれないため、ボクにとっては釣りの対象魚ではなく、あまり歓迎できない。
続いて同じようなアタリが竿先を揺すった。そのままアジを釣っても仕方がないため、「サイズが大きすぎるような気もするが、そのままハリに掛かった状態にして、これを食う魚を狙ってやれ。」と思い、そのままの状態で海底まで仕掛けを落とし込んでみることにした。
予想通りと言うべきか、数分待ったがアタリはなかった。仕方なく仕掛けを回収してみると…。てっきりアジだと思っていた、ハリ掛かりした魚は、何と40cm弱のマダイだったのだ。

普通、小型と言っても、このクラスのマダイであれば、やり取りでの引きはともかくとして、アタリが出た時点で竿を曲げ込むほどの走りがあるのだが、食っても全く走らず、いわゆる居食いをしたためにこうなったのだろう。ということは、かなりの低活性だということになる。
1月は、水温が下降し続ける時期であるのだが、それでも潮流によっては、下げ幅が少なく安定していたり、逆に小幅で上昇していることもあるのだが、実はこの日、その潮流までもが思わしくない状況だったのだ。と言うのも、若狭湾では西から来る=対馬暖流の影響を受ける潮流が本命とされているのだが、この日は福井県側の若狭湾奥からやって来る潮流だったのだ。そのため、下げ幅の大きい水温低下が起こっていたものと思われる。マダイにしてみれば寒くて動けずジッとしているところに流れてきたエサに、つい口を使ってしまっただけのようだ。その様子から、ここまでの各魚礁で魚探に写る反応がほとんどないことにも頷けてしまった。
「アタリがある以上、少し粘った方がイイ」という判断から、同じポイントで時間を掛けて攻めてみたが、たまに上がってくるのはアジ程度で、そのうちにだんだんとエサ取りの動きが目立つようになってきた。
「エサ取りが活発になるということは、水温が上がったのか?。」と肯定的に捉えてみたが、水深の半分を切っても取られっぱなしになり、お手上げとなった。
そして、ついに、「どうにもならい」という判断から、大移動を行うことになった。
■そしてフカセ釣り■
残り時間は3時間程度となっていたし、こちらサイドの「天秤ズボはもうウンザリ」という思いが伝わって、船長は大小ある冠島の水道部分に船を掛け、フカセ釣りのポジションを取ってくれた。
今年初めてのフカセ釣りに期待を込めて投入を開始するが、ここでも逆潮のままであるため、イヤな予感が漂っていたことは否めなかった。
最初に竿を曲げたのは同行していた兄だった。しかし、それは大サバとハマチのダブルでガックリ。
続いてボクのリールもアタリらしき動きを始めたのだが、それはアラームをならしつつ急速回転するようなモノではなく、ヌルヌルッといった感じで「やや速くなったか?」という程度の動きだった。そしてその結果は「やはり」と言うべきか、ハマチだった。
警戒心の薄いハマチクラスですらこんなアタリでは、期待できる状況ではないことは確かだったが、船長の「夕方に一発が来るかも?」という言葉に励まされて、その後も更に投入を続けていた。
そして、気付けば日は傾き始め、赤く色づきつつある頃になって、ようやく、この日初めてアラームを鳴らすアタリをリールが捉えた。
疾走する様子からしてハマチクラスとは違う動きをしているが、大きさはさほどではなさそうだった。しかし、逃せば後がない状況だけに、慎重にやり取りを開始する。
じんわりと力を掛けて、ゆっくりと船縁まで引き寄せると正体が判明する。上バリにハマチがぶら下がり、下バリには待望のヒラマサが掛かっていたが、2本とも無事にゲットに成功し、ホッと胸を撫で下ろすことができた。

貴重な一匹をゲットした後は少しの期待が芽生えたが、続く魚はハマチのみ。やがてエサが全く取られなくなったのと時を同じくして、日没を迎え、尻すぼみのままで納竿となった。

■挑戦は続く■
舞鶴沖でスタートした今年の釣り。かろうじて中型に足を突っ込んだばかりのサイズのヒラマサを釣ったものの、思うような展開ではなかった。
釣行後に調べてみると、欲しかったメダイは、この釣行前に若狭湾では最も沖合にある浦島グリで一船で三桁前後の釣果があったし、釣行後には冠島周辺でもある程度の数が上がるようになっている。その狭間に、タイミングを合わせたかのように釣行するのは「いつもながらのパターン」としか言いようがないのだが、様々な状況から予想するに、ここ2年程続いた不漁気配はなさそうなことは幸いだ。今後は鍋の準備をして待つ家族のために、目の色を変えて狙ってゆくつもりだ。
いよいよ初釣り。今年も「メダイ食いたさ。」から、舞鶴沖でスタートした。
お世話になる釣り船は、舞鶴地区では「ボクの信頼のおける船頭さん」の1人である船長が操る、滝ヶ浦遊船所属の日本海41だ。そして期待を込めて、舞鶴へと向かったのだが…。

●出船前の日本海41●
■空き家続き■
出船が不能、または、危ぶまれる天候続きだったのが、奇跡的に落ち着いた日曜の朝、予定通りの出船となった。湾口を出ても波高は1.5mほどであり、釣りに支障が出る程ではないことにホッとしつつ、日本海41は更に沖へと進んでいった。
今回は、不調の白石グリは始めから避け、冠島方面へと向かうことになった。そして、その道中の天然&人工漁礁で魚探の反応を見ながら「ここぞ!」というポイントを見つけ出し、そこで竿出しして攻めるという作戦だった。
しか~し!である。ほとんどのポイントで魚影が全く無いのである。
移動すること5~6回目の深場で、何やら薄い影を発見するのだが、投入した天秤ズボ仕掛は、そこでは不発。続いて冠島を挟んで東から西へ移動をしたのだが、その方面でもほとんどが空き家という始末だった。
■低活性■
移動することさらに数回目、ようやく魚影を発見したのだが、ここも、モヤモヤとした感じで頼りないモノだった。それでもないよりはマシと、投入を開始する。ここも深場の水深100ラインなので、ここでも天秤ズボ仕掛を使用した。
仕掛けを打ち返すこと数回目、「竿先に変化があったような気がした」程度のアタリを拾って、30cmほどのアジをゲットする。しかし、食ってウマイ魚であっても、全くファイトをしてくれないため、ボクにとっては釣りの対象魚ではなく、あまり歓迎できない。
続いて同じようなアタリが竿先を揺すった。そのままアジを釣っても仕方がないため、「サイズが大きすぎるような気もするが、そのままハリに掛かった状態にして、これを食う魚を狙ってやれ。」と思い、そのままの状態で海底まで仕掛けを落とし込んでみることにした。
予想通りと言うべきか、数分待ったがアタリはなかった。仕方なく仕掛けを回収してみると…。てっきりアジだと思っていた、ハリ掛かりした魚は、何と40cm弱のマダイだったのだ。

●ヤル気のないマダイ●
普通、小型と言っても、このクラスのマダイであれば、やり取りでの引きはともかくとして、アタリが出た時点で竿を曲げ込むほどの走りがあるのだが、食っても全く走らず、いわゆる居食いをしたためにこうなったのだろう。ということは、かなりの低活性だということになる。
1月は、水温が下降し続ける時期であるのだが、それでも潮流によっては、下げ幅が少なく安定していたり、逆に小幅で上昇していることもあるのだが、実はこの日、その潮流までもが思わしくない状況だったのだ。と言うのも、若狭湾では西から来る=対馬暖流の影響を受ける潮流が本命とされているのだが、この日は福井県側の若狭湾奥からやって来る潮流だったのだ。そのため、下げ幅の大きい水温低下が起こっていたものと思われる。マダイにしてみれば寒くて動けずジッとしているところに流れてきたエサに、つい口を使ってしまっただけのようだ。その様子から、ここまでの各魚礁で魚探に写る反応がほとんどないことにも頷けてしまった。
「アタリがある以上、少し粘った方がイイ」という判断から、同じポイントで時間を掛けて攻めてみたが、たまに上がってくるのはアジ程度で、そのうちにだんだんとエサ取りの動きが目立つようになってきた。
「エサ取りが活発になるということは、水温が上がったのか?。」と肯定的に捉えてみたが、水深の半分を切っても取られっぱなしになり、お手上げとなった。
そして、ついに、「どうにもならい」という判断から、大移動を行うことになった。
■そしてフカセ釣り■
残り時間は3時間程度となっていたし、こちらサイドの「天秤ズボはもうウンザリ」という思いが伝わって、船長は大小ある冠島の水道部分に船を掛け、フカセ釣りのポジションを取ってくれた。
今年初めてのフカセ釣りに期待を込めて投入を開始するが、ここでも逆潮のままであるため、イヤな予感が漂っていたことは否めなかった。
最初に竿を曲げたのは同行していた兄だった。しかし、それは大サバとハマチのダブルでガックリ。
続いてボクのリールもアタリらしき動きを始めたのだが、それはアラームをならしつつ急速回転するようなモノではなく、ヌルヌルッといった感じで「やや速くなったか?」という程度の動きだった。そしてその結果は「やはり」と言うべきか、ハマチだった。
警戒心の薄いハマチクラスですらこんなアタリでは、期待できる状況ではないことは確かだったが、船長の「夕方に一発が来るかも?」という言葉に励まされて、その後も更に投入を続けていた。
そして、気付けば日は傾き始め、赤く色づきつつある頃になって、ようやく、この日初めてアラームを鳴らすアタリをリールが捉えた。
疾走する様子からしてハマチクラスとは違う動きをしているが、大きさはさほどではなさそうだった。しかし、逃せば後がない状況だけに、慎重にやり取りを開始する。
じんわりと力を掛けて、ゆっくりと船縁まで引き寄せると正体が判明する。上バリにハマチがぶら下がり、下バリには待望のヒラマサが掛かっていたが、2本とも無事にゲットに成功し、ホッと胸を撫で下ろすことができた。

●62cmのヒラマサ●
貴重な一匹をゲットした後は少しの期待が芽生えたが、続く魚はハマチのみ。やがてエサが全く取られなくなったのと時を同じくして、日没を迎え、尻すぼみのままで納竿となった。

●最後もハマチ●
■挑戦は続く■
舞鶴沖でスタートした今年の釣り。かろうじて中型に足を突っ込んだばかりのサイズのヒラマサを釣ったものの、思うような展開ではなかった。
釣行後に調べてみると、欲しかったメダイは、この釣行前に若狭湾では最も沖合にある浦島グリで一船で三桁前後の釣果があったし、釣行後には冠島周辺でもある程度の数が上がるようになっている。その狭間に、タイミングを合わせたかのように釣行するのは「いつもながらのパターン」としか言いようがないのだが、様々な状況から予想するに、ここ2年程続いた不漁気配はなさそうなことは幸いだ。今後は鍋の準備をして待つ家族のために、目の色を変えて狙ってゆくつもりだ。