■日本陸軍の人々■
日頃から近代史に興味のあるボクは、大東亜戦争(太平洋戦争)関連の書物に触れることが多い。しかし、それらは海軍軍人や海軍の戦史に触れたモノ、特に零戦乗りを代表とする、海軍パイロット関連の本が多く、「他にはないのか?」と、実際にAMAZON等で調べてみても、発刊されているモノの多くが、その類だということに気付かされる。
これは、最終的にはコテンパンにやられた負け戦の中であっても、初期という限定的な期間ながら、零戦という兵器とそれに乗ったパイロットが連合国に対して圧倒的な力を示したことが、「我々日本人の誇り」へとつながる琴線に触れるからだろう。しかし、対する陸軍にはどうも陰惨なイメージが強く、「開戦は陸軍が主導した。」という説による、ある種の後ろめたさがあるから発刊数が少ないのだと個人的には思っている。
しかし、実際には海軍であっても艦隊勤務の現場では鉄拳制裁は日常茶飯事であったし、現在で言うところの省益を優先し、指導部やその周囲では開戦に賛成した人達も多かったそうである。逆に陸軍の中にも我々が誇れる事柄があり、人物が居るハズである。
そんな中、とある本に出会った。それが門田隆将著「この命、義に捧ぐ」という本だった。
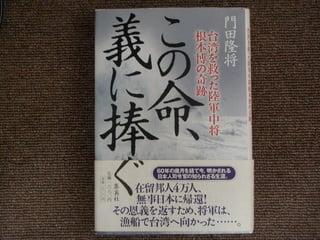
■根本博中将■
この本は、旧日本陸軍中将であるところの根本博中将を追った内容で構成されている。この中将は、駐蒙軍司令官として内蒙古北支方面の指揮にあたっていた際に昭和20年8月15日の終戦を迎えた。
その6日前にあたる8月9日、「日ソ中立条約」の有効期限が半年以上も残る中で突如ソ連が宣戦布告し、隣の満州と、この内蒙古北支方面、樺太等に対しての侵攻が始まった。その際、特に満州国内ではソ連軍その他による、一般人に対しての略奪、強姦、虐待といった不法かつ残虐な行為が起こったが、頼りの関東軍=この一帯を守備し、住民を保護するハズであった、日本陸軍の方面軍に捨て去られたとがこの悲劇の要因として語られることが多い。少し前のNHKドラマ「開拓者たち」でもその描写があったが、これには、南方の対米戦に人員をとられたために兵力が激減し、マトモな反撃できないので仕方なく防衛線を後退させたり拠点にこもったりしたから、そのような結果になったとする説もあるのだが…。
悲劇は8月15日の終戦日を迎えても続く。満州国内の関東軍はソ連の要求する武装解除に素直に応じたため、全くの無抵抗となり、以後同国内に取り残された日本人の多くが、言わば蹂躙されるがままの状態となった。特に後の「シベリア抑留」の被害者は60万人とも言われるが、多くの人々がこのような「奴隷扱い」を受けた他、今も続く残留孤児問題のきっかけは、「抗う術がなかった」ところにもあったようだ。
対して、根本中将の指揮する内蒙古北支方面ではソ連側は信用がおけないとして、ソ連はもちろんのこと、度重なる日本陸軍上層部からの命令にも応じず、「それに対する責任の全ては自身がとる」として、8月15日以降も武装解除には応じなかった。そして同方面に残る在留邦人4万人が無事日本に向けて帰国できる位置へと到着するまで徹底抗戦し、退路である線路の守備はおろか、食料等の物資を待避する一般邦人優先で各駅に配置するなどの計らいも同時に行い、守り抜いたのだ。
しかも、その最中に国民政府(蒋介石側)と交渉し、一般邦人への配慮を要求し、受け入れてもらうことで日本への帰国の目処をつけ、最終的には一般邦人の安全が確保できたとして、自身の軍は国民政府に対して降伏し、そこで武装解除を受けさせたのだ。
■国共内戦のさなか■
終戦後、無事日本に帰国した根本中将だったが、中国国内における毛沢東軍(共産党軍)と蒋介石軍(国民党軍)のいわゆる国共内戦が最終局面に入り、蒋介石軍が台湾海峡付近まで撤退して「後がない」状態まで追い込まれた時に、密使の訪問を受ける。そして、根本中将は終戦時の日本人に対して徳をもって対処してくれた蒋介石とその軍に、義をもってお返ししようと、宮崎県から台湾へ、穴が開いて浸水するような状態の、わずか30トンにも満たないボロ船に乗って密航を決意するのだが…。
以降は本を読んで欲しいが、この根本中将を始め、白団(ぱいだん)と呼ばれていた顧問団の人々ように、国民党の独立保持のために命を懸けた人達がこの時期には何人も居る。そういった人々は根本中将のように、自身が受けた恩義のために、あるいは大東亜戦争中に死んでいった戦友や部下たちに対して、生き残ってしまった自分の”死に場所”を求めて向かったのかも知れない。
■日台の架け橋■
これまで台湾では「八田ダム」と通称で呼ばれる、当時としてはアジア一のダムと灌漑用水路網を築いて台湾最大の穀倉地を造った八田與一(はった・よいち)が、現地で感謝され、毎年追悼式が行われているということは聞いたことがあるが、それ以外にも根本中将達のように、台湾政府の創始から発展に関わり、尽力した人々がたくさん居ることに、この本で気付かされた。
しかし、そんなことが一般には語られず、わざわざ調べなくては判らないにはいくつかの理由がある。
台湾国民政府初期の指導者である蒋介石は、満州事変に始まる日本との15年戦争時には中国大陸における排日運動と対日戦争を強硬に行ったが、その政治的な表の顔の裏側に、彼自身に日本留学経験があることからでも判るように、日本に対する個人的な好意感がどこかにあったように思われる。だからこそ助力を受け入れたのだと思う。だが、台湾に国民政府を移し、腰を据えた後は、台湾に元から住み、日本統治下で暮らしていた本省人に対する外省人の支配力を増すために日本的影響を排除する道を選んだ。その結果、日本人の助力は歴史から消される運命になったのだろう。
そして、戦後の日本では、過去に対する反省もなく表舞台に復活したとされる人々の「口の大きさ」とは逆に、こういった助力をした人の多くが、その責任感の強さと敗戦に対する自戒の念から声を発することを良しとしなかった。もし語ったとしても、死の直前に「あなたが真実を語らなければ…。」と説得された末に、ようやく口を開いた程度の人が多い。だから、こういった人々の話に関しては我々世代以降の人々が発掘しなければ、なかなか世には出てこないのだろう。
■信頼関係■
昨年、東北で震災が起こった後に各国からの支援があった。中でも台湾からは200億円を越える義援金が届けられ、その額は世界最大だという。この背景にはアニメが有名だとか、ファッションがイケてるだとか、先端技術がすごいとか、あるいはビジネスパ-トナーだとか、台湾国民自らが震災にあった際に援助を受けたことに対する返礼という、今の日本に対しての好感に由来する一面があるのかも知れないが、実のところ深層心理のその中にある、発展や建国に助力した人達の姿と、その人達が得た信頼という無形の財産の影響も大きいのだと思う。
ややもすると我々日本人は「友好」という、言葉に騙されやすく、その名の下、他国に利用されてしまうことが多いように思える。勿論、国家という分け隔てがある以上、その利害によって動くことの方が多いのは当然の話だが、もし国同士の友好という言葉が実在するのであれば、それに最も近いのが日台の関係なのだろうと、歴史をたどってゆけば、つくづくと感じることができる。
しかしながら今春、震災1周年追悼式に来訪した台湾代表に対して、我が国政府の当局者は指名献花を許さず、2階席に座らせるという、失礼極まりない扱いをしたそうだが、このような行為は、この国に暮らす者として恥ずかしさの極みに思う。
我々日本人が培った心の奥には「礼」とい部分があったハズだ。これを尽くすことが人間間のクッションの役目を果たし、あるいはそういったことを基礎にして築かれた精神がモノ作りに反映されて、きめ細やかな気遣いに溢れた製品となって世界に受け入れられてきたのだ。
礼に報いる心を忘れるとどうなるのか?…。恐らく信頼を失うだろう。我々が根本中将達のような先人から受け継いだ友好の基礎にある”信頼”をなくせば、次の世代に引き継ぐ”友好”が揺らぐ。こんなことがあってはならないと思う。
日頃から近代史に興味のあるボクは、大東亜戦争(太平洋戦争)関連の書物に触れることが多い。しかし、それらは海軍軍人や海軍の戦史に触れたモノ、特に零戦乗りを代表とする、海軍パイロット関連の本が多く、「他にはないのか?」と、実際にAMAZON等で調べてみても、発刊されているモノの多くが、その類だということに気付かされる。
これは、最終的にはコテンパンにやられた負け戦の中であっても、初期という限定的な期間ながら、零戦という兵器とそれに乗ったパイロットが連合国に対して圧倒的な力を示したことが、「我々日本人の誇り」へとつながる琴線に触れるからだろう。しかし、対する陸軍にはどうも陰惨なイメージが強く、「開戦は陸軍が主導した。」という説による、ある種の後ろめたさがあるから発刊数が少ないのだと個人的には思っている。
しかし、実際には海軍であっても艦隊勤務の現場では鉄拳制裁は日常茶飯事であったし、現在で言うところの省益を優先し、指導部やその周囲では開戦に賛成した人達も多かったそうである。逆に陸軍の中にも我々が誇れる事柄があり、人物が居るハズである。
そんな中、とある本に出会った。それが門田隆将著「この命、義に捧ぐ」という本だった。
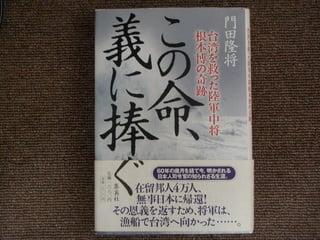
●この命義に捧ぐ●
■根本博中将■
この本は、旧日本陸軍中将であるところの根本博中将を追った内容で構成されている。この中将は、駐蒙軍司令官として内蒙古北支方面の指揮にあたっていた際に昭和20年8月15日の終戦を迎えた。
その6日前にあたる8月9日、「日ソ中立条約」の有効期限が半年以上も残る中で突如ソ連が宣戦布告し、隣の満州と、この内蒙古北支方面、樺太等に対しての侵攻が始まった。その際、特に満州国内ではソ連軍その他による、一般人に対しての略奪、強姦、虐待といった不法かつ残虐な行為が起こったが、頼りの関東軍=この一帯を守備し、住民を保護するハズであった、日本陸軍の方面軍に捨て去られたとがこの悲劇の要因として語られることが多い。少し前のNHKドラマ「開拓者たち」でもその描写があったが、これには、南方の対米戦に人員をとられたために兵力が激減し、マトモな反撃できないので仕方なく防衛線を後退させたり拠点にこもったりしたから、そのような結果になったとする説もあるのだが…。
悲劇は8月15日の終戦日を迎えても続く。満州国内の関東軍はソ連の要求する武装解除に素直に応じたため、全くの無抵抗となり、以後同国内に取り残された日本人の多くが、言わば蹂躙されるがままの状態となった。特に後の「シベリア抑留」の被害者は60万人とも言われるが、多くの人々がこのような「奴隷扱い」を受けた他、今も続く残留孤児問題のきっかけは、「抗う術がなかった」ところにもあったようだ。
対して、根本中将の指揮する内蒙古北支方面ではソ連側は信用がおけないとして、ソ連はもちろんのこと、度重なる日本陸軍上層部からの命令にも応じず、「それに対する責任の全ては自身がとる」として、8月15日以降も武装解除には応じなかった。そして同方面に残る在留邦人4万人が無事日本に向けて帰国できる位置へと到着するまで徹底抗戦し、退路である線路の守備はおろか、食料等の物資を待避する一般邦人優先で各駅に配置するなどの計らいも同時に行い、守り抜いたのだ。
しかも、その最中に国民政府(蒋介石側)と交渉し、一般邦人への配慮を要求し、受け入れてもらうことで日本への帰国の目処をつけ、最終的には一般邦人の安全が確保できたとして、自身の軍は国民政府に対して降伏し、そこで武装解除を受けさせたのだ。
■国共内戦のさなか■
終戦後、無事日本に帰国した根本中将だったが、中国国内における毛沢東軍(共産党軍)と蒋介石軍(国民党軍)のいわゆる国共内戦が最終局面に入り、蒋介石軍が台湾海峡付近まで撤退して「後がない」状態まで追い込まれた時に、密使の訪問を受ける。そして、根本中将は終戦時の日本人に対して徳をもって対処してくれた蒋介石とその軍に、義をもってお返ししようと、宮崎県から台湾へ、穴が開いて浸水するような状態の、わずか30トンにも満たないボロ船に乗って密航を決意するのだが…。
以降は本を読んで欲しいが、この根本中将を始め、白団(ぱいだん)と呼ばれていた顧問団の人々ように、国民党の独立保持のために命を懸けた人達がこの時期には何人も居る。そういった人々は根本中将のように、自身が受けた恩義のために、あるいは大東亜戦争中に死んでいった戦友や部下たちに対して、生き残ってしまった自分の”死に場所”を求めて向かったのかも知れない。
■日台の架け橋■
これまで台湾では「八田ダム」と通称で呼ばれる、当時としてはアジア一のダムと灌漑用水路網を築いて台湾最大の穀倉地を造った八田與一(はった・よいち)が、現地で感謝され、毎年追悼式が行われているということは聞いたことがあるが、それ以外にも根本中将達のように、台湾政府の創始から発展に関わり、尽力した人々がたくさん居ることに、この本で気付かされた。
しかし、そんなことが一般には語られず、わざわざ調べなくては判らないにはいくつかの理由がある。
台湾国民政府初期の指導者である蒋介石は、満州事変に始まる日本との15年戦争時には中国大陸における排日運動と対日戦争を強硬に行ったが、その政治的な表の顔の裏側に、彼自身に日本留学経験があることからでも判るように、日本に対する個人的な好意感がどこかにあったように思われる。だからこそ助力を受け入れたのだと思う。だが、台湾に国民政府を移し、腰を据えた後は、台湾に元から住み、日本統治下で暮らしていた本省人に対する外省人の支配力を増すために日本的影響を排除する道を選んだ。その結果、日本人の助力は歴史から消される運命になったのだろう。
そして、戦後の日本では、過去に対する反省もなく表舞台に復活したとされる人々の「口の大きさ」とは逆に、こういった助力をした人の多くが、その責任感の強さと敗戦に対する自戒の念から声を発することを良しとしなかった。もし語ったとしても、死の直前に「あなたが真実を語らなければ…。」と説得された末に、ようやく口を開いた程度の人が多い。だから、こういった人々の話に関しては我々世代以降の人々が発掘しなければ、なかなか世には出てこないのだろう。
■信頼関係■
昨年、東北で震災が起こった後に各国からの支援があった。中でも台湾からは200億円を越える義援金が届けられ、その額は世界最大だという。この背景にはアニメが有名だとか、ファッションがイケてるだとか、先端技術がすごいとか、あるいはビジネスパ-トナーだとか、台湾国民自らが震災にあった際に援助を受けたことに対する返礼という、今の日本に対しての好感に由来する一面があるのかも知れないが、実のところ深層心理のその中にある、発展や建国に助力した人達の姿と、その人達が得た信頼という無形の財産の影響も大きいのだと思う。
ややもすると我々日本人は「友好」という、言葉に騙されやすく、その名の下、他国に利用されてしまうことが多いように思える。勿論、国家という分け隔てがある以上、その利害によって動くことの方が多いのは当然の話だが、もし国同士の友好という言葉が実在するのであれば、それに最も近いのが日台の関係なのだろうと、歴史をたどってゆけば、つくづくと感じることができる。
しかしながら今春、震災1周年追悼式に来訪した台湾代表に対して、我が国政府の当局者は指名献花を許さず、2階席に座らせるという、失礼極まりない扱いをしたそうだが、このような行為は、この国に暮らす者として恥ずかしさの極みに思う。
我々日本人が培った心の奥には「礼」とい部分があったハズだ。これを尽くすことが人間間のクッションの役目を果たし、あるいはそういったことを基礎にして築かれた精神がモノ作りに反映されて、きめ細やかな気遣いに溢れた製品となって世界に受け入れられてきたのだ。
礼に報いる心を忘れるとどうなるのか?…。恐らく信頼を失うだろう。我々が根本中将達のような先人から受け継いだ友好の基礎にある”信頼”をなくせば、次の世代に引き継ぐ”友好”が揺らぐ。こんなことがあってはならないと思う。






































