都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
いな‐ずま【稲妻・電】 ヅマ
(「稲の夫ツマ」の意。稲の結実の時期に多いところから、これによって稲が実るとされた)
空中電気の放電する時にひらめく火花。多く屈折して見える。また、それが空に反映したもの。動作の敏速なさま、また瞬時的な速さのたとえに用いる。いなびか
り。いなたま。いなつるび。 秋 。古今和歌集恋「秋の田の穂の上を照らす―の光の間にも」
広辞苑
 『広辞苑』で調べると、「いなずま」となっています。「妻」ですから、「いなづま」のはずなのですが、何故でしょう。
『広辞苑』で調べると、「いなずま」となっています。「妻」ですから、「いなづま」のはずなのですが、何故でしょう。
空中電気の放電するときに閃く光が「いなずま」です。今は、「稲妻」と書きますが、本来は、「稲夫」と書いたのです。
ではどうして、稲の夫なのでしょう。
古 代は、稲の稔を女性の妊娠と考え、稲は女性とされていました。そして、稲が実る時期に雷光が多く、この雷光が毎夜、稲に通って実を結ぶと考えられていたのです。だから「稲夫」と書かれていたのです。
代は、稲の稔を女性の妊娠と考え、稲は女性とされていました。そして、稲が実る時期に雷光が多く、この雷光が毎夜、稲に通って実を結ぶと考えられていたのです。だから「稲夫」と書かれていたのです。
 事実、稲妻の多い年はコメがよく稔るそうです。これは空気中の窒素が稲妻により雨に含まれ肥料となるからだとされています。
事実、稲妻の多い年はコメがよく稔るそうです。これは空気中の窒素が稲妻により雨に含まれ肥料となるからだとされています。
そんなことより、「夫」が頑張ったからとした古代の人の考え方に共感するのは、私だけでしょうか。
つま【妻・夫】
配偶者の一方である異性。
結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒ヤソトモノオと出で行きし愛夫ウツクシツマは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛ハしき誰が―」
転じて現在では、夫婦の一方としての女。 おっと。
広辞苑
もともと「つま」とは男女に関係なく、その配偶者を指していたのです。しかし現在ではもっぱら女性のほうを指して言うようになり、漢字も「夫」から「妻」に変わりましたが、ひらがな表記の場合は「いなずま」が残っている、と言うわけです。
したっけ。
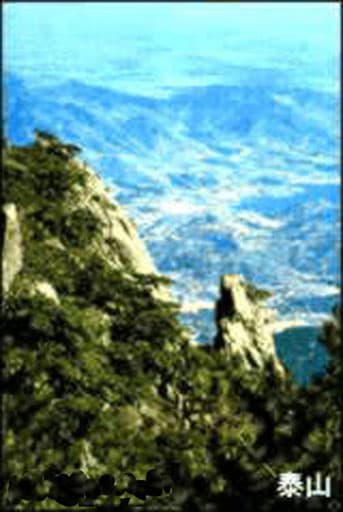 泰山(たいざん)は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来より名山として敬われている。泰山(たいざん)には大きな山という意味もありました。
泰山(たいざん)は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来より名山として敬われている。泰山(たいざん)には大きな山という意味もありました。
「泰山頽(くず)れ梁木(りょうぼく)折る」
「泰山卵を圧す」
「泰山の霤(あまだれ)石を穿(うが)つ」
「泰山北斗の如し」
「大山に登りて天下を小とす」
「大山の高きは一石に非ず」
など「泰山」「大山」を使った中国伝来の諺は数多くあります。
ですから、当然、「大山鳴動(して)鼠一匹」も中国伝来と思いがちですが、実はそのルーツはラテン語の成句だったのです。
 この有名な句は、ギリシアの諺「山が産気づいた。そして鼠一匹を生み落とした」にもとづくといわれます。この諺は ガイウス・ジュリアスパエドルス(Gaius Julius Phaedrus,およそ紀元前15年から西暦50年)の『アエソープス(イソップ)風寓話』四・二四にも取りあげられ、短い寓話として語られているそうです。
この有名な句は、ギリシアの諺「山が産気づいた。そして鼠一匹を生み落とした」にもとづくといわれます。この諺は ガイウス・ジュリアスパエドルス(Gaius Julius Phaedrus,およそ紀元前15年から西暦50年)の『アエソープス(イソップ)風寓話』四・二四にも取りあげられ、短い寓話として語られているそうです。
もともとイソップの寓話として伝えられた話の一つであり、これにもとづいてローマの詩人ホラーティウス(Quintus Horatius Flaccus, 紀元前65年12月8日 - 紀元前8年11月27日)がこの句を書いたことも考えられています。
「The mountain is labor and bringing birth a mouse.(英訳)」(山が産気づいて鼠を一匹産む)が出自です。
泰山が鳴動しているので、ひょっとして大地震、大噴火でもあるのかと恐れていたところ鼠が一匹出てきておしまい。なんとも拍子抜けです。
なおわが国でよく知られている「大山鳴動して鼠一匹」という句は、16世紀にキリスト教の伝来とともにわが国に伝えられたイソップの寓話(またはこれに類似した話)にもとづくものと推定されるのです。
したっけ。
都月満夫
佐倉淳平、私の父である。デカ(刑事)を退職して三年余り、毎日が退屈で堪らない。
私は山本淳一、現職のデカである。
私の両親は、私が小学校に入る前に離婚した。私は母に引き取られ、母の旧姓で育てられた。離婚の原因は、父があまりにも、仕事熱心であった為であった。
母から、警察官にだけはなるな、と言われて育てられた。家に帰ってこない、家庭を顧みない父であった、と言われ続けた。…にも係わらず、私は警察官になった。
そこで、私は父が洞察力の優れた刑事であったことを知った。父は仲間から尊敬を込めて『鬼の淳平』、『鬼平』と呼ばれていた。
北海道警察の『鬼平』が、私の父であることを知る者は少ない。
やがて、私は結婚し、父と同じ理由で離婚した。子供はいなかった。
母は亡くなり、現在、父と同居している。
「おっ!帰ってきたな。」
父がご機嫌で迎えてくれた。また、退屈の虫が疼いているに違いない。
「また退屈ですか…。駄目ですよ。今日は疲れて、眠りに帰ってきたんですから…。」
「そんな、つれないことを親に向かっていうもんじゃないよ。例のマンションの、中学校の女性教師変死事件、調べてんだろ…。発見されて一週間、何の続報もない。お前は帰って来ない。退屈で、退屈でうずうずしてたんだ。そろそろ帰って来るんじゃあないかと、旨い酒買って待ってたんだ。刺身まで買ってよ。聞かせろよ。どうなってんだ、え。」
「駄目ですよ。事件のことは、関係者以外には、話せませんよ。」
「関係者以外って…。オレとお前は親子っていう密接な関係じゃないか…。それに元刑事と現職刑事って関係だ。先輩の意見を伺うってことは大事なことだぜ。」
「またそれだ…。」
「どうせお前だって気になって寝られやしないだろ…。だったら旨い酒飲んで、親子で世間話をしたっていいだろ。」
「世間話って…、言ったって…。」
「世間話だろうよ。新聞に載ってた記事について、話をするんだ。ただ、お前がちょいと事件に詳しいってだけじゃないか、え。」
父はこう言い出したら、後へは引かない。『鬼平』といわれた男だ。
「…。殺し(殺人)ですよ。首を絞められて、殺されてたんですよ。」
「何で、変死なんて発表したんだよ、え。」
「それが…、吉川線がなかったんですよ。」
「吉川線がない。首を絞められたら、首に引っ掻き傷くらいは出来るだろうよ、苦しいんだから…。」
「それが、その引っ掻き傷、吉川線がなかったんで、変死って発表になったんですよ。」
「そうか…、それで検死の結果は…、絞殺か、扼殺かどっちなんだ、え。」
「扼殺(やくさつ)ですよ。」
「扼殺なら、紋(指紋)採れただろう、手で締めたんだ。首を絞めりゃぁ、指の汗腺から出る汗と、マル害(被害者)の皮脂が溶けて紋が残る。絞殺(こうさつ)なら、紐かロープの痕が残る。それに、自分の首は引っ掻かないとしても、ホシ(犯人)の腕くらい、引っ掻くだろうよ。だったら、マル害の爪にホシの皮膚が残るんじゃないか、え。」
「それが、紋も皮膚片も…、採れないんですよ。」
「なら、手袋痕があるだろう。」
「それも、ないんですよ。」
「扼殺で吉川線がない。紋も採れない、ホシの皮膚も手袋痕もないってわけか…。紋のない人間なんて…、いないぜ…。」
父は首をひねった。
「で、死亡推定時刻は何時なんだ。発見されたのは、月曜の午前中だったよな。」
「解剖の結果、日曜の十二時から十五時ってことになってます。」
「日曜といえば、暑かった日だ。当然エアコンは…。」
「今年、使った痕跡はありませんでした。」
「そうか…。犯人の当り(見当)は…。」
「えぇ…、まあ…。」
「何だ、煮え切らないな。」
父は、湯飲みの酒をぐいと飲み込んで、私にも飲めと、一升瓶の口を向けた。
私は酒を飲み干し、湯飲みを差し出した。
「先生で、三十八歳、独身…。で、そのマル害、美人なのかい。」
「ええ、美人ですよ。美人ですけど、豆泥棒(婦女暴行)ではありませんよ。部屋も荒らされていませんし、顔見知りでしょうね。」
「だったら、すぐに判りそうなもんじゃないか。そんなに交際範囲も広くないだろう。」
「そうなんですよ。一人交際相手の先生がいましてね。二十五歳の理科の先生なんですが…。他に、PTAのほうも、捜査中なんですよ。」
「ほかを調べてる…ってことは、そいつにアリバイありだな。で、お前の心証は?」
「黒(犯人)…、でしょうね。」
「そうか…。で、どんなアリバイだ。」
「それが、日曜の九時ごろから、十五時近くまで、生徒と一緒だったんですよ。」
「日曜だ…ってのにか。え。」
「理科クラブの生徒四人と公園で、昆虫採集やら植物採集やらを、してたそうです。」
「生徒の言(証言)じゃ、間違いなさそうだな。」
「で、その理科の先生、評判は…。」
「どの先生に聞いても、真面目で、生徒にも人気があったようです。」
「で、付き合ってたってのは、どこから聞き込んだネタ(情報)だ。」
「行きつけのスナックです。先生たちは知らなかったようなんですよ。」
「仲間内が知らないってのは、おかしいじゃないか。何か事情があるのか…、え。」
「ええ、マル害のほうは実家にすすめられた縁談があるので、田舎に帰って、結婚するようなことを言っていた、って聞いた先生がいましたが…。事情までは…。」
「裏(証言)は取れないんだな。」
「そうなんですよ。実家では、そんな話はないって…。」
「何で、そんな嘘つくんだ…。で、スナックでは、どんな様子なんだ。」
「ちょっと、待ってくださいよ。次から次と、まるで尋問みたいじゃないですか。」
私はそう言って、刺身を口に入れ、酒を飲んだ。父もつられて、酒を飲んだ。
「スナックって言ったって、十人も入りゃあ満員、ってなとこですがね。理科の先生が着任したときに、学年の担任の先生たちと来たのが最初で、後は二人で、ちょいちょい来てたって、言ってましたよ。」
「で、どうなんだ。どうして二人で、ちょいちょいなんだよ、え。」
「それが、男のほうが新任で、ベテランの女性教師に、色々と相談事をしていたようです。生徒指導とか、授業の進め方とか…。」
「ベテラン美人教師の、課外授業ってヤツだな。それで、色々の関係になった…。」
「そうなんですよ。最近の先生は、結構あるらしいですよ。外部との接触の機会が少ない職場ですから…。」
「お前ね、余計なことはいいんだよ。先生たちも来るスナックで二人が飲んでて、他の先生たちが、二人の仲を知らないってのは、変じゃないか?」
「ええ、そうなんですが…。あまりに不釣合で、まさか、付き合ってるとは、思わなかったようで…。」
「で、その不釣合ってのは、どういう意味だよ?」
「男性教師が子供っぽくて、生徒の中にいると見分けがつかないってことですよ。」
「お前もそう思うか?」
私は、酒を口に運びながら、頷いた。
「で、最近の二人の仲はどうだったんだ。そこんとこが、大事なとこじゃないか。見かけじゃ、男女の仲は判らない…。」
「それが…、よく判んないんですよ。学校じゃ誰も知りませんし。スナックのママも、店では仲良く飲んでたって…。」
…。父は再び腕組みをして、考え込んだ。
「マンションからは、何か出ないのか…。」
「何かって言っても、女の一人暮らしですから、別にこれといって不審なものはありませんよ。」
「男の紋は…。」
「ありましたよ、部屋中に。付き合っていた、って言ってるんですから…。」
「変なところになかったか、ってんだよ。」
「テーブルを持ち上げた痕跡がありましたよ。前の週に、カーペットを替えたって…。」
「で、その日は…、行ってないんだよな。」
「はい、本人はそう言ってます。」
「で、隣近所は…。」
「誰も、隣の住人に興味を持つ人間なんて住んじゃいませんよ。独身者ばかりの、賃貸マンションですから…。」
「そういうもんかね。情けないね…。」
そう言うと、父はまた腕を組んだ。
「そういえば、スナックのママが、毎週日曜日に、女の部屋で、二人で食事をしているらしいって、言ってましたよ。」
「バカヤロー、どうして、そういう大事なことを話さないんだ。何で、その日だけ行かなかったんだよ、その男、え。」
「ですから、理科クラブの課外活動の、標本整理があるので、行かないって、前もってマル害に言ってあったそうです。」
「それで納得したのか…。だからお前はダメだっちゅうんだよ。二十五歳の男だよ。少しぐらい忙しくたって、行くだろうよ。逢いたいだろうよ。クラブの標本整理なんか、後回しにしてでも、逢いたいだろうよ。増してや、人目をはばかる仲だろ。逢いたくない訳がない。おかしい…。」
「そうですかね…。」
「そうですかね…、じゃないよ。何か他にないのか、何か…。」
そういうと、父は湯飲みの酒をちびちび飲みながら、考え始めた。
「冷蔵庫の中はどうだった。」
何か閃いたように、父が言った。
「どうって、食材はかなりありましたよ。日曜日だから買い込んだんじゃないですか。」
「ん、そいつはおかしいな。死亡推定時刻は、十二時から十五時だったよな。日曜日の午前中に買い物に行くかな。日曜日の朝ぐらいは、ゆっくりしたいんじゃないか。その日は、男が来ないんだからよ、え。」
「それはそうですが。そうでない人間も、いるんじゃないですか?」
「…ん、こいつは、おかしい。しっくりこない…。…ん。」
そう言うと、父はぶつぶつと何か言いながら、考え始めた。これは、父の勘が働き始めたときの癖である。
「あ、そうだ。スナックのママが言ってました。」
「まだあったのかい。で、何て…。」
「男がトイレに行ったときに、『私でいいのかな…』って、女が言ったって…。」
「それは、どんな調子で言ったんだ。」
「呟いただけだから、なんとも…。」
「これは確認だが、男のほうは結婚する気だったんだよな。」
「ええ、そりゃあもう、子供のようにハシャイデたって、スナックのママが…。」
「それだ。女は悩んでたんだ。こんな若い先生と付き合っていいのか…。別れたほうがいいんじゃないのか、ってな。だから、嘘の結婚話で、学校を辞めようと…。馬鹿な女だぜ。知らなかったのは、回りの先生だけじゃない。肝心の相手の男も、女の気持ちに気づいてやれなかったんだ。男は純粋に女を愛していた。しかし、女は、自分の年齢に悩んでいたんだ。純粋に愛してやればいいのによ。女ってのは、ややこしい生き物だぜ。」
「ちょっと、お父さん。ダメですよ。理科の先生には、アリバイ…。」
「そう考えれば、全てが、納得がいく。」
人の話しなど聞かず、父は得意そうに、私の顔を見た。
「お前に質問だ。その理科の先生、ひょっとして、登山の趣味はなかったか?」
「本格的な登山ではありませんが、生物や植物の観察に、よく、山には行くそうです。」
「もうひとつ。殺された先生の部屋にあったテーブルの大きさは…、人一人ぶん位…。」
「ええ、大きかったです。」
「それと、もうひとつ。その生徒たちといた場所から、女のマンションまで、どれくらいで行ける。」
「生徒を学校まで自動車で送ったとしても、一時間はかからないでしょう。」
「そうか…。読めたよ。いいかよく聞け。先ず、二人の関係だ。男は夢中だが、女は悩んでいた。多分、女も男に惚れてたんだ。だから、自分でいいのかと、心配になった。しかし、年齢差があるので、身を引こうと、嘘の結婚話を洩らしてみた。しかしそれは、噂にもならなかった。それは女にとっては辛い話だ。男はそんなことは知らずに、その日、いつものように、生徒と別れて、女のマンションへ行った。午後四時としよう。そこで、女の口から、結婚話を聞かされた。口論になって、男は女の首を絞めた。女は男が、自分を殺すほど、愛していたことに驚いて、自分の首を絞めている手を振り払うことも出来なかった。それで、吉川線が残らなかった。抵抗すりゃぁよかったんだ。好きだって言ってよ。ところで、首を絞められたら、少なからず喀血するもんだが、血痕は、あったか?」
「いいえ。」
「そうだろうよ。好きな女を殺しちまったんだ。それぐらい、拭き取るだろうよ。女の部屋に、焼酎かウィスキーはあったか?」
「ええ、ブランディーがありました。」
「多分、そいつで、拭いたんだろうよ。自分の紋もよ。アルコールで、汗を拭取りゃあ紋は検出できない。それと、アリバイだ。山へ行く人間なら、アルミシートを持っていたに違いない。こいつは、NASA(アメリカ航空宇宙局)が開発した素材を使用した、優れものだ。雪山で遭難した時に、こいつを持ってりゃ、助かるって言われるほど、断熱効果がある。おまけに、軽く、折畳めば小さくなり携帯に便利だ。今は、贅沢さえ言わなけりゃ、百円ショップでも売っているぜ、類似品を…。そいつで、死体を覆い、テーブルで四隅を押さえた。ペットボトルの、冷えた飲料水でも、保冷剤代りに使って…。シートの断熱効果で、死体は外気温に左右されることなく、保冷された。そして、お前たちの、死亡推定時刻を誤らせた。気温が下がった夜中に、男はアルミシートを、回収したんだろうよ。付き合っていた仲だ、合鍵ぐらいは持っていて、不思議はない。だから、テーブルの下に、持ち上げた時の指紋が残っていた。冷蔵庫に、指紋のないペットボトルが、あれば決まりなんだが…。こいつはオレの推測だ。ここから先は、お前たちの仕事だ。明日から、また忙しくなるぞ。早く寝ろ。」
父は、旨そうに湯飲みの酒を飲み干し、にやりと笑って、立ち上がった。
「 歌舞伎」といえば、その創始者は出雲阿国(いずものおくに)であることはご存知の方も多いと思います。でも、考えてみてください、出雲阿国は、れっきとした女性です。何故、歌舞伎に女優が登場しなくなったのでしょう。
歌舞伎」といえば、その創始者は出雲阿国(いずものおくに)であることはご存知の方も多いと思います。でも、考えてみてください、出雲阿国は、れっきとした女性です。何故、歌舞伎に女優が登場しなくなったのでしょう。
「歌舞伎」を男の役者ばかりで演じるようになったのはずっと後のことなのです。
出雲阿国(いずものおくに:1572年(元亀3年?) - 没年不詳)が、歌舞伎を創始したのは安土桃山時代のことです。
 1603年(慶長8年)に出雲阿国が、歌舞伎踊りで評判を集めると、阿国を真似た遊女たちによって、「女歌舞伎」が大流行しました。彼女たちは芝居興行の後に宴席に呼ばれ、その夜は本職に精を出すのが当時の興行形式だったのです。
1603年(慶長8年)に出雲阿国が、歌舞伎踊りで評判を集めると、阿国を真似た遊女たちによって、「女歌舞伎」が大流行しました。彼女たちは芝居興行の後に宴席に呼ばれ、その夜は本職に精を出すのが当時の興行形式だったのです。
阿国の歌舞伎との大きな違いは、当時最新の楽器だった三味線が使われていたことです。1615年(元和「げんな」元年)から1629年(寛永「かんえい」6年)頃が最も盛んだったようです。しかし、風俗を乱すという理由で1629年(寛永6年)に、「女歌舞伎」、「女浄瑠璃(おんなじょうるり)」など、女性が演じる興行が一切禁止されてしまったのです。

 「女歌舞伎」の禁令により、前髪のある成人前の少年が演じる「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」に人気が集まります。しかし、今度は美少年たちが男色家の餌食になったのです。結局、風俗の乱れはおさまらなかったのです。しかしこれも風俗を乱すため、やむなく幕府は美少年たちの前髪を剃り落とすよう命じ、1652年(承応元年)頃から禁令が出されるようになります。
「女歌舞伎」の禁令により、前髪のある成人前の少年が演じる「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」に人気が集まります。しかし、今度は美少年たちが男色家の餌食になったのです。結局、風俗の乱れはおさまらなかったのです。しかしこれも風俗を乱すため、やむなく幕府は美少年たちの前髪を剃り落とすよう命じ、1652年(承応元年)頃から禁令が出されるようになります。
この禁令以降、前髪をそり落とした野郎頭(やろうあたま)の成人男性が演じる「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」の時代に入っていきます。
随筆・嬉遊笑覧(1830年)一下「寛文の頃の歌舞伎役者のやうに中程を細くそりたり。」とあるそうです。
「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」の時代にも、女性役を演じる「女方(おんながた)」は存在しましたが、技術よりも容色が重視されていました。しかし野郎歌舞伎では、「女方」を専門に演じる俳優が登場し、技術的に女性らしさを表現する方向へと発展していきます。
また「野郎歌舞伎」は、当初、歌や踊りによる短い場面で完結した「離れ狂言(はなれきょうげん)」をいくつか続けて上演していましたが、次第にストーリー性をもつ複数の場面からなる「続き狂言(つづききょうげん)」が上演されるようになります。やがて複雑化したストーリーを表現するために、登場人物を類型化して演じるようになり、延宝年間(1673年~1681年)には、役の年齢や性格に基づいた「役柄(やくがら)」が確立しはじめます。具体的には、若い女性を演じる「若女方(わかおんながた)」、男性役の「立役(たちやく)」、男性の悪人の「敵役(かたきやく)」、中年から老人の女性を演じる「花車方(かしゃがた)」、滑稽な役を演じる「道化方(どうけがた)」などが挙げられ、それぞれの役柄にあった演技術が編み出されていきます。
 「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」の時代が終わり、元禄年間(1688年~1704年)前後には、歌舞伎は江戸と上方[京・大坂]のそれぞれで大きく発展します。
「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」の時代が終わり、元禄年間(1688年~1704年)前後には、歌舞伎は江戸と上方[京・大坂]のそれぞれで大きく発展します。
江戸では、「荒事(あらごと)」を得意とした初代市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)が活躍しました。
「荒事」とは、「見得(みえ)」や「六方(ろっぽう)」などの演技や、「隈取(くまどり)」をはじめとする扮装によって表現される豪快で力強い芸をさします。このような芸が江戸で好まれた理由として、江戸が武士中心の町であったことが挙げられます。また「荒事」は、万治から延宝年間(1658年~1681年)にかけて流行した、金平浄瑠璃(きんぴらじょうるり)の影響を受けているともいわれています。
 1688年~1704年(元禄年間)前後の上方(京・大坂)では、後に「和事(わごと)」とよばれるようになる柔らかく優美な演技を得意とした、初代坂田藤十郎(さかたとうじゅうろう)が活躍しました。藤十郎は、1678年(延宝6年)に上演されて大評判となった『夕霧名残の正月(ゆうぎりなごりのしょうがつ)』の伊左衛門(いざえもん)役をはじめとして、本来は身分が高いにもかかわらず、理由があって落ちぶれている「やつし」とよばれる設定の役を演じて人気を得ました。人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)の作者として有名な近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)は、藤十郎のために『傾城仏の原(けいせいほとけのはら)』をはじめとする多くの歌舞伎作品を書き、藤十郎の人気を支えました。
1688年~1704年(元禄年間)前後の上方(京・大坂)では、後に「和事(わごと)」とよばれるようになる柔らかく優美な演技を得意とした、初代坂田藤十郎(さかたとうじゅうろう)が活躍しました。藤十郎は、1678年(延宝6年)に上演されて大評判となった『夕霧名残の正月(ゆうぎりなごりのしょうがつ)』の伊左衛門(いざえもん)役をはじめとして、本来は身分が高いにもかかわらず、理由があって落ちぶれている「やつし」とよばれる設定の役を演じて人気を得ました。人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)の作者として有名な近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)は、藤十郎のために『傾城仏の原(けいせいほとけのはら)』をはじめとする多くの歌舞伎作品を書き、藤十郎の人気を支えました。
また同時期に活躍した女方の初代芳沢あやめ(よしざわあやめ:1673~1729)は、女方の心得や演技論をまとめた芸談『あやめ草』を残し、女方芸の確立に大きな役割を果たしたということです。
したっけ。
「遅かりし由良之助」という慣用句知っていますか?
若い人にとっては死語かもしれません。いえ、私だってこんなフレーズは口にしたことはありません。子供のころ年配の人が言うのを聞いたことはあります。
間に合わない、手遅れといった事態になると、ことあるごとに「もうだめだ、遅かりし由良之助だ」「残念でした。遅かりし由良之助!」なんて言っていました。子供のころは、由良之助って誰なのだろうと長らく疑問に思っていました。
 大人になって、これは歌舞伎だということが分かりました。「仮名手本忠臣蔵」。
大人になって、これは歌舞伎だということが分かりました。「仮名手本忠臣蔵」。
私は歌舞伎についてはほとんど知識を持ち合わせませんが、「仮名手本忠臣蔵」が赤穂浪士の話であることくらいは知っています。
それでその中に出てくる大星由良之助というのが大石内蔵助のことなのです。吉良上野介も室町時代の実在の人物・高師直(こうの・もろなお)に名前を変えてあります。浅野内匠頭らしき人物は塩冶判官と名乗っています。赤穂の塩だから、「塩冶判官」とは昔の人は洒落が利いています。
吉良上野介:高師直
浅野内匠頭:塩冶判官
なんでそんなことするかと言えば、赤穂浪士というのはそもそも江戸幕府の作った制度に背いて敵討ちを果たした反逆者で、そんな連中を賛美する物語を書いたりしたら、幕府から御咎めを受けてしまう。
そこで知恵を絞って、「これは江戸時代の話ではありません。室町時代のお話です。」ということで実在の人物高師直を登場させ、他は架空の人物を配してあるのです。
その芝居の中で大星由良之助が塩冶判官の切腹の場に駆けつける場面があるそうで、由良之助はなんとか判官が息を引き取る前にたどり着くのだそうです。
たどりついた訳ですから、必ずしも「遅かりし由良之助」でもなかった訳で、実際芝居の中でこの台詞が語られる訳ではないのだそうです。
では何故このような言葉が生まれたのでしょう。
歌舞伎では、なかなか由良之助が到着しない。すんでのとこで塩谷判官の息のあるうちに目通りかなったわけですが、この間、観客はみな、由良之助は遅い、いったい何しているのかと思いになっているわけです。
・・・で、そのじりじりするようなもどかしい思いから、誰が言いはじめたのやらですが
「遅かりし由良之助」という言葉が生まれて、いつの間にか独り歩きをしちゃったということらしいのです。
また、後の歌舞伎作家・河竹黙阿弥が自分の作品、「こいつは春から縁起がいい」の台詞で有名な「三人吉三廓初買』(さんにんきちさ くるわの はつがい)」の中に由良之助の名前を引用しているのだそうです。
巾着切:和尚吉三(おしょうきちさ)。浪人:お坊吉三(おぼうきちさ)。旅役者:お嬢吉三(おじょうきちさ)。などが登場します。その中の和尚吉三の台詞です。
和尚「むむ・・・、そんなら二人が百両を貸す貸すめえと言い募り、大切の命を捨てる気か、そいつぁ飛んだ由良之助だがまだ了簡が若い若い。ここは一番おれが裁きをつけようから、厭でもあろうがうんと言って話に乗ってくんなせえ、互いに争う百両は二つに割って五十両、お嬢も半分お坊も半分、留めに入ったおれにくんねえ、その埋草に和尚が両腕、五十両じゃあ高いものだが抜いた刀をそ のままに鞘へ納めぬおれが挨拶。両腕切って百両の額を合わせてくんなせえ。」
歌舞伎には詳しくないので全体像を把握していません。ですから、「そいつぁとんだ由良之助」が何故「遅かりし由良之助」という台詞として残ったのかは分かりません。
中途半端で申し訳ない・・・。
したっけ。
錬金術は、一説によると一世紀頃にアレクサンドリアあたりで発生したといわ れる。冶金の技術は錬金術の基盤の主要な部分をなしており、その萌芽となるとさらに遡るようである。紀元前13世紀頃のバビロニアの粘土板にはすでに銅鉱石から銀を抽出する製法が記されているらしいし、鉛鉱石から銀を抽出する灰吹法はさらに遡ると云われる。
れる。冶金の技術は錬金術の基盤の主要な部分をなしており、その萌芽となるとさらに遡るようである。紀元前13世紀頃のバビロニアの粘土板にはすでに銅鉱石から銀を抽出する製法が記されているらしいし、鉛鉱石から銀を抽出する灰吹法はさらに遡ると云われる。
古代インド語のサンスクリット語でタータラは熱の意味、ヒンディー語では鋼をサケラーと言うが、これは出雲の鋼にあたるケラと似ているし、ミャンマー語で刀はカタナと言うことなどから、たたら製鉄法はインドの製鉄技術が東南アジア経由で伝播したものではないかと言っています。
いずれにしても、たたらという言葉は強く熱するという意味で、金属製錬と密接に関係し、インドあるいは中央アジアに源をもつ言葉であると考えられます。
 粘土板により錬金術の技術が伝えられたことは、散見されます。よって、この粘土板自体を「タタラ」と言うようになり、やがて粘土を捏ねるときの道具のなまえになったのではないかと推測します。
粘土板により錬金術の技術が伝えられたことは、散見されます。よって、この粘土板自体を「タタラ」と言うようになり、やがて粘土を捏ねるときの道具のなまえになったのではないかと推測します。
したっけ。
コイとフナはともに淡水魚を代表するような魚だが、コイが川魚の王さまのように扱われ、コイの滝登りとか五月のこいのぼりのように華やかな役どころが与えられているのに対し、フナの方は昔から泥臭いもののたとえとして扱われてきた。
江戸時代には意気地なしの田舎者のことをフナと呼び、かの浅野匠頭も吉良上野介に「鮒侍」といわれて頭に血が上ったわけだから、もしも「鯉侍」といわれていたら、討入りなんぞなかったにちがいない。
「お前の狭い家が井戸だとすれば、この御殿は世間だ。井戸の中の鮒は広いところでおろおろして柱に頭をぶつけて死んでしまう。その鮒にお前は似ている。よく見れば鮒そっくりじゃないか。鮒が侍の姿をするのを俺ははじめて見た。鮒だ、鮒だ、鮒侍だア」
歌舞伎の場合、この登場人物は高師直(=吉良)と塩谷判官(=浅野)ということになります。
ところで、高家筆頭で旗本4000石余の吉良上野介の領地は三河国幡豆郡吉良庄です。足利尊氏の親戚筋で三河に定住していた吉良家の係累にして、今川氏真の玄孫という血筋ですが、三河が都会というわけではありませんね。一方の播磨国赤穂五万石も、塩の生産は盛んでしたが、こちらも当時はそれほど先進地帯ではありません。
では、なぜ上野介が「田舎大名」とののしったのか?が疑問ですよね。実は、吉良上野介は江戸生まれの江戸育ちで、領地には一度しか行ったことが無いのです。旗本の場合は、たいてい領地には行かず、代官などに任せきりにすることが多いのです。
つまり、吉良は江戸という大都会の「都会っ子」を自認していたということでしょう。
一方、大名の場合は参勤交代で、一年毎に領地と江戸を行き来しています。当然、軸足は領地にあるわけです。江戸に馴染めなかった人もいたそうで、そういう意味からも旗本たちからは「田舎者」という目で見られていた可能性はかなりありますね。でも、そう言われたくらいでかっとなるかどうかはかなり疑問です。
そこのところは、創作でしょうから、それはそうとしておきましょう。
鮒侍(ふなざむらい)
鯉(コイ)を高位として大人物に例えたとき、鮒(フナ)を小人物と考えた鮒の呼び名。転じて、ドタバタ騒ぐヘッポコ侍のこと。四十七士の仇討ちの美談はともかく、その原因となった浅野内匠頭の殿中松の廊下の刃傷沙汰は、その典型かもしれぬ。髭のあるなしでこれだけの違いがあるのか。
尚、「鮒侍」と言う言葉は広辞苑には載っていません。
したっけ。
 一本の道がほぼ真横に延びるもう一本の道路に突き当たるところ、皆さんはなんといいますか?
一本の道がほぼ真横に延びるもう一本の道路に突き当たるところ、皆さんはなんといいますか?
「T字路(ていじろ:アルファベット)」と思っている人はいませんか。実は漢字で「丁字路(ていじろ)」が正しいのです。音も形も似ているために、最近の若い人は「T(アルファベット)」で書き表す例が見られます。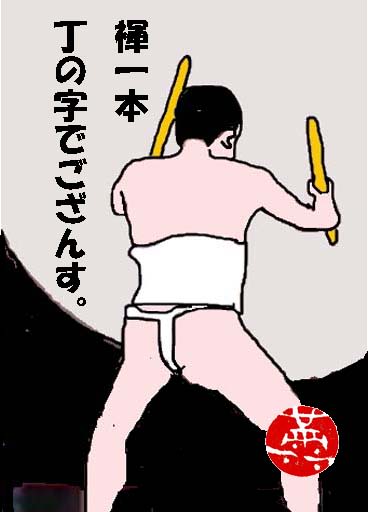
日本語ですから「丁字路(ていじろ)」と書きます。
 夏目漱石の『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』には「美土代(みとしろ)町と小川(おがわ)町が丁字になって交差している三つ角」とあります。
夏目漱石の『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』には「美土代(みとしろ)町と小川(おがわ)町が丁字になって交差している三つ角」とあります。
また「道路交通法」にも「十字路、丁字路その他ニ以上の道路が交わる・・・・・・」とあります。
「T字」よりも先に「丁字」という言葉が日本語としてあるのですから、こちらを使うほうが望ましいというわけです。
ていじ‐ろ【丁字路】
丁字形に交わった道路。
広辞苑
丁字路(ていじろ)は、道路が漢字の丁のような形で枝分かれしている交差点。
道が三方に向けて延びる三叉路の一種である。道路標示はT字型の白線で描かれる。また、道がアルファベットのYの形のように枝分かれしている場合はY字路と呼ばれる。
「丁」の字の発音、字形ともにアルファベットのTに似ているため、現在では「T字路」(ティーじろ)と呼ばれることが一般的になっているが俗称である。
法令上の正式名称はあくまでも「丁字路」であり、道路交通法第2条(定義)5項でも「交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう」と記載されている。
また、上記のY字路も俗称であり、正しくは三叉路である。
Feペディア
などといいながら、先日の運転免許証の更新時に貰った教本を見ると、標識の欄には「+形道路」「┣形道路」「T形道路」「Y形道路」と記載されていました。
時代とともに言葉も変わっています。
したっけ。
 「助手席」という言葉の語源はというと、もともとはタクシー業界の業界用語だったのです。
「助手席」という言葉の語源はというと、もともとはタクシー業界の業界用語だったのです。
大正時代、街中を流す交通手段は人力車がハバをきかせ ていて、タクシーなどとても珍しかった時代の話です。当時、タクシーには運転手と共にもう一人、客の乗り降りを助けた人が乗っていました。
ていて、タクシーなどとても珍しかった時代の話です。当時、タクシーには運転手と共にもう一人、客の乗り降りを助けた人が乗っていました。
なんせ、当時のタクシーは外車で車高が高いうえに、お客さんは着物姿。当然、乗り降りには手助けが必要でした。そして、彼らは「助手さん」と呼ばれていました。それから「助手席」という言葉が生まれて、タクシーの台数が増えるにしたがって「助手席」という呼称が定着していった…と言われています。
それと、もう一つ、クルマ(自動車)が、今のように快適な乗り物ではなかった昔、自動車を一人で運転するのは大変な時代だったのです。

 エンジンをかけるにしても、今はキーをひとひねりすればかかるのですが、昔は、クランクシャフトに、ナンバーの上の穴から棒を突っ込み、(今のジャッキハンドルのようなものです)それを両手で、回転させて、エンジンをかけたのです。
エンジンをかけるにしても、今はキーをひとひねりすればかかるのですが、昔は、クランクシャフトに、ナンバーの上の穴から棒を突っ込み、(今のジャッキハンドルのようなものです)それを両手で、回転させて、エンジンをかけたのです。
そのときに、運転席で、アクセルの微妙な踏み加減が必要だったために、一人でのエンジン始動は困難だったと思われます。40年ほど前までは、セルモーターはついていたものの、バッテリーの容量が少ない上品質も悪かったので、チョークレバーや、ハーフスロットルなど、冬のエンジン始動は大変な作業だったのです。冬の北海道では、オイルパンの下に炭火を置いてオイルを温めました。そうしないと、オイルが硬くエンジンは始動できなかったのです。
また、今のようにステアリング(ハンドル)も安定していないし、ましてや今のように舗装道路ではなく、砂利道を走るものでした。ですから、運転手は、必死でハンドル操作をし、道を探す余裕など無かったのです。
 そこで、先ほどエンジンをかけた人間が、運転席の隣に座り、道案内の補助などをしたのです 。また、それよりも昔、車がまだほとんど走っていなかった頃には、(馬車の時代)先ほどの運転席の隣に座った人が、「ランプ」を持って車から降り、車の前を走って、車の接近を知らせ、道をあけさせたという話もあります。運転席の隣に座る人は、さまざまな雑用を行っていたのです。
そこで、先ほどエンジンをかけた人間が、運転席の隣に座り、道案内の補助などをしたのです 。また、それよりも昔、車がまだほとんど走っていなかった頃には、(馬車の時代)先ほどの運転席の隣に座った人が、「ランプ」を持って車から降り、車の前を走って、車の接近を知らせ、道をあけさせたという話もあります。運転席の隣に座る人は、さまざまな雑用を行っていたのです。
当時、クルマの運転手は非常に数が少なく、エンジニアのような存在だったようです。ですから、運転手は席に座ったまま、何もしなかったのです。
しかし、昭和に入って人件費が高くなったため、タクシーに「助手さん」が同乗する習慣は消滅してしまいましたが、言葉だけはそのまま残ったというわけなのです。
今、助手席に彼女を乗せて走っているのを当時の人が見たら、きっと驚くでしょうね。
したっけ。
美少年は、漢語あるいは日本語の単語である。広義では美少女も「美少年」なのです。そのため、広辞苑では「美少年」は記載してあるが、「美少女」は載っていません。(広辞苑は「美少女」を日本語として認めていないことになります。)しかも、「美しい人(美人)」は男性のみを指す言葉なのです(女性の場合は「美女」)。漢字が生まれた時代、「人」は男性のみを指す文字でした。
「美少年」を意味する用語の一つに「美少人」というものがあり、「小人」になると学徳なきだらしない者を示すそうです。
 もともとは文学上の修辞語で、古くは中国唐代の詩人杜甫の詩「飲中八仙歌」の一節「宗之瀟灑美少年 宗之(そうし)は瀟灑(しょうしゃ)たる美少年」に現れています。
もともとは文学上の修辞語で、古くは中国唐代の詩人杜甫の詩「飲中八仙歌」の一節「宗之瀟灑美少年 宗之(そうし)は瀟灑(しょうしゃ)たる美少年」に現れています。
飲中八仙歌 杜甫(とほ:盛唐712年- 770年)
宗之瀟洒美少年
舉觴白眼望青天
皎如玉樹臨風前
蘇晉長齋繡佛前
醉中往往愛逃禪
宗之 瀟洒(しょうしゃ)たる美少年
觴(しょう:さかずき)を舉げ 白眼青天を望む
皎(こう)として玉樹(ぎょくじゅ)の風前に臨むが如し
蘇晉 長齋(ちょうさい)す繡佛(しゅうぶつ)の前
醉中 往往 逃禪(とうぜん)を愛す
宗之はすがすがしい佇まいの美少年である
彼が杯を掲げ俗世を忘れ遥か空にまなざしを向ける様子は
美しい樹が風に吹かれているように爽やかで輝かしい
代悲白頭翁 劉季夷(りゅう きい:初唐〈651-678頃〉)
洛陽城東桃李花
飛来飛去落誰家
洛陽女児惜顔色
行逢落花長歎息
今年花落顔色改
明年花開復誰在
已見松柏摧為薪
更聞桑田変成海
古人無復洛城東
今人還対落花風
年年歳歳花相似
歳歳年年人不同
寄言全盛紅顔子
応憐半死白頭翁
此翁白頭真可憐
伊昔紅顔美少年
公子王孫芳樹下
清歌妙舞落花前
光禄池台開錦繍
将軍楼閣画神仙
一朝臥病無相識
三春行楽在誰辺
宛転娥眉能幾時
須臾鶴髪乱如糸
但看古来歌舞地
惟有黄昏鳥雀悲
飛び来り飛び去りて誰が家にか落つ
洛陽の女児 顔色を惜しみ
行くゆく落花に逢いて長歎息す
今年花落ちて顔色改まり
明年花開いて復た誰か在る
已に見る 松柏の摧かれて薪となるを
更に聞く桑田の変じて海と成るを
古人復洛城の東に無く
今人還って対す 落花の風
年年歳歳花相似たり
歳歳年年人同じからず
言を寄す 全盛の紅顔の子
応に憐れむべし 半死の白頭翁
此の翁白頭 真に憐れむべし
伊れ昔 紅顔の美少年
公子王孫 芳樹の下
清歌妙舞す 落花の前
光禄の池台 錦繍を開き
将軍の楼閣 神仙を画く
一朝 病に臥して相識無く
三春の行楽 誰が辺(ほと)りにか在る
宛転たる娥眉 能く幾時ぞ
須臾にして鶴髪 乱れて糸の如し
但だ看る 古来歌舞の地
惟だ黄昏鳥雀の悲しむ有るのみ
洛陽城東の桃李の花 風に飛びて たが家にか落つ
洛陽の娘は容色を心配して 落花を見てため息をつく
今年花が落ちれば一年容色がおとろえる 来年花開いた時 誰が生きているだう
既に松が枯れて薪となったのを見たり 更には桑畑が海になったと聞く
あの洛陽城東の古人は既に亡く 今私達が落花の風に吹かれている
紅顔の美少年が 白髪の老人は可哀想だと語りかけてきた
真に老人は憐れだが 昔は紅顔の美少年だった
公子王孫達が芳樹の下で 落花の前に歌い舞う
屋敷は錦繡を敷き詰めたように美しく 楼閣には神仙が描かれている
病に臥すと誰も来なくなる あの春の行楽は何処えいったのか
女性の美しさは長くは続かない あっという間に白髪も糸のように乱れる
昔の歌舞の舞台に 今は黄昏時に鳥や雀が来て悲しげに鳴くだけだ
こう‐がん【紅顔】
年が若く血色のよい顔。「―の美少年」「朝(あした)には―ありて夕べには白骨となる」
大辞泉
美少年とは、一般に、容貌の美しい少年を指す。特に、肌のつやつやした様子を強調して「紅顔の美少年」という形容が使われることもある。
美少年は、漢語あるいは日本語の単語である。広義では美少女も「美少年」である。
私だって昔は「紅顔の美少年」、今は「厚顔の醜老人」?いやいや、今だってまだまだ・・・。
したっけ。































