
525 松本市神林梶海渡の火の見櫓 撮影日150222
■ 前稿に載せた火の見櫓を見てから集落内の生活道路を更に進むとこの火の見櫓が立っていた。この美しいフォルムを見た瞬間に分かった、これはかつて小野にあった大橋鐵工所の「作品」だと。帰宅して資料を確認して、昭和31年3月に竣工した火の見櫓だと分かった。なだらかな曲線を描く柱がつくる末広がりの櫓が美しい。
反りのついた屋根、避雷針の飾りの形、大きい蕨手。見張り台の手すりの○とハートを逆さにしたような飾り。床面の梯子貫通部の円い縁取り。どれも大橋鐵工所のデザインの特徴だ。
理想的な美脚
きちんとコンクリート基礎までトラスが達している脚部。美しいし、構造的にも合理的だ。
踊り場まで架けた外梯子には手すりが付いている。丸鋼を2本並べた梯子段は足を掛けた時、1本とはかなり違うはず。このような気配りに製作者の人柄が窺えるように思う。
松本市の隣村、山形にも大橋鐵工所の「作品」(私が確認できたのは3基)があったが、残念なことに撤去されてしまった。辛うじて山形小学校の前庭に見張り台から上の部分のみ残されている。

左:神林南荒井の火の見櫓(117)撮影日150222 右:神林寺家の火の見櫓(448)撮影日130609
実は大橋鐵工所では神林地区で3基の火の見櫓を同時に一括受注している。それが梶海渡と南荒井、寺家の3基。共に昭和31年3月に竣工している。
梶海渡の火の見櫓の高さを押さえるために梯子段のピッチ(間隔)を測ると37センチメートルだった。南荒井もピッタリ同じ、37センチメートルだった。寺家の火の見櫓は測っていないが、同じではないかと思う。
神林三兄弟、いや三姉妹だから櫓の姿・形も屋根も見張り台もそして脚もよく似ていて、美しい。
過去ログ ←やはり大橋鐵工所で造られた火の見櫓
鐵工所を実名で記すことについて了解を得ています。










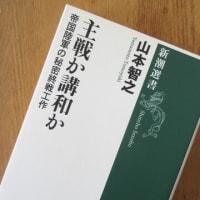









あれ、鉄工所実名で記載…ってまずいことだったんでしょうか?鉄工所どころか寄附者までバリバリ記載してて、今頃聞くのもどうかと思うのですが…。
火の見櫓そのものから読みとれる情報の公開については支障ないと考えています。鉄工所や寄附者の名を記した銘板が火の見櫓に付いているような場合です(いや、本当はこのことも問題があるのかもしれません。現地でのみ読みとれる情報をネット上に載せてよいものかどうか・・・、全く気にならないわけではありません)。
この稿に載せた火の見櫓については製作した関係者からいただいた資料に基づく情報ですので念のために確認しました。全く問題ありませんとのことでしたが。