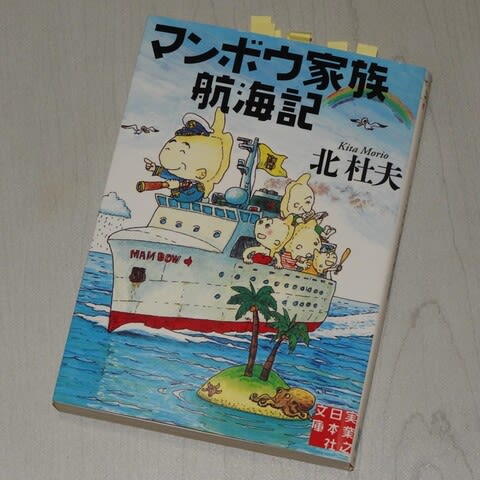■ 火の見櫓の建設費用はどうしていたんだろう・・・。
全額公費で、あるいは全額個人の寄付で賄うケース、全額地元住民が負担するケース、それからこれらの複合ケースがあっただろうと考えていた。一昨日(8日)火の見櫓建設の費用負担に関する資料が見つかった。
以下その報告。
上掲写真の火の見櫓は長野県朝日村西洗馬に立っていたが、隣りの消防団詰所と共に撤去された。見つかったのはこの火の見櫓の建設に関する資料。
この火の見櫓の建設工事契約書の写しと竣工記念写真は手元にある。契約書には請負金額 拾参萬圓也と記されている。記念写真には朝日村消防団第5分団 警鐘楼竣工記念 昭 30.8.12と文字入れされている(第5分団の第は略字)。
火の見櫓と消防団の詰所があった敷地には西洗馬公民館があるが、近々解体されることになっている。それで、一昨日の午前中にこの公民館2階の図書室に長年保存されていた書類等が一般公開されると知り、出かけた。この火の見櫓建設に関することが記載されている書類があるのではないか、と思ったので。
座卓に並べられた何点もの資料。
火の見櫓が建設された年、今から69年前の昭和30年(1955年)の記録簿を見つけた。火の見櫓の建設工事の契約日はこの年の6月21日、ということは契約書の写しで分かっている。予想していた通り、記録簿に建設費用支出に関する記録があった。
「警鐘楼建設補助金の件」 村費支辨(弁の旧字)以外不足金40,300円(記録簿には漢数字で書かれている、以下同じ)について各戸金100円平均負担として残り金13,000円を区にて負担するという内容が記されている(誤読はしていないと思う)。
この記録簿は上記の通り、自治体(村)と地元の区(西洗馬区)と地元住民が建設費用をそれぞれ負担したことを示す具体的な資料として貴重だ。
記録簿は今後も保管する予定、と聞いている。
記録簿には起工式が8月1日に、竣工式が8月12日に行われたことも記されている。これは契約書の工期(昭和30年6月21日~8月20日)より短い。
やはり記録するということは大事なことだと、改めて思った。