今日は先週あったM8の振付の復習。
高齢者が多いので、先週の振付もほとんど覚えていない。
リズム音痴の人が居たり、いわゆる『裏拍(アフタービート)』でリズムが取れない等々・・・。
まぁ、これは毎度のことなので、僕はあまり気にしていませんが・・・・(笑)
日本人は基本的に『裏拍(アフタービート)』が苦手と言われています。
この『裏拍(アフタービート)』に対して、『表拍』と言われるものがあります。
音楽において『表拍』とは、下の図にある様に
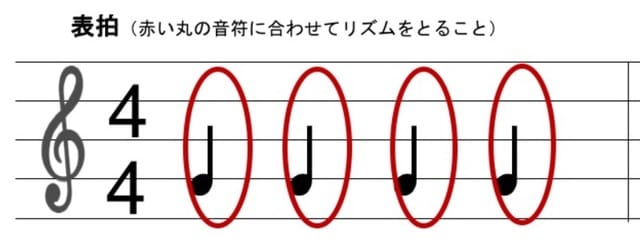
拍を前半と後半に分けたうちの、前半の部分を意味して用いられる音楽用語です。
具体的に言えば、上の図の丸に囲まれた部分を4分の4拍子の曲で「1と2と3と4と」とリズムをとった時、
1、2、3、4の数字の部分が表拍になります。
演歌や民謡の手拍子は、殆どこの『表拍』ですね。
逆にその間の「と」の部分が『裏拍(アフタービート)』になります。
演歌や民謡に対して、洋楽の殆どが『裏拍(アフタービート)』です。
日本人は『裏拍』が苦手。
そう言われる理由の1つに日本の文化的背景が原因と言われています。
お年寄りの観客が多い演歌や民謡などのコンサート会場では間違いなく、この表拍の手拍子を取る傾向があります。
今回の振付のM8は典型的な8ビート、いわゆるロックの曲なのですが、
アフタービートが出来ないから、振付のタイミングが取れないのです。
いっそのこと、ドジョウ掬いの振付にしてしまえ・・・
なんて思ったりするのですが、何度も練習してコツを掴めば出来るようになる。
そういう意味では『復習』というより『練習』ですね。
練習は決して裏切らない。
本番では爺さん婆さんが、元気な振付を披露してくれるでしょう。
高齢者が多いので、先週の振付もほとんど覚えていない。
リズム音痴の人が居たり、いわゆる『裏拍(アフタービート)』でリズムが取れない等々・・・。
まぁ、これは毎度のことなので、僕はあまり気にしていませんが・・・・(笑)
日本人は基本的に『裏拍(アフタービート)』が苦手と言われています。
この『裏拍(アフタービート)』に対して、『表拍』と言われるものがあります。
音楽において『表拍』とは、下の図にある様に
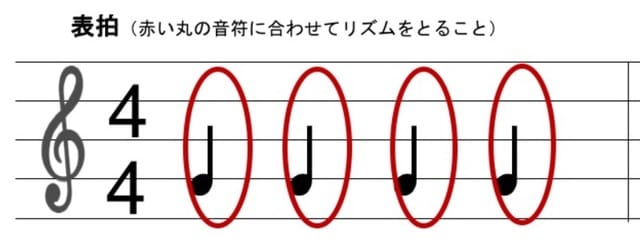
拍を前半と後半に分けたうちの、前半の部分を意味して用いられる音楽用語です。
具体的に言えば、上の図の丸に囲まれた部分を4分の4拍子の曲で「1と2と3と4と」とリズムをとった時、
1、2、3、4の数字の部分が表拍になります。
演歌や民謡の手拍子は、殆どこの『表拍』ですね。
逆にその間の「と」の部分が『裏拍(アフタービート)』になります。
演歌や民謡に対して、洋楽の殆どが『裏拍(アフタービート)』です。
日本人は『裏拍』が苦手。
そう言われる理由の1つに日本の文化的背景が原因と言われています。
お年寄りの観客が多い演歌や民謡などのコンサート会場では間違いなく、この表拍の手拍子を取る傾向があります。
今回の振付のM8は典型的な8ビート、いわゆるロックの曲なのですが、
アフタービートが出来ないから、振付のタイミングが取れないのです。
いっそのこと、ドジョウ掬いの振付にしてしまえ・・・
なんて思ったりするのですが、何度も練習してコツを掴めば出来るようになる。
そういう意味では『復習』というより『練習』ですね。
練習は決して裏切らない。
本番では爺さん婆さんが、元気な振付を披露してくれるでしょう。
















