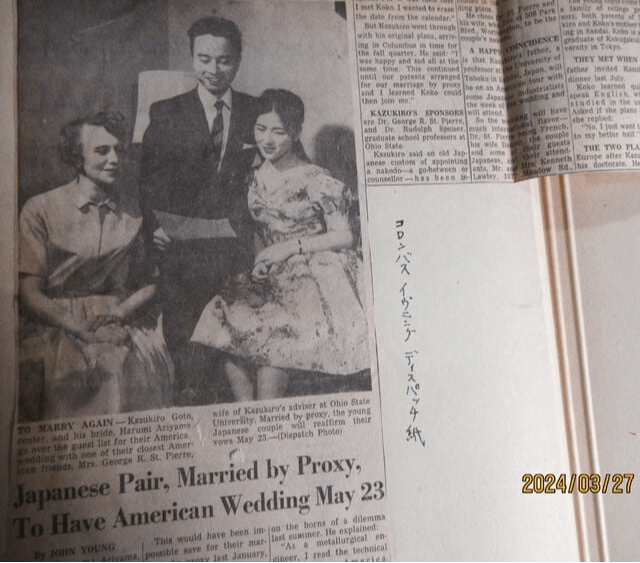




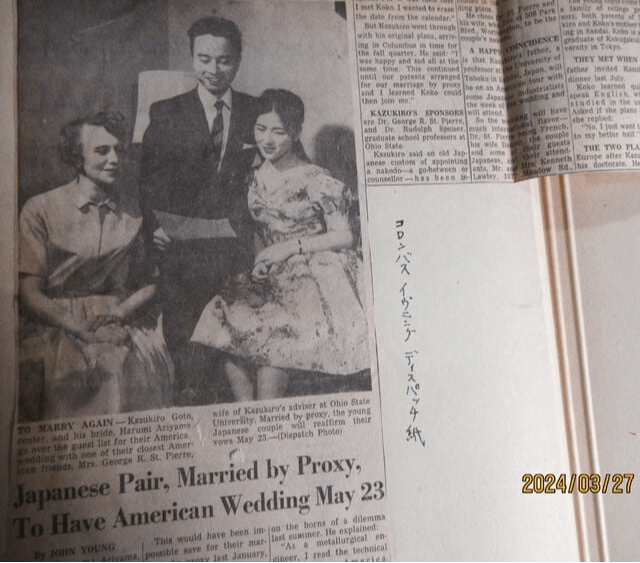























































山梨県へは以前に何度も出かけて行きました。甲斐駒岳の麓の山林の中の小屋を持っていたのでよく行きました。その甲府盆地の周囲の山沿いの傾斜地はブドウ栽培や桃の栽培に使われています。
春になると桃畑は文字通り「桃色」の花が一斉に咲きます。
特に東部の一宮や南部の南アルプス市、そして西部の新府には桃畑が広大に斜面を覆っています。
毎年4月になり花が咲くと夢のような風景になります。あちこちに「桃源郷」という看板が出ています。
甲府盆地の東の一宮には「日本一の桃の里一宮」という大きな看板が中央高速道に出ています。
そして夜叉人峠の入り口の南アルプス市、そして西の新府などの桃の産地には随分と通ったものです。
桃の花は開花すると間引きのため摘花(てきか)します。摘花したあとの桃の枝には花がまばらにしか残っていないので淋しい風景になってしまいます。そこで摘花する前の桃畑を探してあちこちへ動き回ります。
摘花する前の桃畑に行くとピンクの雲の中に入ったようで、甘い桃の香りがして別世界に来たような気分になります。
自分で、「これが桃源郷だ!」と言いながら、何故かとてもロマンチックな気分に浸ります。
下の写真は2011年の4月に撮った山梨県の西の新府の桃源郷です。
桃源郷の初出は六朝時代の東晋末から南朝宋にかけて活躍した詩人・陶淵明(365年 - 427年)が著した詩『桃花源記 ならびに詩』です。(詩集では、『桃花源詩 ならびに序』という名前で,採録されることが多い。)
現在では『桃花源紀』(詩)よりは、その序文のほうがよく読まれている。
晋の太元年間(376年 - 396年)、武陵(湖南省)に川漁師の男がいた。ある日、山奥へ谷川に沿って船を漕いで遡ったとき、どこまで行ったか分からないくらい上流で、突如、桃の木だけが生え、桃の花が一面に咲き乱れる林が両岸に広がった。その香ばしさ、美しさ、花びらや花粉の舞い落ちる様に心を魅かれた男は、その源を探ろうとしてさらに桃の花の中を遡り、ついに水源に行き当たった。そこは山になっており、山腹に人が一人通り抜けられるだけの穴があったが、奥から光が見えたので男は穴の中に入っていった。
穴を抜けると、驚いたことに山の反対側は広い平野になっていたのだった。そこは立ち並ぶ農家も田畑も池も、桑畑もみな立派で美しいところだった。行き交う人々はみな微笑みを絶やさず働いていた。
男を見た村人たちは驚き話しかけてきた。男が自分は武陵から来た漁師だというとみなびっくりして、家に迎え入れてたいそうなご馳走を振舞った。村人たちは男にあれこれと「外の世界」の事を尋ねた。そして村人たちが言うには、彼らは秦の時代の戦乱を避け、家族や村ごと逃げた末、この山奥の誰も来ない地を探し当て、以来そこを開拓し、その一方、決して外に出ず、当時の風俗のまま一切の外界との関わりを絶って暮らしていると言う。彼らは「今は誰の時代なのですか」と質問してきた。驚いたことに、ここの人たちは秦が滅んで漢ができたことすら知らなかったのだ。ましてやその後の三国時代の戦乱や晋のことも知らなかった。
数日間にわたって村の家々を回り、ご馳走になりながら外の世界のあれこれ知る限りを話し、感嘆された男だったが、いよいよ自分の家に帰ることにして暇を告げた。村人たちは「ここのことはあまり外の世界では話さないでほしい」と言って男を見送った。穴から出た男は自分の船を見つけ、目印をつけながら川を下って家に戻り、村人を裏切ってこの話を役人に伝えた。役人は捜索隊を出し、目印に沿って川を遡らせたが、ついにあの村の入り口である水源も桃の林も見付けることはできなかった。その後多くの文人・学者らが行こうとしたが、誰もたどり着くことはできなかった。(終り)