



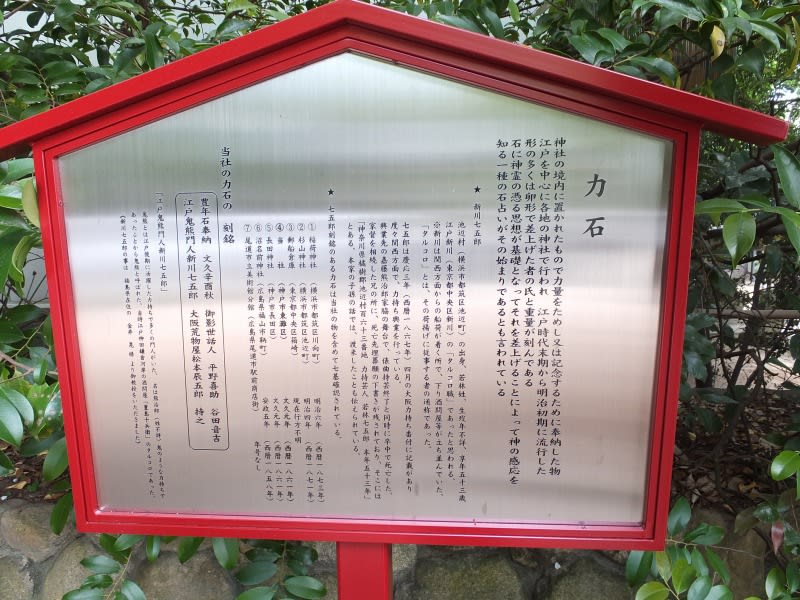

祭りの喧騒の後の静寂を題材にした川柳に「境内はこんなに狭い祭りあと」があります。
この川柳は居酒屋E“e”の女将が、神戸新聞文芸欄の川柳壇に投稿し特選に選ばれました。兼題は『祭り』でした。
弓弦羽神社の境内もだんじりの宮入宮出しの日は近隣の善男善女でぎっしりです。
☆2010年5月4日神戸御影郷の弓弦羽神社でダンジリの宮入・宮出しがありました。
この画像は13:30からの宮出しのシーンです。
040510Danjiri Festival@Kobe.wmv
☆以下は2009年5月5日に掲載しただんじりの宮入の画像です。
5月4日の10時半から七基の地車が東灘区の弓弦羽神社へ宮入しました。一昨年と同じくらいの人出のように思いましたが、整理の警察官の数は多くなっていました。見物人が増えているのでしょう。七つの地区の住民がそれぞれ地車を所有、維持して、こうして老若男女が参加して運行する!うちの氏神さんは大した伝統を持っているなあと嬉しくなります。




お兄さん、こけちゃったねえ!と声が聞こえました。



このだんじり(地車)は祭委員会のアナウンスによると、戦前から淡路島の名工により製作されてきたものだそうです。間違いなく人形浄瑠璃の発祥の地、淡路にはこのような工作物を全て製作可能な技術的文化的な伝統があるのでしょう。
「淡路」は「京の都から阿波の國へ至る道」の意味で、阿波路がいつか淡路と表記されるようになりました。阿波の國、徳島は戦国時代に御所の財務基盤を支えた“三好党”が出た、物成りのいい豊穣な土地柄で、昔から芸能、伎楽が盛んな所です。
♪全51枚の画像を掲載したアルバムはこちらから。スライドショーでどうぞ。
08年08月18日神戸新聞朝刊 文芸川柳欄
「境内はこんなに狭い祭りあと」
『選評』
祭も済んで、ひと気のなくなった神社の境内に一人立つ作者。ついさっきまで、ここは祭の熱気と喧騒と人いきれであふれていた。この狭い境内に、よくまああれほど多くの屋台や人間が詰め込まれていたことよ・・・。「祭の後の寂しさ・むなしさ」を詠んだ句はたくさんありましたが、この句は「寂しい」「むなしい」といった言葉を使わずに、そこはかとない寂寥感を出すのに成功しています。
日清のパイロット販売の冷凍商品。麵とかき揚げをレンジで解凍するところから始まります。一口たべてすぐ思いました。あぁ、これは東京の立喰い蕎麦屋の味そのままだと。東京勤務13年の間、外回りの営業部員としてどんなにお世話になったかわからない立喰い蕎麦屋の「かき揚げソバ」。現在は試験販売で2袋280円と言う半額の値段だったそうです。もし正式に販売商品にラインアップされるなら、これは常備品にしたい。東京へ行けば必ず食べるあの味の蕎麦が、神戸で食べられるんですから。
夜の酒の肴は棒ぎょうざ、鶴橋のキムチ、カボチャの煮物、フキ・厚揚げ・竹の子と鶏肉の煮物でした。

夜の酒の肴は棒ぎょうざ、鶴橋のキムチ、カボチャの煮物、フキ・厚揚げ・竹の子と鶏肉の煮物でした。






















