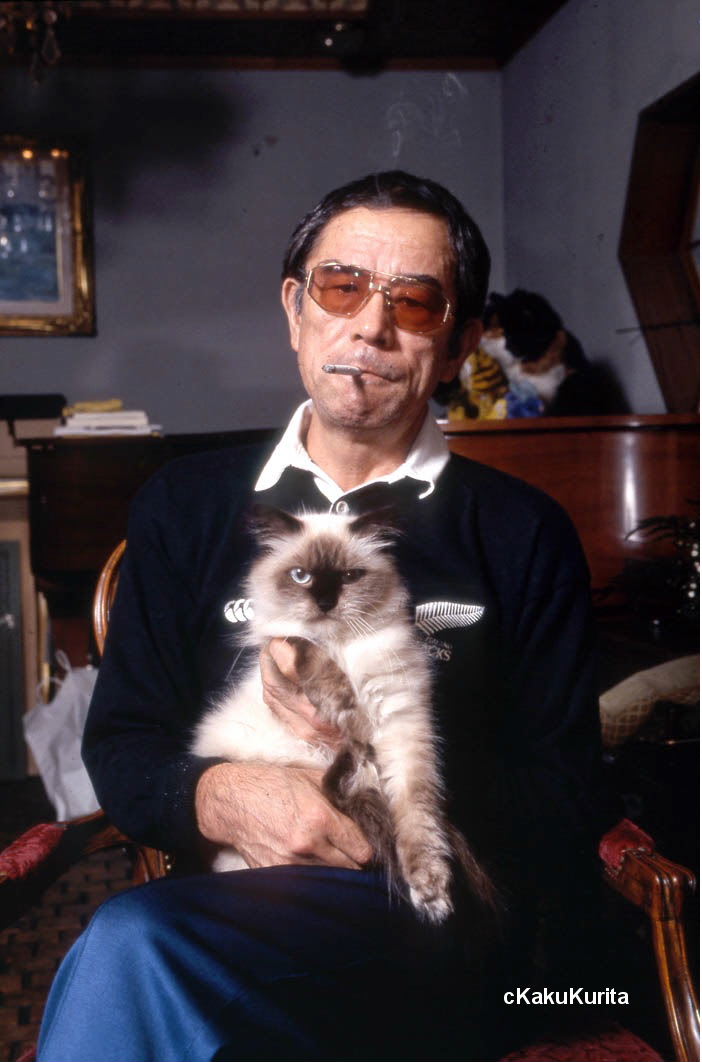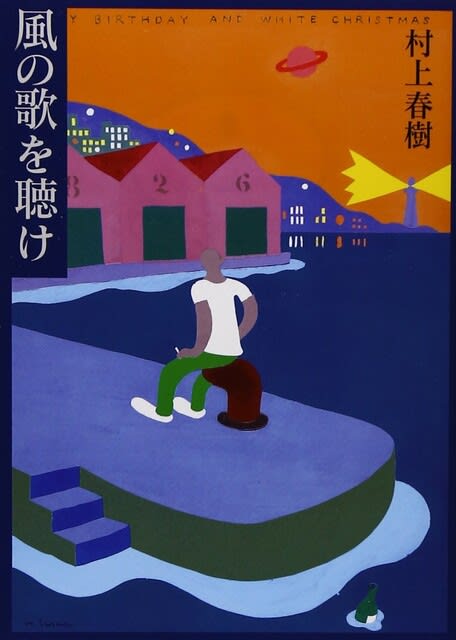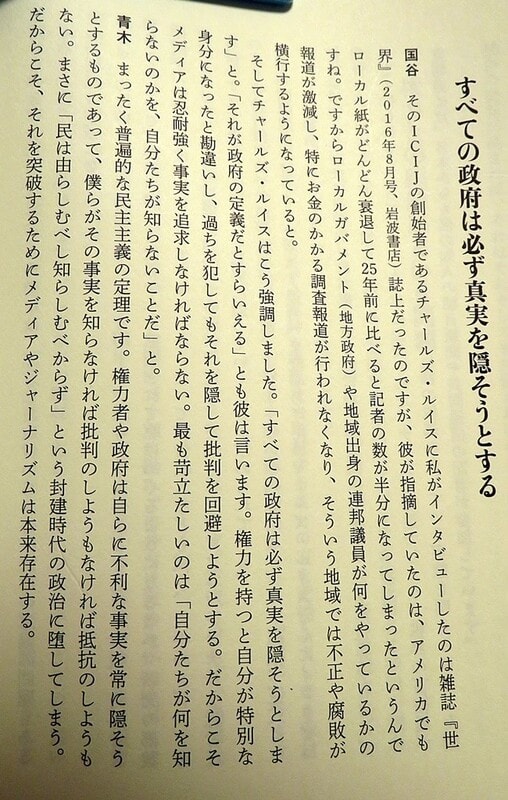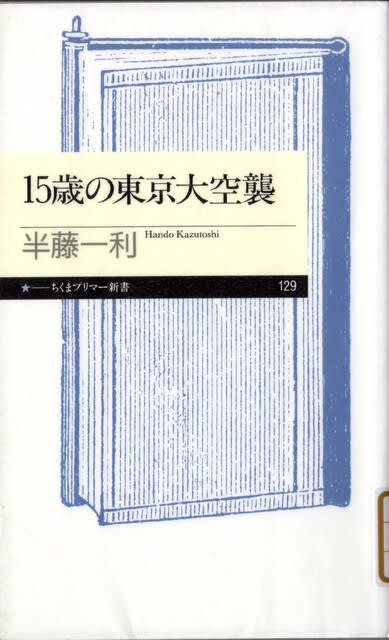もはや できあいの思想には倚りかかりたくない もはや できあいの宗教には倚りかかりたくない もはや できあいの学問には倚りかかりたくない もはや いかなる権威にも倚りかかりたくはない ながく生きて 心底学んだのはそれぐらい じぶんの耳目 じぶんの二本足のみで立っていて なに不都合のことやある 倚りかかるとすれば それは 椅子の背もたれだけ |
| 在日米軍:オスプレイ本土訓練通知 「怖い」市民ら不安 知事「いきなりとは何事だ」 /静岡 毎日新聞 2012年11月03日 地方版 御殿場市の米軍キャンプ富士などで今月、米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの低空飛行訓練が行われる計画が2日、東京都内で開かれた全国知事会議の席上明らかになった。初めて知らされた地元の市民からは、「オスプレイは怖い」「絶対安全という確認ができない」などと不安を訴える声が目立った。【樋口淳也、小玉沙織、野島康祐、西嶋正信】 同会議に参加していた川勝平太知事は、東京都内で毎日新聞の取材に応じ、「何の打診もなく、突然のことで驚いている。住民の意向さえも聞かずいきなりとは何事だ」と強く反発した。 御殿場市の若林洋平市長は「耳を疑うもの」と森本敏防衛相の突然の発表を批判し、国に対して発言に関する詳細な説明を要求した。さらに「仮にキャンプ富士への飛行訓練が示された場合は、第10次東富士演習場使用協定にのっとり、(地元)2市1町と(同演習場の)地元権利者団体などと一体となり、協議を進めざるを得ない」と述べた。 オスプレイの飛行訓練について情報収集を進める松井隆・県民生活局長は、「南関東防衛局に問い合わせたが、『本省から情報がない』と言われた。こちらとしては、県民の不安を払拭(ふっしょく)できるよう、国の責任で2市1町と地権者に丁寧な説明をしてもらいたい」と話す。 地元住民は複雑な心境だ。同市西田中の自営業、山崎勝正さん(78)は、「オスプレイは事故を繰り返している。絶対安全だと確認できればいいが、訓練は時期尚早だ」と反対の立場。一方で、同市中山の自営業の男性(64)は、「沖縄以外でも応分の負担を受け入れざるを得ない」と指摘した。 ☆【わが空はわが空ならず秋の空】 旧軍の戦闘機乗りで敗戦後、日本航空のパイロットになった人が詠ったという伝説の俳句。 アメリカの占領状態が67年間続く日本の空。 臥薪嘗胆、捲土重来、次は勝つ、の気概を持つ「官、財、政、学、マスコミ」が戦後67年間の間、この国に存在したことはない。 しかし裏を返せば、この67年間、国家の正規軍が他国民を戦争の名目で殺害したことのない国連加盟国の中の大国は、唯一日本だけである。 国連の常任理事国であるアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの五国は1945年以降も、それぞれ国の正規軍がなんらかの名目で、他国民を戦闘で殺してきた。 自国の空と陸を自由にアメリカに使われ、裁判権を渡すなど不平等な地位協定を結んだ吉田茂と、その忍びの者を勤めた白洲次郎は、それらと引き換えに憲法九条を維持し、ならずものの国にならないで来たこの国への自らの働きと貢献を、墓石の下で自負しているだろうか?それとも忸怩たる思いをしているのだろうか? |
| 2012/11/3 12:02 九州電力は2日、管内の企業や家庭に今冬の節電を要請すると発表した。暖房用の電力需要が見込まれる一方、原子力発電所6基すべてが停止しており、電力供給力が落ちた状態が続いているため。ただ節電が定着してきたうえ、他の電力会社からの電力融通も見込めるため、数値目標は設定しない。今夏、万一の供給不足に備えて準備した計画停電も実施しないとしている。 節電要請期間は12月3日~2013年3月29日(12月31日~1月4日を除く)の平日で、時間帯は午前8時~午後9時。2日、記者会見をした平田宗充取締役は「生活・健康や経済活動に支障のない範囲で節電に協力をお願いしたい」と述べた。九電は火力・水力発電所の補修による停止を暖房用需要が増える冬にしないで済むよう点検時期の前倒しなどで対応している。 今冬の気温が平年並みで推移した場合、2月の最大電力需要は1471万キロワットと想定。昨冬並みの厳しい寒さとなったケースでは1537万キロワットを見込む。一方、最大供給力は1584万キロワットあり、予備率は3.1%を確保できる。他の電力会社も今冬の予備率に余裕があり、さらなる電力融通も見込めるという。 |