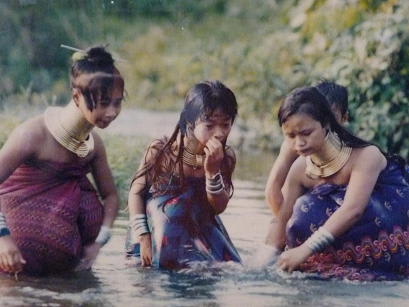(2月 首都モガディシオのAU部隊 “flickr”より By AU/UN_IST http://www.flickr.com/photos/au_unistphotoarchive/6222535967/)
【「軽蔑にしか値しないこういった連中はとても人間とは言えない」】
事実上の無政府状態が続くソマリアの隣国ケニアでは、ソマリア武装勢力によって外国人が拉致される事件が相次いでいます。
この1か月の間にも、英国人女性とフランス人女性が、それぞれ別のビーチリゾートで誘拐されており、ケニアの観光産業は大きな打撃を受けています。
また13日には、ケニアのダダーブ難民キャンプで、支援活動を行っていたスペイン人女性2人が銃で武装したグループに連れ去られています。ダダーブ難民キャンプは世界最大の難民キャンプで、主にソマリアからの難民45万人が生活しています。【10月17日 AFPより】
今月1日に拉致されたフランス人女性が武装勢力による拘束中に死亡しました。
****ソマリア武装勢力に誘拐された仏人女性が死亡、仏外務省****
フランス外務省は19日、ケニア東部ラム島近くのリゾート地・マンダ島でソマリア武装勢力に誘拐されていたフランス人女性が死亡したと発表した。
死亡したのはマリ・デデューさん(66)。今月1日、10人ほどの武装集団がデデューさんを拉致し、誘拐を阻止しようとしたケニア海軍と戦闘を繰り広げたのち、ボートでソマリアに連れ去った。
外務省によると、解放交渉の窓口役となった人物から死亡の知らせを受けたという。また、死亡の経緯は不明としながらも、デデューさんの健康悪化が一因との見方を示した。デデューさんは数年前の事故で車いす生活を余儀なくされている上、末期のがんを患っており、数時間ごとに薬を飲む必要に迫られていた。(後略)【10月20日 AFP】
*******************************
ソマリア武装勢力は、死亡したマリ・デデューさんの遺体と引き換えに身代金を要求してきたと報じられてましす。こうした武装勢力に対し、サルコジ仏大統領は「このような言語道断な行為を働く者は、野蛮人の集団以外の何者でもない」と怒りをあらわにしています。
****ソマリアの武装勢力、仏人女性の遺体と引き替えに身代金を要求****
フランス政府は20日、仏人女性マリ・デデューさん(66)をケニアからソマリアに連れ去って拘束中に死亡させたソマリアの武装勢力が遺体と引き替えに身代金を要求してきたとして、この武装勢力を「野蛮人」と呼んで強く非難した。
仏政府は19日、デデューさんは1日、ケニアで武装勢力によってソマリアに連れ去られ、拘束されている間に死亡したと発表していた。
デデューさんは、数年前の事故で車いす生活を余儀なくされていたうえ、がんを患っていた。死因は、武装グループがデデューさんに薬を与えなかったためだとみられる。
ジェラール・ロンゲ国防相は、ニュースネットワークi-TELEに、「病気を抱えた高齢女性を誘拐し、薬も与えず敗血症で死に至らせた。そのうえ、彼女の遺体を売りつけようとしている!軽蔑にしか値しないこういった連中はとても人間とは言えない」と語った。
仏西部の汚水処理場を訪問していたニコラ・サルコジ大統領も、「このような言語道断な行為を働く者は、野蛮人の集団以外の何者でもない」とAFPに語った。
その一方で、ロンゲ国防相は、誘拐集団はソマリアの名を汚す例外的な少数派のごく小規模なグループだとして、軍事攻撃を加える考えはないと語った。
仏政府は、無条件でデデューさんの遺体を即時返還するよう、武装グループに要求している。【10月21日 AFP】
*******************************
【アメリカのトラウマ】
“誘拐集団はソマリアの名を汚す例外的な少数派のごく小規模なグループ”というのは、フランスとして軍事攻撃は行わない弁解みたいな発言です。
ソマリアでは、イスラム過激派組織アルシャバブが、最近首都モガディシオからは撤退したものの、依然としてソマリア国土の多くを実効支配しています。また、一連の誘拐事件にはアルシャバブのほか、海賊グループの関与も指摘されています。
アルシャバブは国連や欧米系NGOの活動を「スパイ」と見なして活動を禁じており、干ばつと飢饉に苦しむソマリアへの国際援助の障害となっています。
ソマリアでは90年代前半に国連PKOが展開されていましたが、映画「ブラックホーク・ダウン」でも描かれているように、93年、民兵のロケット弾攻撃により米軍単独作戦中のヘリ2機が撃墜され、この乗員救出に向かった米軍は激しい市街戦で大きな犠牲を出しました。
事件後、米兵の遺体が裸にされ市内を引きずりまわされている映像はアメリカ国内に大きな衝撃を与え、厭世感を強めたアメリカはソマリアから撤退しました。95年には国連PKOも失敗し撤退しました。
このトラウマを抱えるアメリカは、ソマリアのその後の無政府状態にもかかわらず、これに直接介入することは避けています。
そのかわり、2006年には、ソマリア国境でソマリ族の分離独立運動を抱えるエチオピアが、アメリカの支援のもとでソマリアに侵攻し、全土を掌握しました。
しかし、ソアリア国内の反エチオピア感情が強いことがあって、エチオピアもアフリカ連合にあとを任せる形で09年初頭までに撤退しました。
【「アルシャバブのいるところならどこであれ攻撃を行う」】
今度は、一連の外国人誘拐の舞台となっている、やはりソマリアの隣国にあたるケニアが、ソマリアに軍事進攻しています。
****ケニア、誘拐頻発でソマリア進攻 過激派、報復テロ警告****
ソマリア国境に近いケニア東部で外国人の誘拐事件が相次いだためケニア軍がソマリア南部に進軍、同国を拠点とするイスラム過激派組織アッシャバーブとの間で緊張が高まっている。アッシャバーブは軍が撤退しなければ、ケニア国内でテロを行うと脅迫している。(中略)
ケニア政府は一連の誘拐事件をアッシャバーブの犯行と断定して領土保全と被害者保護を理由に16日に約400人の部隊と戦車などをソマリア南部に派遣した。難民流入を防ぐため国境警備を強化する狙いもあるとみられる。アッシャバーブは関与を否定しているが、ソマリア暫定政府はケニア軍と協力してアッシャバーブの拠点を攻撃する方針を表明している。
アッシャバーブは国際テロ組織アルカーイダとの連携を表明し、ソマリア中南部の多くを実効支配。今年8月、首都モガディシオから撤退したが、今月4日にはモガディシオで自爆テロを起こし80人以上を殺害した。モガディシオでは18日にも、車を使った自爆テロが起き、少なくとも6人が死亡。ケニアのハジ国防担当相らがソマリア暫定政府幹部らと会談するため訪れていたときで、アッシャバーブの犯行とみられる。
アッシャバーブは「ケニア軍が撤退しない場合はケニアを攻撃する」と脅している。ソマリアには1992年に米海兵隊が派遣されたが、死傷者が続出して撤退。2006年にはエチオピアが軍事介入したが、反エチオピア感情が高まり、撤退している。【10月20日 産経】
***************************
世界の警察官を自任するアメリカも直接介入したがらない、アフリカ連合のPKO活動も十分に機能していないソマリアに、自国でのテロ激化のリスクを犯してまでケニアが単独介入する意図も、また、どこまで介入する気なのかもよくわかりません。
介入意図については、単に“外国人の誘拐事件が相次いだため”というだけではないでしょう。アメリカとの関係が強いケニアですから、アメリかの要請を受けたもののようにも思えます。
拉致被害にあっている欧州各国からの働きかけもあるのでしょうか。
規模については、ケニアとしてもあまり深入りはしない、限定的な侵攻作戦ではないでしょうか。
ただ、ケニアは、ソマリア難民49万8000人近くを抱えています。1日当たりの到着難民数は、従来の1500人から減少しているとはいえ1000〜1200人とも言われています。
ケニアはソマリア難民がこのままケニア国内に定着してしまうことを懸念しており、難民が帰国できる状況を早期に作り出したいのも事実でしょう。
“AP通信によると、ソマリアでは17日、ケニア軍部隊が戦車や装甲車でアル・シャバブの拠点に向けて移動しているが、大規模な武力衝突は起きていない模様だ。アル・シャバブが既に敗走したとの情報もある。”【10月17日 読売】
また、“ケニアのジョージ・サイトティ国内治安担当大臣は15日、アルシャバブを「敵」と呼び、「アルシャバブのいるところならどこであれ攻撃を行う」と述べていた。” 【10月17日 AFP】とのことです。
【無政府状態が続くソマリア情勢に転機?】
一方、国際支援をアルシャバブが妨害し、深刻な食糧危機に見舞われているソマリアに、アルシャバブを支援する国際テロ組織アルカイダが支援物資を送っているそうです。
首都モガディシオを撤退する状況となっているアルシャバブについては、“内部抗争や資金の欠乏、大衆支持の低下などによって、本格的な戦闘を断念せざるをえなくなったのではないか”との指摘があります。
****アルカイダ、食糧危機のソマリアを支援 米分析機関****
米国のテロ情報分析機関インテルセンターは14日、国際テロ組織アルカイダが、深刻な食糧危機に見舞われているソマリアに支援物資を送っていることを明らかにした。
同国のイスラム過激派組織アルシャバブとの緊密な関係を誇示し、ソマリア国民の間に支持基盤を確立する目的とみられる。支援物資の配給にあたっては、華々しい式典が開かれたという。
各援助団体によると、治安が悪化したソマリアでは、食糧や医薬品は武装勢力に強奪されるうえ、援助団体の職員も誘拐される危険があるため、定期的な支援物資の配送はほとんど不可能な状況だという。
アルシャバブは首都モガディシオで4年間にわたって暫定政府軍との攻防を展開してきたが、8月に突如、モガディシオに持っていた拠点のほとんどを放棄した。だが、依然としてソマリア国土の多くは、アルシャバブが実効支配している。
ソマリア情勢のアナリストらは、政府転覆に失敗したアルシャバブは内部抗争や資金の欠乏、大衆支持の低下などによって、本格的な戦闘を断念せざるをえなくなったのではないかと分析している。【10月15日 AFP】
*******************************
「国民は家にこもって雨を待つのだ。外国人のやっている難民キャンプには行ってはならん」(アルシャバブ広報担当)という、アルシャバブの住民無視の姿勢は住民の反発を買っています。
“ソマリアの食糧危機が深刻化する中、国際社会の支援を拒否し続けたアルシャバブは急速に住民の支持を失っている模様で、約20年間にわたって無政府状態が続くソマリア情勢は転機を迎えている。”
ケニアのソマリア侵攻も、こうした情勢変化を睨んでのことでしょう。