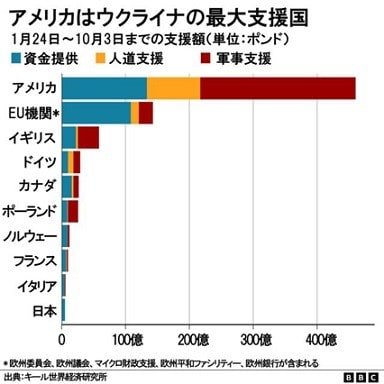(【11月10日 NHK)】
【出生数 予測より8年早く80万人割れ】
今更の話ではありますが、日本の少子化が止まりません。
年間の出生数は、第1次ベビーブームにあたる1949年には最多の269万超を記録しましたが、2016年には100万人を下回り、今年は80万人を切ると推測されています。
単に減少しているだけでなく、近年の減少速度が国が予測していたペースを遥かに凌ぐものになっています。
****ことしの出生数 初めて80万人下回るか 国の予測より8年早く****
1年間に生まれる子どもの数を示す「出生数」について、大手シンクタンク「日本総研」はことし全国でおよそ77万人と、国の統計開始以降、初めて80万人を下回る見通しになったとする推計をまとめました。
ことし80万人を下回れば国の予測よりも8年早く、少子化が想定を上回るペースで進んでいることになります。
ことし80万人を下回れば国の予測よりも8年早く、少子化が想定を上回るペースで進んでいることになります。
日本総合研究所は厚生労働省が公表していることし1月から8月までに生まれた子どもの数などをもとに、1年間の出生数を推計しました。
それによりますとことしの出生数は全国でおよそ77万人で、前の年から4万人余り、率にして5%程度減少し、国が統計を取り始めた1899年以降で初めて80万人を下回る見通しになったということです。
それによりますとことしの出生数は全国でおよそ77万人で、前の年から4万人余り、率にして5%程度減少し、国が統計を取り始めた1899年以降で初めて80万人を下回る見通しになったということです。
厚生労働省によりますと、出生数は1970年代半ばから減少傾向が続いていて、ことしも国内で生まれた外国人も含んだ8月までの速報値で52万人余りと、前の年より2万7000人余り減少しています。
国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した予測では、出生数が80万人を下回るのは8年後の2030年となっていて少子化が想定を上回るペースで進んでいることになります。
推計を行った日本総合研究所は少子化の進行について、新型コロナの感染が拡大する中、結婚の件数がおととし、去年と、減少が続いていることが関係していると分析しています。(中略)
国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した予測では、出生数が80万人を下回るのは8年後の2030年となっていて少子化が想定を上回るペースで進んでいることになります。
推計を行った日本総合研究所は少子化の進行について、新型コロナの感染が拡大する中、結婚の件数がおととし、去年と、減少が続いていることが関係していると分析しています。(中略)
結婚の件数も減少傾向 来年以降も低下局面か
厚生労働省によりますと1年間の結婚の件数も2000年代から減少傾向が続いています。
最近では、2019年はいわゆる「令和婚」で前の年から増加し、59万9007組となりましたが、2020年は前の年と比べて7万3500組減少して52万5507組に、2021年は前の年から2万4369組減少して50万1138組と、戦後、最も少なくなりました。
また、国立社会保障・人口問題研究所が5年に1回程度行っている出生動向基本調査では、コロナ禍の2021年の時点で「一生結婚するつもりがない」と回答した人が18歳から34歳までの世代で男女とも増加していることから、日本総合研究所は結婚の件数が今後も減少していくことが懸念されるとしています。
最近では、2019年はいわゆる「令和婚」で前の年から増加し、59万9007組となりましたが、2020年は前の年と比べて7万3500組減少して52万5507組に、2021年は前の年から2万4369組減少して50万1138組と、戦後、最も少なくなりました。
また、国立社会保障・人口問題研究所が5年に1回程度行っている出生動向基本調査では、コロナ禍の2021年の時点で「一生結婚するつもりがない」と回答した人が18歳から34歳までの世代で男女とも増加していることから、日本総合研究所は結婚の件数が今後も減少していくことが懸念されるとしています。
専門家「今後10年間は対策するうえで特に重要な期間」
推計を行った日本総合研究所の藤波匠 上席主任研究員は、ことしの出生数が80万人を下回る見通しになったことについて「2015年の出生数は100万人を超えていた中、わずか7年で20%以上減少してしまうことになる。少子化が進むと国内の社会保障の問題や経済成長などにも大きな影響があると考えられ、対策は喫緊の課題だ」と指摘しています。
そのうえで「1990年代の出生数は120万人程度と比較的安定していた時期で、その年代の子どもたちが20代から30代となってちょうど結婚や出産の時期を迎えているので、今後の10年間は少子化対策に取り組むうえで特に重要な期間になるのではないか」と指摘しています。【11月10日 NHK】
そのうえで「1990年代の出生数は120万人程度と比較的安定していた時期で、その年代の子どもたちが20代から30代となってちょうど結婚や出産の時期を迎えているので、今後の10年間は少子化対策に取り組むうえで特に重要な期間になるのではないか」と指摘しています。【11月10日 NHK】
******************
出生数、ひいては人口動向は経済政策、社会保障制度など国の全ての計画の根幹をなすものです。
その予測において、2017年に80万人を切る年を13年後の2030年に予測していたのが、実際には5年後の2022年・・・・現実において想定を超えるものがった面もあるのでしょうが、予測事態が“(異様に)甘い”というか、“(根拠なき)期待”に近いものだったというか、“(政治的に)不都合な現実”から目を背けようとしていたというか・・・そんな面もあったのでは。
結婚や出産の時期にある者の数が比較的安定している今後10年間の対応が重要・・・・昨今の政治情勢を見ると今後10年の間に抜本的改革がなされるとはほとんど期待できません。
その10年を過ぎたら、母数自体がどんどん少なくなっていくので、どうあがいても出生数は回復しないという時期をを迎えます。
【減っていない既婚女性の出生率 出生数減少を止めるためには未婚化・婚外子への対応が必要】
減り続ける出生数の一方で、「出生率」に関して、私的には“以外”な数字も。既婚女性の出生率は変わっていないそうです。
****少子化傾向が続く中でも、結婚した夫婦の出産志向は変わっていない****
<事実婚や未婚での子育ても支援する、多様な家族像に配慮した環境づくりが必要>
少子化の進行が止まらない。コロナ禍はそれに拍車をかけており、出生数は2019年が86万人、2020年が84万人、2021年が81万人と、ガクンガクンと減っている。戦後間もない頃、年間250万人以上の子どもが生まれていた時代とは、隔世の感がある。
だが出生率という指標を計算してみると、あまり知られていない事実が浮かび上がる。全人口ではなく、出産年齢の既婚女性をベースにした出生率だ。総務省の『国勢調査』から25〜44歳の有配偶女性の数を拾うと、1990年では1403万人、2020年では815万人。年間の出生数は順に122万人、84万人(厚労省『人口動態統計』)。割り算で出生率を出すと、以下のようになる。
▼1990年......122/1403 = 8.7%
▼2020年......84/815 = 10.3%
▼2020年......84/815 = 10.3%
出産年齢の既婚女性をベースとした出生率は、この30年間で上昇している。結婚した夫婦に限って見てみると、出産志向は変わっていないようだ。国の出生数が減っているのは、出産年齢の既婚女性の絶対数が少なくなっていることによる。(中略)
それは、出生順位の統計からもうかがえる。出生児のうち第3子以降の割合は1990年では18.9%、2020年は17.8%で、大きな変化はない(厚労省『人口動態統計』)。既婚の夫婦の中では、子を何人産もうという意向も変わっていないようだ。
少子化の最大の要因は出産年齢の女性の減少だが、その次に大きいのは未婚化だ。これに歯止めをかけようと、各地の自治体は出会いの場を設けるなどして、何とか婚姻を増やそうとしているものの、あまり成果を上げていない。そういう取り組みもいいが、どういうライフスタイルを選ぼうと、子を産み育てられる環境を構築すべきではないだろうか。
日本では、法律婚をした夫婦を前提に育児支援等の制度ができている。(中略)だが、諸外国では違う。<表1>は、出生児のうち婚外子が何%かを国別にみたものだ。

日本は2.3%で韓国に次いで低いが、アメリカは39.6%で、50%を超える国も珍しくない。事実婚で子を授かる人や、未婚で子を産み育てる人もいる。
日本でも未婚の母が増え、配偶者との離別者や死別者と同じく、税の控除を受けられるようになった。性的マイノリティーのパートナーシップを認める自治体も増えてきた。しかし、そうした人たちが子育てをしやすい(できる)環境になっているかというと、そうとは言えないだろう。
結婚と出産を結びつける慣行を見直すこと、多様な家族像に思いを馳せること。今後の少子化対策の上では、常に念頭に置く必要がある。【11月2日 舞田敏彦氏 Newsweek】
*******************
外国では婚外子が多いことはかねてより指摘されている点です。
日本の場合、政府・与党の考える“あるべき家族の姿”あるいは“美しい日本”に馴染まないせいか、婚外子への配慮が薄く、結果的に人口減少という国家衰退の原因ともなっています。
【未婚化が進む背景に「男は仕事、女は家事」という日本のジェンダー意識から生じる結婚生活における女性の負担の大きさが】
“あるべき家族の姿”の中核にあるのが「男は仕事、女は家事」という日本のジェンダー意識です。
先に見たように、日本の出生数減少の大きな要因として「未婚化」がありますが、未婚化が進む背景に「男は仕事、女は家事」という日本のジェンダー意識から生じる結婚生活における女性の負担の大きさがあるようにも。
****家事分担を妨げる「男は仕事、女は家事」という日本のジェンダー意識****
<男性の労働時間が減っても、その分だけ家事をする時間が増えるとは限らない>
先週の記事「日本の男性の家事分担率は、相変わらず先進国で最低」で見たように、日本の男性の家事分担率は国際的に見て低い。
OECDの統計によると、15~64歳男性の1日の家事等の平均時間は41分で、女性は224分(2016年)。男女の合算に占める男性の割合は15.4%でしかない。他国の同じ数値を計算すると、アメリカは37.9%、スウェーデンは43.7%にもなる。
日本の男性は、仕事時間がべらぼうに長いからではないか、という意見もあるだろう。同じくOECDの統計によると、日本の15~64歳男性の1日の平均仕事時間は452分で、アメリカの332分、スウェーデンの313分よりだいぶ長い。家事等の平均時間は順に41分、166分、171分と逆の傾向だ。
以上は3つの国のデータだが、より数を増やして、仕事時間と家事時間の関連を可視化してみる。横軸に仕事時間、縦軸に家事等の時間をとった座標上に、OECD加盟の30カ国のドットを配置すると<図1>のようになる。

日本は仕事時間が長く、家事等の時間は短いので右下にある。対極にあるのは、北欧のデンマークだ。傾向としては、仕事時間が長いほど家事等の時間は短い、両者はトレードオフの関係にあると言えなくもない。
仕事時間が短ければ、自宅にいる時間も長くなり、家事や育児にも勤しむようになる。いたって自然なことだ。政府の『男女共同参画白書』でも、男性が家事・育児・介護等に参画できるよう、長時間労働を是正する必要があると言及されている。
だが、事はそう単純ではない。定時に上がっても、自宅ではなく酒場に足が向く男性もいるだろう。コロナ禍以降、在宅勤務が増えているものの、夫が家事をしないのは相変わらずで、「大きな子どもが1人増えたようだ」という妻の嘆きもSNS上で散見される。仕事時間を減らせば万事解決となるかは分からない。
<図1>は国単位のデータだが、個人単位でみると仕事時間と家事時間の関連はどうなっているか。既婚男性を仕事時間に応じて3つのグループに分け、家事時間の分布を比べてみる。<図2>は、結果をグラフにしたものだ。

男性を見ると、仕事時間の多寡に応じて家事時間が大きく変わる傾向はない。小さな差はあるものの、どのグループも家事時間は週10時間未満が大半だ。
対して女性は、仕事時間に関係なく、家事時間が週20時間以上の人が多い。サンプル数が少ないが、一番右側のグループ(仕事週50時間以上、家事週20時間以上)の負荷は相当なものだろう。
未婚化が止まらないが、結婚生活の負荷を女性が認識し出したこともあるだろう。2021年の国立社会保障・人口問題研究所の『出生動向基本調査』によると、女性が結婚相手に求める条件として最も多いのは「人柄」だが、それに次ぐのは「家事・育児への姿勢」だ。
2015年との比較でいうと、この項目を重視する女性の割合が増えている(57.7%→70.2%)。対して、職業や経済力を重視するという回答は減っている。
女性の社会進出を促し、かつ未婚化・少子化に歯止めをかける上でも、男性の「家庭進出」が求められるが、長時間労働の是正だけでは足りない。意識の啓発も必要になってくる。家庭内での性別役割分業を子どもに見せることは、既存のジェンダー構造を次代にまで持ち越す恐れがあることをしっかりと自覚しなければならない。
また日本では、「男は仕事、女は家事」という性役割分業で社会が形成されてきた経緯があるので、家事に求められるレベルが高くなってしまっている(一汁三菜の食事、洗濯物は綺麗にたたむなど)。外国人が驚くところだ。これなども、男性の家事分担を妨げている。共稼ぎが主流になっている今、見直すべきだろう。【10月26日 舞田敏彦氏 Newsweek】
***********************
上記記事でもスウェーデンなど北欧は、男性の仕事時間が比較的短く、家事労働時間が長く、結果的に男性の家事分担率が高くなっている姿が示されていますが、同様の現象を示すフィンランドに関する記事も。
****フィンランド、労働時間が初めて男女平等に****
フィンランド統計局は10日、国民が家事労働と有償労働に費やした時間の合計が、昨年初めて男女で等しくなったと発表した。
10歳以上の人口の有償労働と家事労働を合わせた1日の総労働時間はこれまで、女性の方が長かった。統計局は、男性の有償労働時間が減少し、家事労働時間が増加したと説明。特に男性が育児に費やす時間が大きく増えたとし、その要因としては文化の変化に加え、男性向け育児休暇制度の拡充があるとした。
ただ、有償労働の時間は依然として男性が女性よりも1日平均30分長かった。 【11月11日 AFP】
*******************
日本の出生数の減少に歯止めをかけようとすれば、前述のような多様な家族形態を認め、婚外子の扱いを変更、そして「男は仕事、女は家事」という日本のジェンダー意識を変えることで女性の結婚生活の負担感を軽減することが必要と思われます。
それでもカバーできない人口減少は、外国人労働者・移民に関して本腰を入れて取り組むことでフォローすることも。
しかし、上記のいずれも政府・与党の考える“あるべき家族の姿”“あるべき社会の姿”には馴染みません。
ということは、日本を待ち受ける未来は・・・。
【日本以上に深刻な韓国の少子化】
日本より深刻なのが韓国。韓国から見ると、日本の現状はまだましなものに見えるようです。
(ただし、下記記事で“日本の出生率が低水準ながら徐々に上昇している”とありますが、これは事実誤認。
確かに日本の合計特殊出生率は2005年の1.26から2015年の1.45まで上昇しましたが、その後はまた減少しています。2021年は1.30)
****韓国を逆転、日本が低出生率の罠を脱出できた理由は?=韓国ネット「子どもなんて生まないほうが賢明」****
2022年11月7日、韓国メディア・韓国経済は「減っていく人口、消滅する韓国」と題したシリーズ記事を掲載し、「日本が低出生率の罠(少子化の罠)を脱出した秘訣(ひけつ)」を分析している。
日本の人口減少が始まったのは11年(国連統計基準)で、前年の1億2813万人から1億2808万人となった。以来、昨年まで減少が続いている。記事は「日本経済が30年間足踏み状態にある理由の一つに人口停滞・減少が挙げられる」と指摘した。
日本の合計特殊出生率は1975年に2.0人を下回ってから下落傾向となり、80年代後半には1.5人台となった。2005年には1.26人まで落ち込んだが、15年に1.45人に上昇。昨年は1.30人を維持した。国連は日本の出生率は小幅に上昇し60年代には1.5人まで回復すると予想している。
対照的に、韓国は出生率が世界的に例を見ないほど下落している。2000年までは1.48人で日本(1.37人)を上回っていたが、18年は0.98人と、世界で初めて1人を割り込んだ。昨年は0.81人で、今年4~6月期は0.75人まで下落した。
日本の出生率が低水準ながら徐々に上昇しているのに比べ、韓国の出生率は下落し続けている理由について、記事は「日本国内では少子化克服政策を長期間、持続的に進めてきた結果だ」と伝えている。
日本は1990年に少子化対策に着手。継続的に予算を投入してきた。今年はこども家庭庁を新設している。一方、韓国は2006年にようやく対策に乗り出したが、権限のない低出産高齢社会委員会という組織が置かれただけとなっている。
記事はこれまでの日本の政策を詳しく説明し、「1990年から初めた少子化対策の効果が2006年から現れている。15年かかったことになる」と指摘している。
韓国のネットユーザーからは
「不動産価格、教育費、経歴断絶問題など社会的環境も、新婚夫婦に好意的ではない。だから若い夫婦が2人以上の子を持とうと思わないんだ」
「結婚と出産は女性1人でするものではない。低賃金、物価高、不動産価格による未来への不安から、男性は結婚を恐れている」
「不動産価格と物価が安定しないと出生率は上がらないと思う」「育児戦争が終わったら教育問題、入試地獄、就職難、住居問題。子どもを育てようなんて思えるわけがない」
「政策だけの問題ではない。共稼ぎなのに家事、育児の負担は女性にばかりある」「経済のせいにするのはどうなのか。1960年代、70年代は経済環境が良かったから出生率が高かったというのか?」
「少子化と非婚は世界的な現象だ。韓国の出生率が特に低いのは婚外出産がほとんどないからだろう。婚外出産に対する認識から変えるべきだ。家族と性に関する考えが昔も変わっていない」「子どもを欲しがっている不妊の夫婦もものすごく多いよ。彼らへの支援を手厚くするべきだ」
「少子化で困ってるのは国だけじゃないか?個人にとっては、だから何?って感じ。コメントを見ていると、子どもなんて生まないほうが賢明だと思うよ」「まずは生まれた子どもたちをしっかり守らないとね」など、さまざまな声が寄せられている。【11月11日 レコードチャイナ】
*****************
問題の立て方が違います。「どうして日本は韓国よりも・・・」ではなく、「どうして日本も韓国も・・・」という問題認識を持つべきでしょう。
韓国は、婚外子への認識、「男は仕事、女は家事」というジェンダー意識など、日本とよく似た社会です。結果、よく似た少子化に苦しむことに。