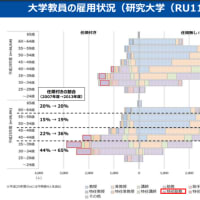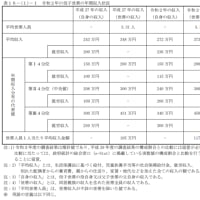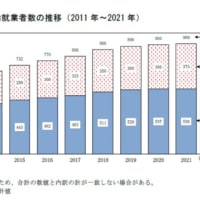日曜日の朝、FMを聞いていたら2030年に「住宅における省エネ基準が変更」という話があった。
TFM:日曜まなびより「買う前に知ろう!家選びの新しい基準」
しかもこの「省エネ基準」の対象が、戸建て住宅だけではなくマンション等にも適用されるという。
この「省エネ基準」の第一弾が今年4月にスタートするという。
ということは、現在建設中のマンションなどもこの「省エネ水準」に達していなければ、意味がないということになる。
戸建て住宅に比べ、建設期間の長いマンション等は認可が下りてから、完成までに時間がかかることを考えると、今年完成予定のマンション等はこの「省エネ水準」に達しているのだろうか?と、フッと疑問にかんじたのだ。
この「新しい省エネ水準」は、既に2030年に引き上げられる事が決まっている為、現在建設中のマンション等も2030年の水準(=ZEH水準)を満たさなくては意味がない、ということになる。
高気密・高断熱というだけではなく、循環型のエネルギーシステムを組み込むような建築物ということになるようなので、マンション等は建設時点で設備ハードルが随分高くなるのでは?と、想像することができる。
このような行政主導による「住まいの在り方」の変化に、今の住宅は追いついているのだろうか?と、思ったのだ。
特に都市部で見られるような、タワマンと呼ばれる高層マンション等は、このような循環型のエネルギーシステムを組み入れること自体、難しいのでは?という気がしている。
理由の一つは、高層マンションそのものが1棟当たりの戸数が多い、ということが挙げられる。
戸数が多いということは、それだけの世帯数の「省エネ化」を考える必要がある、ということになる。
太陽発電システムを導入するにしても屋上の免責は限られており、全戸数分の発電が賄えるとは思えない。
それをカバーするために、「ペロブスカイト太陽発電」のような、これまで発電場所として疑問視されていたような場所での発電システムの研究が進められているのだろう。
積水科学:国内初、ペロブスカイト太陽電池を建物外壁に設置した実証実験開始
このような行政側の動きに対して、住宅を購入する側はどれほどの情報を得ているのだろうか?
上述したFM番組の冒頭のように、生活者にはそれらの情報が届いていないような気がするのだ。
と同時に、時代の変化とともに住まいの在り方も変わるのであれば、住宅ローン完済後のことまで考える必要がある、ということになる。
戸建てであれば、費用面の問題は別にして、時代に即した住まいを立てることは可能だが、タワマンのような高層マンションでは、簡単な事ではない。
「建ってしまったものは、しょうがない」では済まない時代がやってきている、ということなのだ。
現在問題になっている「空き家問題」だが、戸建て住宅であれば取り壊したりすること自体は、難しいことではない。
だが、高層マンションとなるとどうなのだろう?
そのような事を考えると、都市部を中心に乱立する高層マンションという建物自体が、(特にディベロッパーにとって)リスクのような気がしてくる。
最新の画像[もっと見る]