
小学3年生の女の子たちと
空気の圧力で水を飛ばす道具を作って遊びました。
うまくいかないとき、「こうかな?」「こうじゃない?」とあれこれやってみて、
やっているうちに「そうだ、こういうことやってみよ!」と閃いて、ためしています。
一人の子のアイデアで、ストローの先に空気の吹き込み口にプラスチックのコップ
を取りつけてみたら、うまくいきました。
「遊び」に近い自発的な活動のなかで何かに夢中になって関わると、
学習する時の考える力の持久力が変わってきます。
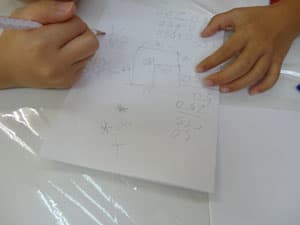
理科実験や工作の後で解いた「つるかめ算」などを面積図で解く問題。
集中して頭を使うような遊びをした後は、
見たことがない問題を解くときに、柔軟に多角的に考えて、
自力でやりきろうとする態度がアップします。
「もっと問題を出して!」とやる気が高まっていたので、
つるかめの足が200近いケースなど大きな数で問題を出しました。
すると「結局大きい数になったって、筆算する時に(ケタが)増えるだけでしょ?」
と自分なりに基本を応用させて解いていました。
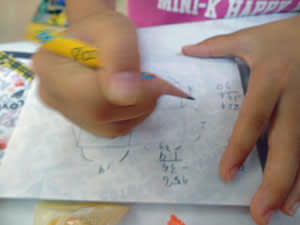
そういう姿を見ると、「あれもこれも」と将来役立ちそうな知識を詰め込んだり、
技能を訓練するよりも、
「ひとつのことにじっくり関わることを楽しめる」素地を養うことが大事だなと
思いました。
それは「うまくいかないとき、わからないとき」に簡単に他人に頼ったり、
放りだしたりしないで、自分で試行錯誤をしていくことにつながります。
子どもの遊びの世界を豊かにすることは、
そのまま子どもたちの学力の向上につながっていくことを今回も強く実感しました。



















