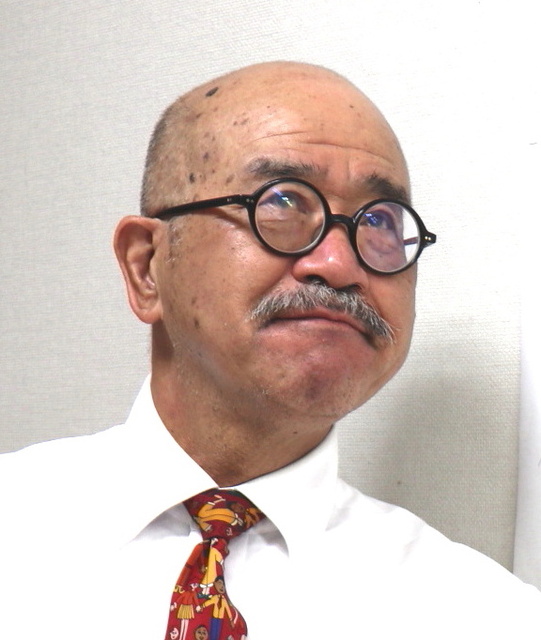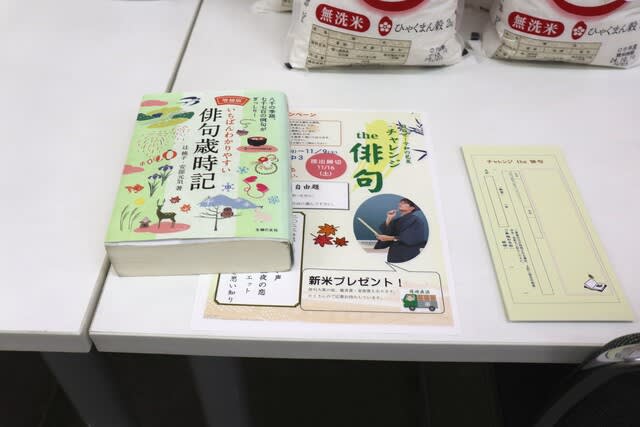



本社に行くときには、JR石山駅で京阪電車石坂線(石山寺-坂本)に乗り換えて、膳所本町で下車します。
が、うむ、たまには逆方向に乗ってみようか。
ちょっと時間に余裕があったのです。
JR石山駅で乗り換えて、瀬田川の方向へ2駅。終点の石山寺駅へ。
NHK大河ドラマ「光るんですか」に乗っかって、源氏物語、紫式部で売り出し中です。
手すりなどを紫色に塗って(紫ですから?)、平安時代のイメージの宣伝幕なども。
私は、スミマセンけれども、大河ドラマは最初だけ見て逃亡しました。
韓国ドラマのパクリですね。
ドロドロの人間模様。
陰謀、ワナ、嫉妬と恨み、呪い、毒。
立ち聞き。*韓国ドラマでは携帯電話の立ち聞きですが、平安時代には携帯電話が無かったから、すぐ近くの位置で聞きます。
まあ、大河ドラマで平安時代は無茶でしたなあ。
それならいっそ、古事記のほうがいいのじゃないか。ヤマタノオロチ退治など、ダイナミックに。
そんなわけで、私は京阪電車の写真を撮りました。
あ。「撮り鉄」というほどのものじゃないです。
でも、楽しい塗装(ラッピング)の電車が次々に来ます。
石山駅では、撮影しにくい。停車時間も短いし、光線の角度も逆光だったり。
乗降客が多いから、お客さんが画面に入ってしまうのです。
最近は、なにかと難しい時代でありまして、通学の高校生、特に女子高校生が画面に入ると、「わわっ!あのオジサン、怪しいやつではないか」というような方向の、あらぬ誤解を。クワバラ、桑原。
*『故事・俗信ことわざ大辞典』の「雷が鳴るとき桑原、桑原と言うと落雷しない」の項目には、3つの説が載っていた。
1つ目は、養蚕…桑を栽培してカイコを育て、繭(マユ)から生糸(絹)をとる…による収入が多かった農家では、だいじな桑畑が雷で荒らされないように、お察し下さいという意からとなえた、というもの。
2つ目は、雷が桑の木を嫌うとされるところから言った、というもの。
3つ目は、江戸時代の随筆「夏山雑談」「一挙博覧」などによれば、「桑原」は菅原道真の所領であった土地の名で、道真配流後、この桑原には一度も雷が落ちなかったという言い伝えから、落雷を防ぐ呪文になった、というものが書かれている。
〔岡山県立図書館のホームページから引用しました。〕
まあ、私は大型のCANONの一眼レフカメラを使っていて、しかもアヤシイと誤解されぬように、カメラから大きな操作音をバシャッ♪と出しています。
さすが日本製で、操作音も選んで音量を調整できる。最大音量にセットしています。
石山寺駅は終点で、ゆっくりと撮影できました。
楽しい電車が次々と。オススメです。
あ。駅で電車を見るばかりで、石山寺には…。
紫式部さん、ごめんなさい。
写真は、絵本作家の作品展のPR電車。もうクリスマスか。早いなあ。
そういえば、教室にもクリスマスの飾りが登場しています。
今日は中3クラスの授業へ。
中学校の授業の順番がユニークで、進むスピードも…。うむむ。
おうみ進学プラザの標準的な順番とは、かなりズレがあるのです。
こういう場合、「学校の授業なんか、知らんぞ!」では、生徒たちが困る。
かといって、ピッタリと中学の授業を追尾すると、急に…というケースもあります。
なぜかいきなり超スピードで進んだり、ジャンプ?したりするケースもありますよ。塾では、そのあたりを調整しながら、冬へ。
さいわい生徒たちが意欲的に取り組んでくれるから、これなら滋賀県内の私立高、県立の特色選抜までには仕上げていけそうです。
爽やかな晴れ。ただし、やや寒いか。
秋から冬へと進みます。