いつものように岐阜県図書館の新着図書の棚を見ていると、『アポカリプス・ベイビー』という書が目に付き、訳者の「あとがき」を当たってみると、2010年にミシェル・ウェルベックとフランスの芥川賞のようなゴンクール賞を争い、惜しくも次点だった著者とある。
このウェルベックであるが、新聞の図書欄で見かけ、面白そうなので岐阜県図書館にあるものを借りたところ、さまざまなフェイクやテロルに揺れるフランスを活写していて面白かったので、『セロトニン』『服従』『地図と領土』『ある島の可能性』『素粒子』など図書館にある彼のものはほとん読破した。
彼の小説は、レイシズムやミソジニー、フェイクなどなど、いわゆるポリティカル・コレクトネスなどどこ吹く風といった描写が続くのだが、それらの描写を通じて、パリの取り澄ました表層の下にあふれるまさに「他なるもの」の蠢きやそのテロルとしての顕現を掘り起こしてゆく。

そのウェルベックと肩を並べるというのだからヴィルジニー・デパントも面白いに違いないと早速借り出してきたのが『アポカリプス・ベイビー』であった。
大雑把にいうと、父親から素行調査を依頼されていた15歳の少女・ヴァランティーヌに捲かれるのみか失踪を許してしまった女性探偵が、もう少し野性的な女性探偵ハイエナの手を借りて少女を追いかけるという追跡ロードムービーのような筋立てである。
その叙述は、段落が代わるごとに記述の主体がそれぞれの登場人物に変わるという形式で、事態の進行がそれぞれの人物の思いを含む重層的なものであることが伝わる。物語の展開に従い、当然、重要人物ほど記述機会が多くなる。
ここで、恥しながら私自身の勝手な思い込みのミスについて告白すべきだろう。
この小説を読み始めてしばらくして、どこか違和感を感じて作家の名前をあらためてググッてみて愕然とした。この小説のややワイルドな表現や、ウェルベックなみのポリティカル・コレクトネス無視の記述スタイルからして、これは当然男性の手によるものだとばかり思っていたのだが、それが大間違いで、作者は女性だったのだ。

しかも、その経歴そのものがひとつの物語でもあるのだ。
彼女は、フランスの労働者階級の家庭に育ち、15歳の折、両親は彼女の意思に反して彼女を精神科病院に入院させたというのだ。その後の少女時代はヒッチハイクをしたり、ロックバンドを追いかけたりしていたが、17歳のとき、友人とヒッチハイクをしているとき、ライフルを持った3人の若者に脅され、輪姦されるという被害に遭ったという。そして成人後は、メイド、「マッサージパーラー」やのぞき小屋での売春婦、レコード店の販売員、フリーランスのロックジャーナリスト、ポルノ映画評論家をしていたというのだ。そして24歳で小説家としてデビューしたという。
私の間違いは、まずは外国人の名前につき、その男女の区別がつかないという無知によるもの、そして、ワイルドでハードボイル調の描写は男性によるものというなんの根拠もない誤った先入観によるものであった。
しかし、私が「ん?」と思ったのは、ミソジニー風の表現が出てきたり、いわゆる「ヴィアン」がかなりのウエイトで出てくるのだが、その描出の仕方が男性のそれではないような気がしたからだった(と、ひとまずは私のミスを取り繕うことにしておこう)。
小説の方に戻ろう。二人の女性探偵の追求は、パリを離れスペインのバルセロナへ至り、少女ヴァランティーヌを連れ戻すという任務には一応成功する。しかし、この少女は父親のもとには帰らなかった。永久に・・・・。この少女が身を挺した大惨事、まさにカタストロフィでありアポカリプスであった。
しかもそれを引き起こした方法というのがまったくもって奇想天外なのであるが、まったくありえないとはいえないのが現代なのだ。
なお、2010年に出版された(日本での翻訳は2021年)この小説は、その後、フランスを揺るがしたテロルの連鎖を予告したものとしての評価もあるという。
この小説が面白かったので、このデパントのもの2冊を読んだ。
『ヴェルノン・クロニクル 1「with the lights out 」』と『ヴェルノン・クロニクル 2「Just like Heaven」』だ。2冊合わせると700ページを超えるが、まあなんとかなるだろうと思って読んだ。
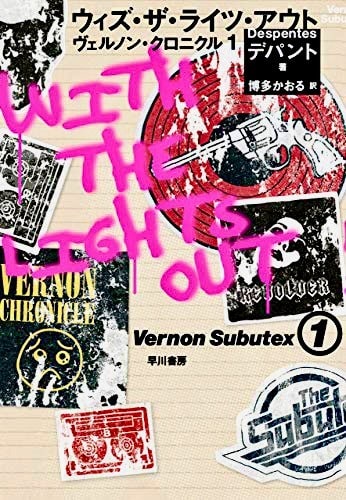
「1」の方は、かつてパリでロックを中心とした音楽愛好家たちにその品揃えの質量の豊かさで尊重されていたレコード店の店主ヴェルノンが、人々の音楽需要の形態の変化により、閉店へと追い込まれ、新しい職に就くこともできず、かつての友人たちの元を転々として泊まり歩くのだが、ついには泊めてくれるところもなくなり、ホームレスへと至る過程を述べる。
叙述のスタイルは、『アポカリプス・ベイビー』と同様、ヴェルノンと知り合った多数の人間のそれぞれを語り手として進行してゆく。それぞれの人達は、音楽の趣向、性愛のタイプ、ポルノ・DV・ドラッグなどへの向き合いを異にしながら生きている。「男も女もLGBTも、金持ちも貧乏人も、移民も難民も、老いも若きも、現代という壺の中に投げ込まれ掻き混ぜられ、毒と血と体液を塗され、日々生きている」(同書の感想文より)。
こうした群衆の叙述を通じてその時代の多様性を描写してゆく作風は、評論家をして、デパントを「現代のバルザック(1799~1850)」と言わしめるほどてある。
「2」の方は、すっかりホームレスの地位に落ち着き、もはや普通の家屋に泊めてもらうことすら負担に感じるようになったヴェルノンが登場するが、問題は彼が唯一持っていた、いまは亡き友人にして伝説のロックスター・アレックス・ブリーチの遺言とも言える独白を録画したカセットデッキの争奪戦と、その公開をめぐる話となる。

このカセットのなかでアレックスは、映画界で権力をもつディレクターが一人の女性をなぶり殺しにした事実を告発している。それを巡って復讐劇なども出てくるが、問題は、このカセットを観た限られた人たちの間に、ヴェルノンを中心とした緩やかなサークルが出現し、「1」でヴェルノンが泊まり歩いた人々、それを断った人たち、その後、偶然の機会で出会った周辺の人々を含み、とくにこれといった目標をもたない「無為の共同体」のようなものが出来上がったことだ。
これについて、ヴェルノンがなにか能動的な働きかけをしてるわけではない。ただし、彼には長年のレコード屋の経験を経ての音楽の評価能力、受容能力があり、それらを生かしたディスクジョッキーとしての音楽の選択能力は抜群で、彼がDJを務めるパーティや集まりに参加した面々はすっかりその虜になり、気づけばヴェルノンを取り巻く「無為の共同体」の一員になっているのだ。
この共同体は、ホームレスとなったヴェルノンの居場所の公園に集まる少数の集団にすぎない。そして、この集団がどうなってゆくのか、それは不明のまま小説は終わる。
ここで今一度、私自身の愚かさを告白しなければならない。
デパントの小説、『ヴェルノン・シリーズ 1・2』の700ページ超のものを読んだといった。たしかにその通り読んだ。しかし、この小説は私が当初考えたように、「1・2」がいわゆる「上・下」ではなく、「3」へと続くのだった。しかも、それに気づいたのは「2」をほとんど読み終える頃だったのだ。
だったら、「3」を読めばいいだけの話だろうということになる。しかし、しかし、しかしだ、フランスではもう「3」は出版されている(2017)ようなのだが、邦訳はまだないのだ。
いずれ邦訳は出るだろう。しかし、それまでにこちらの寿命がもつかどうかが問題なのだ。
【お願い】私が逝ったあとでこの小説の「3」を読んだ方は、私の墓前でその概要でけっこうですから、教えて下さい。
*『アポカリプス・ベイビー』 齋藤可津子:訳 早川書房
*『ヴェルノン・クロニクル 1「with the lights out」』 博多かおる:訳 早川書房
*『ヴェルノン・クロニクル 2「Just like Heaven」』 博多かおる:訳 早川書房
*『ヴェルノン・クロニクル 3』 日本語訳未刊




















































